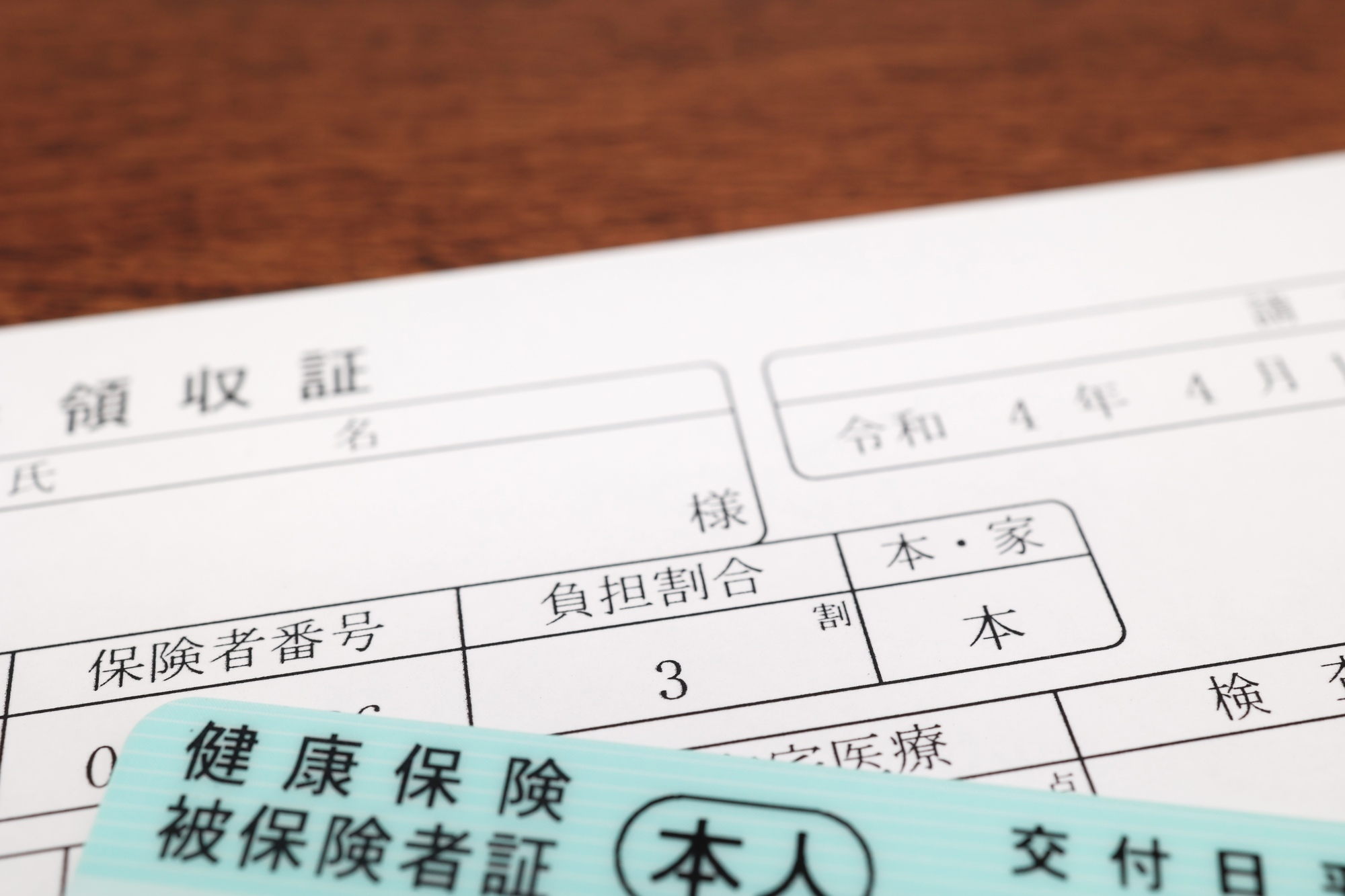顧客ニーズの多様化や少子高齢化などに伴って、さまざまな企業でイノベーションが求められるようになっていますが、どのようにイノベーションを起こせば良いのか分からない方もいるのではないでしょうか。
今回はイノベーションの基礎知識や代表的な種類、日本企業における成功事例などを解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
イノベーションとは?

イノベーション(Innovation)とは、技術や仕組み、発想を刷新し、新たな価値を創出することを指します。
この概念は現チェコ出身の経済学者ヨーゼフ・シュンペーター氏が1911年に提唱した「新結合(ニューコンビネーション)」に由来し、現代に至るまで多くの起業家たちに大きな影響を与え続けています。
イノベーションは新技術の開発のみに限らず、商品やサービス、ビジネスモデル、組織体制の変革など新たな価値を生み出す創造的な革新も含まれます。
日本語では「革新」「技術革新」などと訳され、近年では社会課題の解決や競争力強化の鍵として、ますます注目されています。
経済産業省による定義
経済産業省は「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」で、イノベーションを以下のように定義しています。
【「イノベーションの定義」】
研究開発活動にとどまらず、
1. 社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)で新たな価値(製品・サービス)を創造し
2. 社会・顧客への普及・浸透を通じて
3. ビジネス上の対価(キャッシュ)を獲得する一連の活動を「イノベーション」と呼ぶ
出典:経済産業省「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
イノベーションが必要な背景

以下の現代社会のさまざまな課題や環境変化によって、企業にはイノベーションが求められています。
【1.技術の急速な進化】
AIやIoTなど新技術の登場により、従来のビジネスモデルでは対応が難しい場面が増え、企業は競争力維持のために常に革新を求められています。
【2.人口減少と高齢化】
日本を含む多くの先進国では人口構造の変化が進み、労働力不足や社会保障の負担増などが深刻化しています。こうした課題に対応するには、新たな仕組みやサービスの導入が欠かせません。
【3.グローバル競争の激化】
海外企業との競争が激しくなる中で、生き残るためには差別化された製品・サービスを生み出す必要があります。
【4.顧客ニーズの多様化】
顧客の価値観やライフスタイルが多様化する中で、従来の画一的な商品・サービスでは顧客の期待に応えることが難しく、柔軟な発想が求められています。
【5.経済効果の大きさ】
イノベーションによって新たな産業や市場が生まれ、雇用創出や生産性向上が期待できます。地域経済の活性化や国全体の経済成長にも直結するため、大きな波及効果があります。
イノベーションの種類

イノベーションは提唱する経営学者によって定義が異なりますが、どのような種類があるのでしょうか。
ここではイノベーションの代表的な種類を紹介していきます。
シュンペーターによる分類
イノベーションを初めて提唱した故ヨーゼフ・シュンペーター氏は、イノベーションこそが経済発展の原動力であり、以下5つの類型によって成り立っているとしています。
- プロダクト・イノベーション
- プロセス・イノベーション
- マーケット・イノベーション
- サプライチェーン・イノベーション
- オルガニゼーション・イノベーション
それぞれ詳しく解説していきます。
プロダクト・イノベーション
プロダクト・イノベーション(商品やサービスの創出)は、これまで市場に存在しなかった製品やサービスを開発し、社会に新たな価値を提供することです。
例えばAppleが発売したiPhoneは、電話・音楽・インターネット機能を1つに統合した画期的な製品であり、スマートフォン市場を新たに創出することになりました。
新製品は消費者のライフスタイルを一変させ、大きな経済効果をもたらします。
プロセス・イノベーション
プロセス・イノベーション(生産・流通方法の創出)は、製品やサービスの生産工程に新たな技術や仕組みを導入し、効率や品質を向上させることです。
例えばトヨタ自動車株式会社の「カンバン方式」は、必要な部品を必要なときに供給する方式で、在庫コストの削減と生産性の向上を実現しました。
マーケット・イノベーション
マーケット・イノベーション(市場の創出)は、既存の商品・サービスを新たな地域や顧客層に展開し、新しい需要を創り出すことです。
例えば株式会社ユニクロは海外進出によって、日本国内で成熟した市場とは別に、アジアや欧米などの新市場を開拓しました。
その後、ブランドのグローバル化に成功し、売上を大きく伸ばしました。
サプライチェーン・イノベーション
サプライチェーン・イノベーション(供給方法の創出)は、従来とは異なる原材料やエネルギー源、調達先を利用して、コストやリスクの低減を図ることです。
例えば、多くの電力会社が火力発電から太陽光や風力などの再生可能エネルギーへと移行していますが、これは環境負荷の軽減と安定供給を両立させるサプライチェーン・イノベーションの一環だといえます。
オルガニゼーション・イノベーション
オルガニゼーション・イノベーション(組織の創出)は、経営体制や企業構造を見直し、より柔軟で効率的な運営を目指すことです。
例えばソニーグループ株式会社は一部事業を分社化し、各部門に意思決定の自由度を持たせることでスピーディーな経営を実現しました。この組織改革により、競争力と利益を向上させています。
シュンペーター氏は、前述したイノベーションを推進する人物を起業者(アントレプレナー)と呼び、彼らこそが経済に「創造的破壊」をもたらし、従来の仕組みを壊しながら新たな価値を創造すると提唱しました。
この考え方は現代のベンチャー企業やDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略にも大きな影響を与え続けています。
クリステンセンによる分類
イノベーション研究の第一人者でハーバード・ビジネス・スクールの著名な教授でもあった実業家の故クレイトン・クリステンセン氏は、著書の「イノベーションのジレンマ」でイノベーションには以下の2種類があると提唱しています。
- 持続的イノベーション
- 破壊的イノベーション
それぞれ詳しく解説していきます。
持続的イノベーション
持続的イノベーションは既存の商品やサービスを段階的に改良し、性能や品質を向上させるイノベーションです。主に既存顧客のニーズに応え、競争優位性を強化していきます。
例えば自動車メーカーによる燃費性能や安全機能の向上は、既存技術を進化させつつ、競争力を維持する代表的な事例です。
破壊的イノベーション
破壊的イノベーションは、既存の市場構造や価値観を根本から変える革新的な技術やビジネスモデルです。初期は低価格・低性能でも、新たな市場を生み出し、やがて主流となるケースがあります。
例えばNetflixはDVDレンタル中心だった映像業界にストリーミングという新モデルを導入し、従来のビジネスを一変させました。
イノベーションのジレンマ
イノベーションのジレンマとは、破壊的イノベーションによって市場優位になった企業が既存商品・サービスの品質改善・維持に注力するあまり、競合の破壊的イノベーションへの対応が遅れ、市場の主導権を失ってしまう現象です。
破壊的イノベーションによって誕生した新技術・サービスは、初期段階では性能や利益が低限定的に見えるものの、成長とともに市場を再定義し、いずれ既存企業に大きな脅威となります。
すでに成功している市場優位になった企業はイノベーションのジレンマにどう向き合うかが成長の鍵となります。
例えば世界初のカーラジオや携帯電話を生み出し、1990年代には世界のアナログ式携帯電話市場でシェア率60%超を誇っていた老舗企業のモトローラ社は、長きにわたる数々の破壊的イノベーションによって、世界有数のテクノロジー企業へと成長していました。
しかし1990年代中期に差し掛かると、自ら築き上げたアナログ式携帯電話市場を覆しかねないデジタル式携帯電話に慎重になったことで、競合に出遅れてしまいました。
結果的に1998年にはノキア社にトップの座を奪われ、その後も凋落していくことになりました。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
ヘンリー・チェスブロウによる分類
イノベーション戦略や技術経営に関する世界的な第一人者でカリフォルニア大学バークレー校ハース・ビジネススクールの教授を務めるヘンリー・チェスブロウ氏は、著書の「オープンイノベーション」でイノベーションには以下の2種類があると提唱しています。
- オープンイノベーション
- クローズドイノベーション
それぞれ詳しく解説していきます。
オープンイノベーション
オープンイノベーションとは自社だけでなく他社や大学、顧客など外部の知識や技術を活用し、新たな価値を創出する手法です。
例えば米国の印刷機器メーカーのゼロックスが運営するパロアルト研究所では、1979年から業界関係者向けに見学コースを設けており、開発中の製品のデモをおこなっていました。
その中にはGUIとマウスを使った世界初のPCであるAltoがあり、これを見学したスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツは、そのコンセプトを応用し、それぞれMacintoshやWindowsを開発しました。
クローズドイノベーション
クローズドイノベーションは、自社内の技術や人材だけで開発を進める従来の閉鎖的な手法のことであり、外部への知見の共有や連携はおこないません。知的財産の保護には有利であるものの、顧客ニーズや市場トレンドの変化に対応が遅れるリスクがあります。
代表的な例として、かつて世界最大手のカメラ・フィルムメーカーであったイーストマン・コダックが挙げられます。
同社では1975年にエンジニアであったスティーブ・サッソン氏が世界初のデジタルカメラの開発に成功しました。
しかし写真フィルムに依存したビジネスモデルを脅かす存在だとして恐怖した経営陣は、彼の功績を冷遇し、デジタルカメラの誕生を口外禁止にしました。
その後、密かにデジタルカメラ事業への投資自体はおこなわれたものの、当時の経営陣が顧客ニーズを読み取れていなかったことと写真フィルムに対する誇りが大きな障壁となって、本格的にデジタルカメラ事業に重心を移すことはありませんでした。
結果として、ソニーやキャノンなどの競合に大きな遅れを取ることになり、写真フィルム市場の縮小に伴う赤字が拡大した結果、2012年に経営破綻に追い込まれました。
2013年に再建を果たしたものの、かつての影響力は失われ、現在はデジタル印刷や商業印刷などの分野に注力しています。
日本政府によるイノベーションの取り組み

内閣府の「第6期科学技術・イノベーション基本計画」で説明されてるように、日本政府では2021年から2025年の期間で以下の施策のために30兆円の投資をおこなっています。
- 政府のデジタル化
- 宇宙システム・量子技術・半導体等の次世代インフラや技術の整備・開発
- カーボンニュートラルに向けた研究開発
- スマートシティ・スーパーシティの創出
- 博士課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大
- 若手研究者ポストの確保など
日本企業のイノベーションの現状と事例

東京商工会議所の『「中小企業のイノベーション実態調査」報告書』で説明されているように、都内23区で活動する10,000社のうち、イノベーション活動に取り組んでいる企業は全体の73.0%、競合が導入していない新たなイノベーションに取り組んでいる企業が全体の30.5%を占めます。
この調査結果からも分かるように、日本企業においてもイノベーションは身近な存在だと言えますが、どのような事例があるのでしょうか。
ここでは日本企業におけるイノベーションの成功事例を紹介していきます。
富士フイルム株式会社
富士フイルム株式会社は、かつて写真フィルムやカメラの製造販売を主力事業とし、大きな成功を収めていました。しかし、デジタルカメラの普及による市場縮小を受け、事業の転換を図ります。
新たに本格参入したのは、化粧品・医薬品・再生医療の3分野でいずれも一見は無関係の異業種ですが、実際には写真フィルムで培った技術や知識を活かせる領域でした。
同社はこれらの分野で技術を転用し、数多くの製品開発に成功。大胆な事業転換によって、急速な成長を遂げています。
株式会社田代合金所
1914年創業の株式会社田代合金所は、システム開発や合金製造を手がける企業で、これまでに数々のイノベーションを実現してきました。
かつては新聞社向けの版印刷用合金の製造が主力でしたが、やがて合金を必要としないオフセット印刷の普及により、その需要は激減しました。
そこで同社は、合金製造で培った鋳造技術をアクセサリーやベルトのバックルに応用し、国内シェアの半数以上を獲得するまでに成長します。
さらに合金技術を活かした内装材を展開し、独自性の高い製品の開発に成功。国内外で高く評価され、現在では海外市場にも販路を拡大しています。
ヤマト運輸株式会社
1919年創業のヤマト運輸株式会社は、当初トラック運送を主な事業とし、三越百貨店との輸送契約により安定した収益を得ていました。しかし、長距離輸送市場への参入が遅れたことに加え、オイルショックの影響も重なり、1973年には存続の危機に直面します。
この状況下で創業者の後を継ぎ社長に就任した小倉昌男氏は、新たな収益源として個人向け宅配サービス「クロネコヤマトの宅配便」を開始しました。
当時、個人宅配はコスト高で採算が取れないとされ、競合他社の参入はほとんどありませんでした。しかし、小倉昌男氏は「荷物の密度を高めれば十分に成り立つ」と確信し、営業所で荷物を集約し、小型トラックで周辺地域へ配達する現在の宅配システムの原型を築きました。
サービス開始当初は関東地方に限定されていましたが、需要の増加に伴い全国へと展開。これをきっかけとして、中小企業だったヤマト運輸株式会社は売上高1兆円を超える大手運輸企業へと成長を遂げました。
トヨタ自動車株式会社
世界最大の自動車メーカーであるトヨタ自動車株式会社は、自動運転やデジタル化、若者の車離れ、カーボンニュートラルといった外的要因を受け、「社会価値を創出するモビリティ企業」への転換を進めています。
イノベーションの柱として、MaaS(Mobility as a Service)、自動運転技術、EV(電気自動車)などを幅広く展開し、「移動」の概念を再定義するとともに、社会課題の包括的な解決を目指すビジョンを掲げています。
2021年には、静岡県裾野市で未来型スマートシティ「Woven City(ウーブン・シティ)」の建設を開始。自動運転、AI、再生可能エネルギー、ロボティクスなどの最先端技術の実証実験の場として注目されています。
トヨタは、車中心の移動手段を超え、都市インフラと融合する新たな価値の創出を目指しており、そのイノベーションは世界中から関心を集めています。
任天堂株式会社
1889年に花札の製造から始まった任天堂株式会社は、ファミリーコンピュータ(ファミコン)やゲームボーイで世界的な成功を収めてきました。
しかし2000年代に入ってから高性能なゲーム機を発表するソニーやマイクロソフトなどに遅れを取るようになり、任天堂は徐々に競争力を失っていきます。
当時、ゲーム業界の首位はPlayStation2を擁するソニーに奪われていましたが、任天堂株式会社は「誰もが楽しめる」をコンセプトにゲーム機Wiiを開発しました。
同社は高性能競争に加わるのではなく、モーションセンサーによる直感的な操作を取り入れることで、子どもから高齢者まで幅広い層に訴求しました。
かつて「ゲームは家族の時間を奪うもの」とされていた固定観念を、「家族みんなで楽しめる」「絆を深めるためのツール」へと再定義し、大ヒットとなるWiiを生み出します。これにより、業界の首位を奪還しました。
このコンセプトはNintendo Switchにも受け継がれており、世界での販売台数を大きく伸ばし、業績がV字回復しています。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
イノベーションの本質は技術革新だけでなく、新たな価値を創出することであり、身近な存在であるともいえます。
破壊的イノベーションによって成功を収めた企業は、持続的イノベーションに注力するあまり、競合に先を越されてしまうおそれがあるため、オープンイノベーションを活用しながらイノベーションし続けられるように努めると良いでしょう。
これから初めての起業や異業種参入を検討している方は、フランチャイズへの加盟も1つの手です。
フランチャイズは業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、集客や営業、商品開発、仕入れなどをサポートしているため、初めてでも成功しやすい傾向にあります。