生活支援員は、障がいがある方の日常生活などをサポートする重要な専門職であり、障がい者数の増加や少子高齢化の拡大によって、今後も需要が増していくと考えられています。
しかし生活支援員に興味を持ったばかりという方の中には、主な仕事内容や平均給与などが分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は生活支援員の概要や支援対象者、仕事内容、働く場所、役立つ資格などを網羅的に解説していきます。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
生活支援員とは

生活支援員は、障がいのある方の日常生活や社会参加をサポートする専門職です。主に以下のような役割を担います。
- 食事・入浴・排せつなどの生活介助
- コミュニケーション支援や見守り
- 社会活動や就労支援の補助
支援対象者は知的・身体・精神に障がいのある方で、働く場所はグループホームや福祉施設、就労支援事業所など多岐にわたります。
ここでは生活支援員の主な役割と責任、支援対象者、働く場所について詳しく解説します。
主な役割と責任
生活支援員の主な役割は、知的・身体的・精神的な障がいのある方の自立を促し、日常生活を支える専門職です。
主な業務は、食事・排せつ・入浴・着替えなどの生活介助のほか、金銭管理、買い物、通院の付き添いなど多岐にわたります。
生活支援は単なる「手助け」ではなく、サービス利用者の残存機能(心身に障がいのある方に残されている機能)を活かすサポートが重視されています。
たとえば、片手が動く方には自分で食事ができるように食器の工夫をおこなったり、知的障がいがある方にはイラスト入りの手順書を用いて家事の自立を促したりします。
こうした個別支援を通じて、利用者の「できること」を増やし、自己肯定感の向上や社会参加へとつなげていくことが、生活支援員の大切な役割です。
支援対象者
生活支援員の支援対象者は、身体障がい・知的障がい・精神障がい者、認知症の高齢者など多岐にわたります。
身体障がいのある方は移動や動作の補助が必要であり、知的障がいのある方には理解力に応じた丁寧な説明や見守りが求められます。
精神障がいのある方には、感情の変化に配慮した落ち着いた対応が重要です。
年齢層も幅広く、10代の発達障がい者には就学や生活リズムの支援が必要な一方で、中高年のサービス利用者には金銭管理や健康維持へのサポートが中心となる場合もあります。
このように、サービス利用者一人ひとりの特性やライフステージに合わせた柔軟な支援が求められます。
働く場所
生活支援員の働く場所は多岐にわたり、施設の種類によって支援内容も異なります。主な勤務先と特徴は以下の通りです。
【障がい者向けグループホーム(共同生活援助施設)】
・少人数での共同生活を支援
・食事、入浴、服薬管理などの日常生活全般をサポート
【就労継続支援A型・B型事業所】
・軽作業や内職などの仕事を通じた支援
・就労習慣の定着や社会性の向上を目指す
【生活介護施設】
・重度障がい者のための日中活動支援
・創作活動、リハビリ、医療的ケアの補助などを実施
【高齢者施設(特別養護老人ホームなど)】
・要介護高齢者の生活支援や身体介助
・認知症ケアやレクリエーション活動も担当
それぞれの施設でサービス利用者の状態やニーズが異なるため、状況に応じた柔軟な支援が求められます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
主な仕事内容

生活支援員の主な仕事は、障がい者や高齢者の自立を支えるための支援業務です。具体的な業務は以下の通りです。
- 食事・入浴・排せつなどの身体介助
- 掃除・洗濯・調理などの生活援助
- 金銭管理や通院の付き添い
- レクリエーションや社会参加の支援
ここでは、こうした日常生活の支援の詳細と生活支援員の1日のスケジュール例について解説します。
日常生活の支援
生活支援員は、サービス利用者が安心して暮らせるようサポートします。主な支援内容には、以下のような介助があります。
【食事介助】
自力で食べられない方へのスプーンでの介助や、誤嚥を防ぐための姿勢調整・食事形態の工夫などをおこないます。
【入浴介助】
転倒防止の見守りや身体の清潔を保つための洗体補助などを実施します。
【排せつ介助】
トイレ誘導やオムツ交換など、プライバシーに配慮しながら対応します。
またサービス利用者の自立を促すため、「できる部分は自分でおこなってもらう」といった一部介助も重要です。
たとえば、箸の持ち方を工夫したり、衣服に目印をつけて着替えやすくするなど、個々の能力に合わせた工夫を通じて「できること」を少しずつ増やす支援が求められます。
1日のスケジュール例
生活支援員の1日の流れは、施設の種類やサービス利用者の生活スタイルによって異なります。ここでは、グループホーム勤務の場合の一般的なスケジュール例をご紹介します。
| 時間帯 | 業務内容 |
| 7:00から9:00 | 起床支援、洗面・着替え介助、朝食準備・配膳・介助、服薬確認、通所先への送迎対応 |
| 9:00から12:00 | 掃除・洗濯などの家事支援、記録業務、ミーティング、病院付き添いや買い物支援など |
| 12:00から13:00 | 昼食の調理・配膳・介助、服薬管理、食後の片付け |
| 13:00から16:00 | 体調確認、レクリエーション、個別支援、金銭管理の補助、外出支援など |
| 16:00から18:00 | 帰宅受け入れ、夕食準備・配膳・介助、入浴介助、夜間の見守り準備など |
このように生活支援員は、1日を通してサービス利用者の生活に寄り添い、日常動作のサポートや自立支援をおこないます。施設によっては夜勤がある場合もあります。
生活支援員の給料の実態

生活支援員の給料は、以下の要因によって変動します。
- 経験年数や資格の有無
- 勤務先の地域や施設形態
- 夜勤や手当の有無
処遇改善加算や各種手当が加わることで収入が増えるケースもあります。ここでは、生活支援員の平均年収と給与体系について詳しく解説します。
平均年収と給与体系
厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」によれば、2024年の生活支援員を含む福祉・介護職員(常勤)の平均給与は327,720円でした。その内訳は以下の通りです。
| 項目 | 平均金額(円) |
| 基本給 | 207,810円 |
| 手当 | 69,920円 |
| 一時金(賞与等) | 50,000円 |
| 合計 | 327,720円 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」
手当には、職務・処遇改善・通勤・家族手当に加え、早朝・深夜・休日勤務などの時間外手当も含まれます。資格を持っている場合は職務手当が上乗せされ、給与を増やすことができます。
また平均給与は、以下のようにサービス・入居施設の種類によって大きな開きがあり、医療型障害児入居施設の給与が最も高い傾向にあります。
| 全体平均 | 327,720円 |
| 居宅介護 | 317,550円 |
| 重度訪問介護 | 347,540円 |
| 生活介護 | 317,000円 |
| 施設入居支援 | 371,620円 |
| 就労継続支援A型 | 289,060円 |
| 就労継続支援B型 | 289,130円 |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 291,050円 |
| 児童発達支援 | 293,940円 |
| 放課後等デイサービス | 286,110円 |
| 福祉型障害児入所施設 | 394,030円 |
| 医療型障害児入所施設 | 410,840円 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」
さらに勤続年数に比例して平均給与は増えていき、次のように勤続年数1年では290,680円ですが、10年以上になると373,370円に達します。
| 平均年齢(歳) | 平均給与 | |
| 全体(平均勤続年数7.9年) | 44.9 | 327,720円 |
| 1年(勤続1年から1年11ヶ月) | 40.5 | 290,680円 |
| 2年(勤続2年から2年11ヶ月) | 40.9 | 299,490円 |
| 3年(勤続3年から3年11ヶ月) | 41.9 | 296,750円 |
| 4年(勤続4年から4年11ヶ月) | 43.0 | 310,240円 |
| 5年から9年 | 45.5 | 324,130円 |
| 10年以上 | 49.4 | 373,370円 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
生活支援員に向いている人の特徴は?

生活支援員に向いている人の特徴は、以下のような資質を持つ方です。
- 人の気持ちに寄り添える共感力がある
- 状況に応じて柔軟に対応できる
- 小さな変化にも気づける観察力がある
- 根気強く支援を続けられる忍耐力がある
体力的・精神的な負担はあるものの、支援を通じて「できることが増えた」「笑顔が見られた」といったやりがいを感じられます。
ここでは、生活支援員がやりがいを感じる瞬間について詳しく解説します。
やりがいを感じる瞬間
生活支援員のやりがいは、サービス利用者の小さな変化や成長に気づけた瞬間、そして感謝の言葉をもらえたときに強く感じられます。
日々の支援は地道なものとなりますが、信頼関係の積み重ねがサービス利用者の笑顔や行動の変化につながります。
▼生活支援員Aさん(40代・女性)
「毎朝あいさつを続けていたサービス利用者が、ある日初めて“おはよう”と返してくれて、涙が出るほど嬉しかったです。」
▼生活支援員Bさん(30代・男性)
「いつも無表情だった利用者が、自分の作ったおやつに“おいしい”と微笑んでくれて、すべてが報われた気がしました。」
こうした日々の小さな変化こそが、生活支援員にとって大きなやりがいであり、支援を続ける原動力となっています。
生活支援員に必要な資格は?
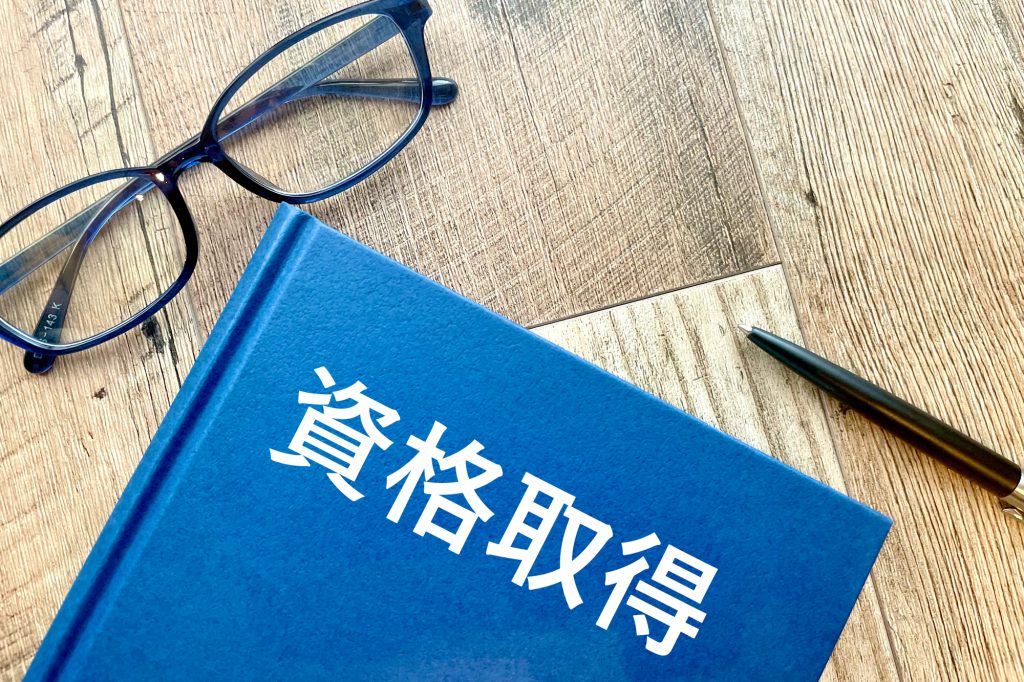
生活支援員として働くために必須の資格はありませんが、以下のような関連資格を持っていると採用や業務の面で有利になります。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
これらの資格を持っていると、支援の幅が広がるだけでなく、処遇改善手当の対象となることもあります。
ここでは、生活支援員に役立つ主な資格について詳しく解説します。
必須資格の有無
生活支援員として働くうえで、法的に必須とされている資格はありません。無資格・未経験でも採用されるケースは多く、特に障がい者グループホームや生活介護施設では、人柄や意欲重視で採用される傾向にあります。
ただし、施設の方針や支援内容によっては、介護職員初任者研修などの資格を保有していることが望ましいとする場合もあります。
また重度障がい者の医療的ケアが必要な施設では、一定の知識やスキルが求められることもあります。
施設の種類や支援レベルに応じて求められる条件は異なるため、求人票や事業所の説明を確認することが大切です。
取得すると有利な資格
生活支援員として働くうえで、以下の資格を取得しておくとスキルの証明やキャリアアップに有利になるほか、毎月の手当てが増えます。
【介護職員初任者研修】
・介護の基本を学ぶ入門資格で訪問・施設の両方で活用可能
・受講期間は1から2ヶ月、費用は5万円から10万円前後
・資格手当の相場:月5,000円程度
【介護福祉士(国家資格)】
・実務経験(原則3年以上)と実務者研修の修了が必要
・費用は研修・受験等で10万円から15万円前後
・資格手当の相場:月10,000円から20,000円前後で、役職手当や昇給にも直結することもある
【社会福祉士・精神保健福祉士(国家資格)】
・相談業務やサービス管理責任者など、上位職への道が広がる
・大学または養成校の履修が必要で、費用は20万円から40万円前後
・資格手当の相場:月10,000円から15,000円前後で配置加算の対象にもなりやすい
これらの資格を取得することで、実務上の信頼性が高まるだけでなく、処遇改善加算の対象にもなるため、給与面でも有利になります。資格取得はキャリアアップの大きな一歩となります。
よくある質問
生活支援員の資格はどうやって取りますか?
生活支援員に必須資格はありませんが、介護職員初任者研修などは民間スクールや通信講座で受講・修了することで取得できます。働きながら通う人も多くいます。
生活支援員は誰でもなれるの?
生活支援員は資格や経験がなくても働ける職場が多く、基本的に誰でも目指せます。人柄や意欲が重視されるため、未経験からの挑戦も可能です。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
生活支援員は、障がいや高齢によって支援が必要な方の生活を支える大切な仕事です。資格がなくても始められ、人の成長を間近で感じられるやりがいがあります。
その一方で、給与水準は施設や経験によって大きな差があり、高収入を目指すには時間がかかる場合もあります。
福祉分野に関心があり、より早く安定した収益を目指したい方には、福祉フランチャイズ加盟店のオーナーという選択肢も有力です。
福祉フランチャイズは、本部が経営ノウハウを共有しているほか、行政対応や書類作成代行、営業、集客などをサポートしているため、未経験でも成功しやすい傾向にあります。
経営を通じて支援に関わる道もあるため、検討してみると良いでしょう。









