精神科訪問看護は、在宅での医療的ケア支援が必要な方の増加に伴い、需要が拡大しているサービスですが、どういったサービスが提供されているのか知らない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は精神科訪問看護の基礎知識や主な対象者、提供されているサービス、利用するメリットなどを紹介していきます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
精神科訪問看護の役割をわかりやすく解説

精神科訪問看護は、看護師や精神科での勤務経験を持つスタッフが自宅を訪問し、心身の状態を専門的にサポートする医療サービスです。
心の安定や症状の変化を丁寧に観察しながら、生活リズムの改善や症状の再発予防につなげる支援が特徴です。
日常生活の介助が中心となる訪問介護とは異なり、医療的な判断と心理面のフォローを組み合わせて支援します。
服薬状況の確認、ストレス要因の整理、体調悪化の兆しの早期発見など、医療と生活の間をつなぐ役割を担い、利用者が自宅で安心して暮らし続けられるようサポートします。
どんな人が対象?精神科訪問看護を利用できる人の特徴

精神科訪問看護は一定の条件を満たした方のみが利用できるサービスです。ここでは精神科訪問看護の主な対象者を解説していきます。
精神疾患の診断がある人
精神科訪問看護の対象となるのは、医師から精神疾患の診断を受けている方です。主な例としては、統合失調症、うつ病、双極性障害、パニック症などがあげられます。
これらの疾患は体調や気分が日によって変動しやすく、通院だけでは十分なフォローが難しい場合があります。そのため、自宅での継続的な支援として精神科訪問看護の利用が適しています。
精神科訪問看護では、専門職が利用者に寄り添い、安心して生活を続けられるようサポートします。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
具体的な病名がなくても利用できるケース
精神科訪問看護は、診断名が確定していなくても利用できる場合があります。例えば主に以下の症状が見られ、日常生活に支障をきたしているケースでは、医師が在宅での医療的支援を必要と判断することがあります。
- 睡眠不足が続いている
- 強い不安や緊張で外出が難しい
- ひきこもり傾向が強まっているなど
病名が確定していない段階でも精神科訪問看護が早期の支援介入としても活用され、生活の安定や通院継続につながる役割を担っています。
年齢や状態による制限はある?
精神科訪問看護は、年齢による利用制限がなく、小児から高齢者まで幅広く利用できます。
発達段階に応じた支援が必要な子どもから、症状の変動が生活に影響しやすい成人、精神症状が再燃しやすい高齢者まで、それぞれの状態に合わせた医療的フォローが可能です。
ただし、高齢者の場合は介護保険との関係に注意が必要です。65歳以上で要介護認定を受けている方は、原則として介護保険での訪問看護が優先され、医療保険が使えるのは医師が特別な理由を認めたケースに限られることがあります。
サポートが家族の負担になっているケースも対象
精神科訪問看護は、本人の症状安定だけでなく、家族の負担が大きくなっている場合にも有効です。
精神症状の変動が続くと、家族が見守りや声かけ、通院管理を担う場面が増え、心身の負担が蓄積しやすくなります。
訪問看護では、看護師が定期的に自宅を訪れ、症状の観察や服薬確認、生活リズムの調整などの医療的フォローをおこなうため、家族の負担を軽減しやすい点が特徴です。また、家族が抱える不安や対応方法について相談できる点も大きなメリットです。
看護師が状況を整理し、必要に応じて主治医や相談支援専門員と連携することで、家族だけでは抱えきれない問題を専門職と共有できます。
こうした支援により、家庭全体の安心感を高めながら、継続的なサポート体制を整えられます。
精神科訪問看護で受けられる主なサポート内容

精神科訪問看護で提供している主なサポート内容と制度上の理由で提供できない対応を紹介していきます。
症状悪化を防ぐためのメンタルケア
精神科訪問看護では、症状悪化を防ぐためのメンタルケアをおこないます。不安・緊張・落ち込み・希死念慮といった心の変化を丁寧にチェックし、悪化の早期兆候を見逃さないよう観察します。
兆候が見られた場合は、生活リズムの調整や環境づくりなど具体的な予防策を考えます。また、気分の波を日々把握し、再発につながらないよう対策を講じながら、安定した生活の継続を支援します。
内服管理と副作用のチェック
精神科訪問看護では、内服管理と副作用のチェックをおこないます。飲み忘れや自己判断での服薬中断を防ぐため、服薬状況を確認し、続けやすい方法を整えます。
また副作用によって日常生活に支障が出ていないかを観察し、変化があれば速やかに医師へ報告します。
生活リズム・セルフケア支援
精神科訪問看護では、生活リズムやセルフケアの支援も重要な役割です。睡眠や食事の乱れ、活動量の偏りなどを一緒に確認し、無理のない方法で改善していきます。
また起床・就寝時間、食事の時間の安定化など、生活リズムを整えるための具体的なサポートもおこないます。
コミュニケーション支援
精神科訪問看護では、対人関係に不安を抱える方へのコミュニケーション支援もおこないます。
人との会話に緊張しやすい、言いたいことがうまく伝えられない、誤解が生じやすいといった悩みに対して、看護師が状況を整理しながら、安心して話せる練習や言葉の選び方を確認します。
またミスコミュニケーションが起きた場面を振り返り、トラブルを避けるための対応を考えることで、不安を軽減し、円滑なやり取りをサポートします。
就労・社会参加を見据えた支援
精神科訪問看護では、就労や社会参加を見据えた支援もおこないます。まずはA型・B型事業所などの日中活動に参加しやすいように体調管理や生活リズムの調整をサポートします。
働きたい方には、症状の安定化や通所・就労に向けた行動面の課題を整理し、実現に向けた対応をおこないます。
また社会的リハビリテーションとして、対人場面での不安やつまずきやすいポイントを振り返り、社会参加に向けた準備を整えることで、本人が安心してステップアップできるように支えます。
家族への支援と助言
精神科訪問看護では、家族への支援と助言も重要な役割です。症状が不安定なときの接し方や声掛けの工夫など、家庭内で実践しやすい関わり方を整理し、家族の不安を軽減します。
また、状態の変化や気になる点があれば看護師が医師へ共有し、必要な医療につながるよう調整します。
家族だけで抱え込まずに相談できる環境を整えることで、利用者本人と家族の双方を支える体制づくりをサポートします。
医師・相談支援員・他職種との連携
精神科訪問看護では、状況に応じて主治医・看護師・相談支援員などの複数の専門職が連携しながら支援します。連携が必要になるのは、たとえば以下のような場合です。
- 症状が不安定になり、治療の調整が必要なとき
- A型・B型・グループホームなど日中活動や生活面で課題があるとき
- 服薬管理や副作用に不安が生じたときなど
こうした場面では主治医へ状態を共有し、複数の専門職が支援方針をすり合わせます。また必要に応じて訪問頻度の調整や緊急対応につなげ、支援が途切れない体制を整えます。
精神科訪問看護でできないこと
精神科訪問看護は医療的ケアを提供するサービスであり、できないことも明確に定められています。具体的には、主に以下の対応は対象外です。
- 料理・掃除などの家事代行
- 買い物や外出の同行
- 金銭管理や支払い代行
- 法律相談や専門的な契約手続き
- 医療行為の一部(注射・採血・点滴など医師の指示なくおこなえない行為)など
また、長時間の見守りや介護保険サービスの代替となる支援もできません。精神科訪問看護は、あくまで医療・心理面のフォローを中心に、在宅生活を安全に続けるための専門的支援をおこなうサービスです。
精神科訪問看護の利用料金と負担割合

精神科訪問看護の利用料金は所得や年齢などによって異なります。ここでは精神科訪問看護の利用料金と自己負担の割合を説明していきます。
医療保険が適用される場合
精神科訪問看護は、ほとんどの場合医療保険が適用され、自己負担は1割から3割となります。以下のように現役世代は原則3割負担、高齢者は所得に応じて1割から3割に区分されます。
| 区分 | 年齢 | 所得などの条件 | 自己負担割合 |
| 一般 | 65歳以上(第1号被保険者) | 年金+その他所得が一定以下 | 1割 |
| 現役並み所得者(Ⅰ) | 65歳以上 | 年収:約383万円以上(世帯) | 2割 |
| 現役並み所得者(Ⅱ) | 65歳以上 | 年収:約463万円以上(世帯) | 3割 |
| 第2号被保険者 | 40歳から64歳 | 特定疾病に該当 | 1割から3割(所得区分に準ずる) |
訪問看護を利用しても通院の医療保険と併用でき、負担が増えることはありません。また高額療養費制度の対象にもなるため、一定額を超えた分は自己負担が軽減されます。
医療保険に基づく仕組みのため、必要な医療的フォローを受けながら在宅生活を続けやすい点が特徴です。
自立支援医療での1割負担
精神科訪問看護は、自立支援医療(精神通院医療)を利用すると自己負担が一律1割になります。統合失調症、うつ病、双極性障害など多くの精神疾患が対象で、訪問看護もこの制度の枠内で利用できます。
また所得に応じた月額上限額が設定されているため、医療費が一定額を超えることがなく、家計の負担を大きく抑えられる点が特徴です。
条件や負担上限額は自治体によって異なりますが、東京都の場合は以下の通りです。
| 世帯所得状況 | 自己負担割合 | |
| 割合 | 上限月額 | |
| 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 1割 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 1割 | 5,000円 |
| 次の世帯が「重度かつ継続」に該当する場合、以下のように自己負担が軽減されます。 | ||
| 市町村民税課税世帯で、33,000円未満 | 1割 | 5,000円 |
| 市町村民税33,000以上235,000円未満 | 1割 | 10,000円 |
出典:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
対象となる医療は「通院における精神医療(外来、投薬、デイケア、訪問看護等)」であり、入院医療や精神障害と関係のない治療費用は対象外となります。
実際に自立支援医療を利用できるかどうかは、住んでいる自治体・保険加入状況・病状・診断書の有無などによって異なるため、あらかじめ確認すると良いでしょう。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
介護保険が適用されるケース
精神科訪問看護は、65歳以上で要介護認定を受けている場合、原則として介護保険が優先されます。
ただし、次のような医療的支援が特に必要と判断されるケースでは、例外的に医療保険での訪問看護が認められます。
- 幻覚・妄想の急激な悪化や強い興奮状態
- 自力での服薬管理が困難で治療の継続が危うい状況
- 副作用の疑いがあり、医師の観察が必要
- 自傷リスクや希死念慮の増大による安全確保の必要性があるなど
自費(全額自己負担)になるパターン
精神科訪問看護は医師が発行する指示書が必須のため、指示書がない場合は訪問看護自体を利用できません。
一方で、生活相談や家事支援など、医療としての必要性がなく保険対象外の内容が中心となる場合は、訪問看護ではない別のサービスとして提供されることがあります。もちろん医療行為には該当しないため、料金は全額自己負担となります。
精神科訪問看護を利用するまでの5つの流れ
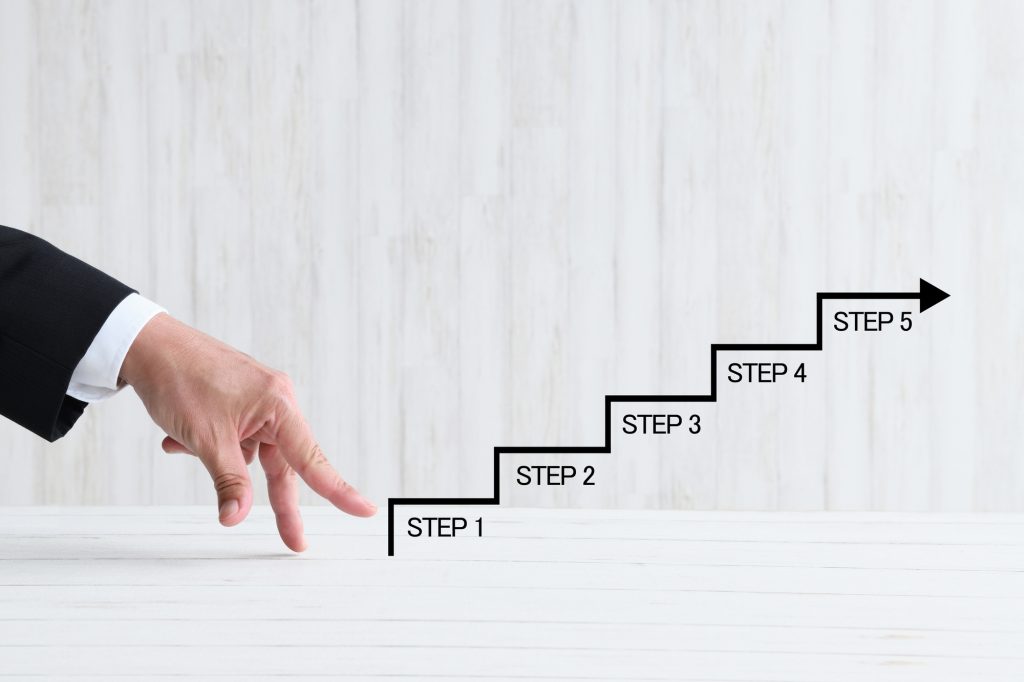
ここでは精神科訪問看護を利用するまでの主な流れを紹介していきます。
①主治医または相談支援へ相談
精神科訪問看護を利用する際は、まず主治医または相談支援専門員に相談することから始まります。
症状の安定、服薬管理、生活リズムの調整など、どのような支援を希望するのかを整理して伝えると、手続きがスムーズに進みます。
本人が相談しづらい場合は、家族や支援者からの相談も可能です。状態や生活状況を確認したうえで、訪問看護の必要性を医師が判断します。
②精神科訪問看護指示書の発行
精神科訪問看護を利用するには主治医が発行する「精神科訪問看護指示書」が必須です。これは保険適用の前提となる書類で、指示書がなければ訪問看護を利用できません。
指示書には、診断名または症状名、訪問の目的、必要な医療的支援の内容、訪問頻度や期間などが記載されます。
これらは看護師が支援計画を立てる際の基礎となり、治療方針に沿った適切な在宅ケアを提供するために欠かせません。
③訪問看護ステーションを選ぶ
精神科訪問看護を利用する際は、指示書をもとに訪問看護ステーションを選びます。選ぶ際のポイントは次のとおりです。
【精神科対応の経験】
精神症状への理解、観察力、家族支援の実績があるかなどを確認します。
【支援体制】
緊急時の連絡体制、多職種との連携が取れているかなどを確認します。
【相性の良さ】
看護師に相談しやすいか、安心して話せる雰囲気かなどを確認します。
これらを確認し、自分に合ったステーションを選ぶことで、より安心した在宅ケアにつながります。
④初回訪問・アセスメント
精神科訪問看護では、利用開始後に初回訪問とアセスメントをおこないます。アセスメントは、生活状況や症状、困りごとの背景を看護師が丁寧に把握するためのプロセスです。
睡眠・食事・活動量など日常のリズムを確認しながら、必要な支援を整理します。そのうえで無理のない目標を設定し、今後の訪問内容や支援方針を決めていきます。
⑤利用開始
精神科訪問看護は、初回アセスメント後に計画書が作成され、その内容に沿って本格的な利用が始まります。
訪問スケジュールは、たとえば週2回・30分といった形で、利用者の状態に合わせて調整されます。
開始後は、計画書に基づいて症状の変化や生活状況をモニタリングし、必要に応じて支援内容や訪問頻度を見直します。
精神科訪問看護を受けるメリット

ここでは精神科訪問看護を利用することで期待できる主なメリットを紹介していきます。
病状が安定しやすくなる
精神科訪問看護を利用する最大のメリットは、病状が安定しやすくなる点です。看護師が定期的に自宅で様子を確認するため、強い不安や落ち込み、睡眠の乱れなどの変化にいち早く気づくことができます。
こうした早期発見は、主治医への適切な報告や必要な対応につながり、症状の悪化防止に役立ちます。
また生活リズムや服薬状況のチェックを継続的におこなうことで、再発リスクを下げ、安定した日常を取り戻しやすくなります。
再発・入院の予防
精神科訪問看護は、再発や入院につながりやすい生活の乱れやストレスに早めに気づき、対処できる点が大きなメリットです。
家庭や職場でのプレッシャー、人間関係の悩みなどは、症状が落ち着いている時期でも再発のきっかけになることがあります。
訪問看護では、こうしたストレスを軽減する方法を検討し、生活が大きく崩れる前に立て直せるよう支援することで、症状の再発や入院を防ぎます。
家族の負担を軽減できる
精神科訪問看護には、家族の負担を軽減できるという大きなメリットがあります。症状の変化の把握や対応を家族だけで担うには限界があり、心身の負担が蓄積しやすくなります。
訪問看護では、看護師が定期的に状態を確認し、必要な支援を専門的な視点でおこなうため、家族が抱え込みがちな不安やプレッシャーが和らぎます。
さらに困ったときに相談できる支援者がいることで「ひとりで対応しなくていい」という安心感が生まれ、家庭全体の負担も軽減されます。
孤立防止と社会復帰の後押し
精神科訪問看護は、人との関わりが少なくなり、孤立しやすい状況にある利用者への支えにもなります。
看護師が定期的に訪問することで、気軽に話せる相手ができ、孤独感が和らぎます。また、生活リズムを整えながら外部とのつながりを少しずつ増やすことで、無理のない形で社会復帰を後押しできます。
自分のペースで社会との距離を縮められる点は、大きなメリットです。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
A型・B型事業所と精神科訪問看護の相性が良い3つの理由

精神科訪問看護はA型・B型事業所と組み合わせることでより充実した支援を提供できるようになります。
ここではA型・B型事業所と精神科訪問看護の相性が良い主な理由を解説していきます。
競合がまだ少ない
A型・B型事業所と精神科訪問看護が相性の良い理由の一つが競合の少なさです。
厚生労働省の「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、日本の人口の約1,164万人が何らかの障がいを持つと推計されています。そのうち精神障がい者が約半数を占めており、年々増加傾向にあります。
しかし、その一方で精神科に対応できる訪問看護ステーションはまだ多くありません。需要に対して供給が追いついておらず、地域によってはほとんど選択肢がないケースもあります。
そのため、早い段階で参入すれば利用者から選ばれやすく、医療連携の基盤も築きやすい分野といえます。
訪問看護によって経営が安定する
A型・B型事業所は、精神科訪問看護と組み合わせることで経営が安定しやすくなります。
訪問看護によってA型・B型事業所の利用者の体調が改善すると、通所が安定し、サービス費の変動が少なくなるためです。
また利用者の健康面をフォローし続けることで、利用者本人の生活の質や働く意欲にも良い影響が与えられます。精神科訪問看護は、事業所と利用者の双方にとってメリットの大きい組み合わせだといえます。
手厚い支援により信頼度が上がる
A型・B型事業所に精神科訪問看護が入ることで支援体制が強化され、医療機関や相談支援員からの信頼度が高まります。
また精神疾患のある利用者にとっては、健康面のフォローが整うことで通所の不安が軽減され、働く一歩を踏み出しやすくなります。
就労面と健康面の両方を支えられる環境が地域での信頼獲得につながります。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
精神科訪問看護は、症状の安定化や再発予防、家族の負担軽減、社会復帰の後押しなど、多岐にわたるメリットを持つサービスです。A型・B型事業所との相性も良く、支援の質向上や経営の安定化にもつながります。
GLUGでは、これまで1,000社以上のA型事業所を支援してきた実績をもとに、訪問看護事業の立ち上げから運営まで手厚くサポートしています。
訪問看護事業の導入をご検討中の方は、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。









