2025年問題は前例のない超高齢化社会に突入することによって発生が危惧されている悪影響であり、多くの企業が対策を講じています。
2025年問題はあくまでも過渡期であり、ピークは2040年となりますが、今の時点で十分に備えることができなければ競合に優位に立てなくなるおそれがあります。
今回は2025年問題の概要や引き起こされる国内や企業への影響、2030年問題・2040年問題との違い、国・企業の対策などを網羅的に解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
2025年問題とは?

2025年問題とは、団塊世代(1947年から1949年生まれ)が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護・社会保障制度や労働力、地域社会に大きな影響を及ぼすとされる日本の社会問題です。
ここでは2025年問題の概要を説明していきます。
超高齢化社会の問題
総務省の「統計からみた我が国の高齢者」によれば、2024年9月時点の推計で75歳以上の後期高齢者が2,076万人に達しており、65歳以上人口は3,625万人と過去最多を記録しています。
出典:総務省「統計からみた我が国の高齢者」
また同発表によればアメリカやイギリス、ドイツなど世界各国でも高齢化が進んでいますが、65歳以上人口の割合は日本が世界で最も高くなっています。
出典:総務省「統計からみた我が国の高齢者」
厚生労働省の「今後の高齢化の進展 ~2025年の超高齢社会像~」は、「これまでは高齢化の進展の速さが問題であったが2015年以降は高齢化率の高さが問題となる。」と説明しています。
詳しくは後述しますが、高齢化が進んだ場合、以下の問題が発生するため、世界各国が対策を進めています。
- 労働力人口の低下
- 社会保険費の負担増大
- 経済の縮小
- 需要過多による医療・介護の破綻など

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
2025年の崖とは
2025年の崖とは、日本がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できないことが原因で2025年以降に生じる可能性がある経済的な損失のことです。
経済産業省が2018年に発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』によって提唱されました。
2025年の崖では、主に以下の3点が問題として挙げられています。
- 現役で使っているレガシーシステム(老朽化したシステム)が複雑化・属人化しており、維持費が高いうえにDX化の妨げになっている
- レガシーシステム担当者の高齢化による退職で突発的なトラブルに対応できなかったり、原因究明ができなかったりする場合がある
- 業務や既存システムの見直しをおこなおうとしても、現場の強い反発でDX化を進められない
上記のような問題を解消できなければ、2025年の崖によって最大で年間約12兆円の経済的な損失が発生すると推定されています。
2030年問題・2040年問題とは
2030年問題は少子高齢化などによって2030年に発生する可能性がある社会問題のことです。
2025年問題は団塊世代が後期高齢者になることで医療・介護の需要が急増し、制度の破綻が危惧されています。
一方で2030年問題は少子高齢化に伴う人口減少や人材不足、人件費高騰、地方消滅の危機などのリスクが課題として挙げられます。
2040年問題は団塊ジュニア世代の全員が65歳以上になることが原因で生じるとされる問題のことで、日本の高齢者人口は約3,900万人、全体の35%に及ぶと推定されています。
2025年問題が少子高齢化の過渡期であるなら2040年問題はそのピークとなります。
2040年問題では以下のリスクが危惧されており、2025年問題・2030年問題も含めて早急に対策しなければなりません。
- 担い手不足により、消防・上下水道・ごみ収集などのインフラが脆弱化する
- 働き手の減少と高齢者の増加により、税収減と支出増が発生し、地方自治体が財政破綻に陥る可能性がある
- 需要過多による慢性的な医療・介護スタッフの不足
- 社会保険料の負担が増加など
2025年問題が日本にもたらす影響

2025年問題によって、以下の影響が発生することが危惧されています。
- 社会保障費の負担増大
- 医療・介護の破綻
- 経済の縮小
- ビジネスケアラーの増加
それぞれ詳しく解説していきます。
社会保障費の負担増大
社会保険費とは、国民の生活を支えるために支払う費用のことで、健康保険・介護保険・年金・雇用保険・労災保険などの種類があります。会社員の場合、社会保険費が毎月の給与から自動的に天引きされ、会社と折半します。
現役世代が社会保険費を負担することで高齢者を支える仕組みですが、2025年問題によって後期高齢者が増加・現役世代が減少し、社会保険費の負担がさらに大きくなると予測されています。
社会保険費の増加も少子高齢化を加速させる一因ともなっており、現役世代の負担をいかに軽減できるかが大きな課題となっています。
医療・介護の破綻
2025年に団塊世代の全員が75歳以上の後期高齢者になることで高齢者人口は過去最多に達します。これに伴い、慢性疾患や認知症を抱える高齢者も増加し、病床や介護施設の不足が懸念されています。
また急増する高齢者数に対し、医療・介護スタッフの確保が追いつかないとされており、厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の将来推計について」によれば、2025年には約32万人の医療・介護スタッフが不足すると考えられています。
このように需要に供給が追いつかない状態が続けば、高齢者の健康維持が難しくなるだけでなく、現場で働くスタッフの負担増によりサービスの質の低下も懸念され、早急な対策が求められています。
経済の縮小
中小企業庁の「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」によれば、2025年までに平均引退年齢(70歳)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人に達し、そのうちの約半数の127万人が後継者未定となる見込みです。
一般的に国内の中小企業・小規模事業者は経営者に依存している傾向にありますが、2025年問題により高齢の経営者が引退期を迎えることで、後継者不在による廃業が増加すると懸念されています。
この課題を解決できなければ、最終的に累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われると推測されており、第三者による事業承継(M&Aなど)へのニーズが一層高まると見込まれます。
ビジネスケアラーの増加
ビジネスケアラー(ワーキングケアラー)は仕事と介護を両立させている現役世代のことです。2025年問題による高齢者人口の増加に伴ってビジネスケアラーの数も急増すると見込まれています。
経済産業省の「経済産業省における介護分野の取組について」によれば、2025年にはビジネスケアラーが約307万人に達し、両立の困難さから仕事の生産性が低下し、2030年には約9.1兆円の経済損失が発生すると推計されています。
また経済産業省の「新しい健康社会の実現」によれば、仕事と介護の両立ができず、介護を理由に毎年約10万人が離職しており、人材不足に拍車をかける要因となっています。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
2025年問題に向けて国が打ち出した対策

2025年問題による悪影響を国も深刻に捉えており、以前からさまざまな対策が講じられています。
ここでは国がおこなっている2025年問題対策の一例を紹介していきます。
公費負担の見直し
2025年問題によって後期高齢者が増加し、現役世代が減少する中で、医療・介護費は急増しています。その結果、国や自治体の財政負担は限界に近づき、公費負担の見直しが進められています。
例えば2022年10月からは、一定以上の収入がある75歳以上の高齢者の医療費自己負担が、従来の1割から2割へと引き上げられました。
さらに2024年10月からは、従業員51人以上の企業に勤務するパート・アルバイトも社会保険の加入対象となりました。
また厚生労働省の「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」にもあるとおり、2021年4月に改正された同法では、定年の延長など70歳までの就業機会を確保する努力義務が導入され、世代間の負担の均等化を図る取り組みも進められています。
医療・介護領域の人材確保
厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の将来推計について」によれば、2025年には約32万人の医療・介護スタッフが不足すると考えられています。
厚生労働省の「介護人材確保に向けた取組」によれば、国は人材確保に向けて以下のようにさまざまな取り組みをおこなっています。
- 未経験者の参入ハードルを下げるための入門研修の実施
- 人材育成や就労環境等の改善をおこなう事業者の認証評価制度の設立
- 休暇取得や育児介護との両立支援
- 週休3日や副業など多様な働き方のモデルケースの試験的な導入
- パンフレットやSNS、イベントなどを活用した医療・福祉の普及啓発など
また厚生労働省の「ロボット技術の介護利用における重点分野の改訂について」によれば、医療・介護スタッフの負担軽減や高齢者の自立支援を推進することを目的として、介護ロボットやICT、IoT技術などを段階的に導入していくとしています。
地域包括ケアシステム
ビジネスケアラーの負担を軽減し、仕事の生産性低下や離職を防ぐためには、高齢者の自立支援、地域での助け合い、企業における多様な働き方の推進が不可欠です。
厚生労働省の「地域包括ケアシステム」によれば、国は住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を目指しています。
この地域包括ケアシステムは、ビジネスケアラーの負担を和らげるとともに、要介護者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよう、地域全体で包括的な支援を行う仕組みです。
また、その中核的な役割を担う地域包括支援センターの設置も推進されており、現在は全国で5,451カ所に展開されています。
2025年問題と日本企業の関係
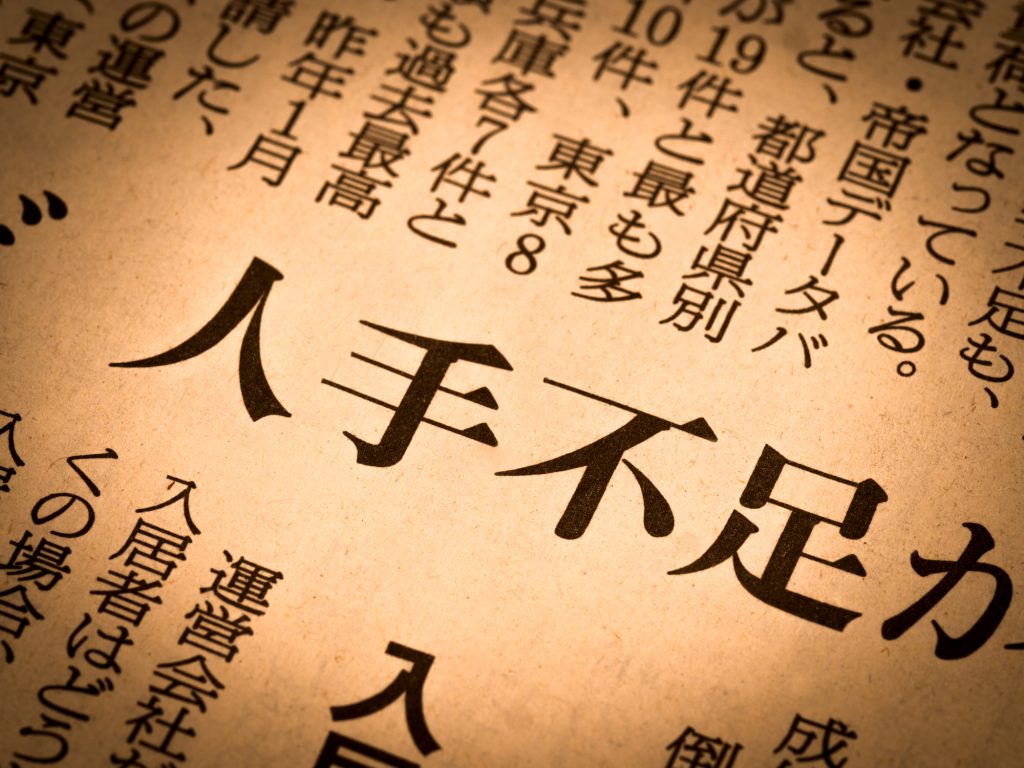
ここでは2025年問題が日本企業に及ぼす主な影響を解説していきます。
人材不足の深刻化
パーソル総合研究所の調査である「労働市場の未来推計2030」によれば、2025年時点で505万人、2030年に644万人の人材不足が発生すると推測されています。
特に深刻な人手不足が見込まれているのは、サービス業界と医療・福祉業界、運送業界、建設業界です。
人材不足による倒産も現在進行形で発生しており、帝国データバンクの「人手不足倒産の動向調査(2024年)」によれば、2024年には人手不足を原因とする倒産が324件にのぼりました。今後も少子高齢化の進行により、高水準で推移することが懸念されています。
旧来のシステムによる弊害
経済産業省の『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』で説明されている通り、多くの企業が導入から20年以上経過したレガシーシステムを使用し続けています。
しかし、レガシーシステムがDX推進の妨げとなっており、以下のようなリスクが生じることで、最大年間約12兆円の経済損失が発生すると推定されています。
- 古い言語や設計に対応できるエンジニアの減少により、保守やトラブル対応が困難になる
- 新技術との互換性が低く、競合他社に対して優位性を失う
- 最新のセキュリティ対策を導入できず、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まる
- 保守・運用コストが年々増大する
実際、こうしたレガシーシステムの弊害はすでに表面化しています。某金融機関では、古いプログラミング言語のCOBOLで構築されたシステムの保守が難航するようになり、システム障害が多発する事態に。
COBOL技術者の不足や度重なる改修によるシステムの複雑化が原因で迅速な復旧ができない状態となっており、一時的なATMの取引停止を免れることができず、顧客に大きな影響を及ぼしました。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
2025年問題と各業界の関係

2025年問題の日本企業への影響を解説しましたが、各業界が受ける具体的な問題を把握することで多角的な視点で対処を考えることができます。
ここでは各業界が受ける2025年問題の影響を紹介していきます。
IT
テクノロジーの進化によってIT業界の需要が拡大し続けていますが、経済産業省の『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』で説明されている通り、供給が追いつかないことで2025年までに約43万人の人材が不足すると推測されています。
また前述したようにレガシーシステムがDX推進の障害となっており、このままでは年間最大約12兆円の経済損失が発生する恐れがあります。
一方で、2025年までにDXを実現できれば、2030年には実質GDPを130兆円以上に押し上げられると予測されています。
保険
少子高齢化により、保険業界にも深刻な影響が及ぶと予想されています。高齢化によって保険金の支払いが増える一方で、少子化により新規契約者が減少し、収益の低下が懸念されています。
このような状況に対応するため、保険業界はDXを推進し、業務の効率化や新たな保険商品の開発に取り組む必要があります。
飲食
飲食業界は少子高齢化による市場縮小と人手不足が進行し、原材料費や物流コストの高騰も経営を圧迫しています。また人手不足が原因で従業員への負担も増加しており、離職率の上昇も課題となっています。
また円安による輸入原材料の価格上昇も価格転嫁が難しく、収益悪化の要因となっています。
飲食業界が2025年問題を乗り切るためにはコストカットや業務効率化が必須です。調理済み冷凍食品の活用や調理工程の簡素化、食品ロスの削減などさまざまな取り組みがおこなわれています。
医療・介護
医療・介護業界は少子高齢化によって急激に需要が高まる一方で、供給が追いついていません。厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の将来推計について」によれば、2025年には約32万人の医療・介護スタッフが不足すると考えられています。
そうした供給不足の中で現場への負担もさらに大きくなると予想されており、前述した地域包括ケアシステムの構築や医療・介護人材の確保が急務となります。
建設
国土交通省の「建設業における人材確保に向けた取り組みについて」によれば、建設業界では55歳以上の労働者が35.9%を占める一方で、29歳以下の若年層はわずか11.7%にとどまり、他業種と比べても少子高齢化が特に深刻です。
また国土交通省の「建設産業の現状と課題」でも説明されているように、2025年には90万人の労働者が不足すると考えられています。
しかし、そうした状況の中で長時間労働や出勤日数が多いというイメージから若年層に敬遠される傾向があり、2022年と比較して建設業界に就く若年層は約2万人減少しています。
さらに2025年問題によりベテラン従業員の大量引退が進む中、技術の継承や業務の質の低下も懸念されています。状況を改善するためには、労働環境やイメージの改善、若年層の確保、ICT技術の導入などが急務となります。
運送
運送業界は通販サイトやフリマアプリなどの普及に伴って需要が拡大し続けている一方で、高齢ドライバーの大量退職や若年層の就業離れにより深刻な人手不足に直面しています。
国土交通省の「トラック運送業の現状等について」によれば、40歳から54歳のドライバーが全体の45.2%を占めるのに対し、29歳以下の若年層はわずか9.1%にとどまっています。
また2024年の働き方改革の一環で年間時間外労働の上限が960時間に制限されました。しかし労働環境改善に向けた施策であったものの、これが原因でトラックドライバーの稼働時間と残業による手取り収入が大きく減少し、離職者が増える結果となりました。
こうした状況を改善するためにAIを活用した配車システムや自動運転技術の導入が進められていますが、中小企業では導入コストや人材不足が障壁となっています。
2025年問題に対して日本企業が今できること
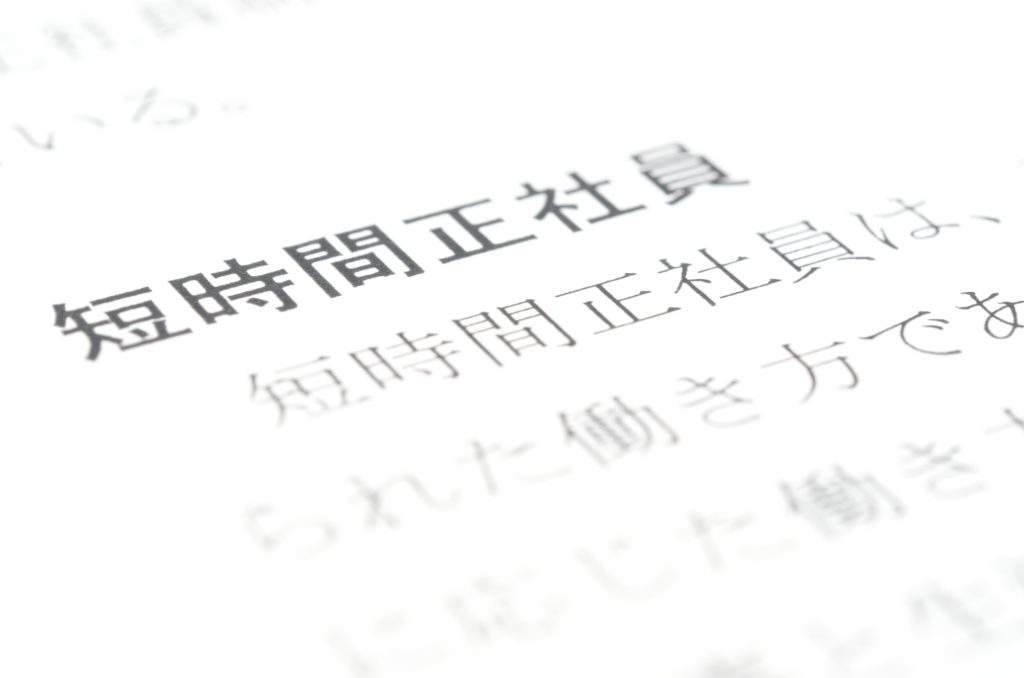
2025年問題の影響を最小限に抑えるために企業はどのような対策をおこなえば良いのでしょうか。
ここでは日本企業でおこなっている主な2025年問題対策を紹介していきます。
制度の整備
従業員が働きやすい環境を整えることは、現場の負担軽減につながり、定着率やパフォーマンスの向上、採用コストの削減、さらには優秀な人材の確保にも寄与します。
例えばテレワークやフレックスタイムの導入により、従業員のワークライフバランスが整い、育児や介護と仕事の両立がしやすくなります。
また2025年問題により後期高齢者となる団塊世代の介護を担う団塊ジュニア世代が増加すると見込まれることから、社内の介護支援制度の充実も重要です。
雇用形態の多様化
少子高齢化の進行により、今後も若年層の確保は困難が続くと予想されます。そのため、多様な雇用形態を導入し、就労意欲のあるシニア層にも積極的にアプローチすることが人材不足の解消につながります。
内閣府の「第1章 高齢化の状況」によれば、男性の60歳から69歳と女性の60歳から64歳は6割以上が現役で仕事をしており、その9割近くが70歳以上まで働きたいと考えています。
さら厚生労働省の「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」で説明されているように2021年4月に改正・施行された高年齢者雇用安定法によって、企業には定年を70歳までとする努力義務が課され、高齢者の就労促進が進められています。
契約社員・パート・アルバイト・業務委託に加え、近年では所定労働時間を短縮した「短時間正社員」への関心も高まっており、こうした多様な働き方の導入により、シニア人材の確保がしやすくなるでしょう。
外部リソースの活用
多様な雇用形態の導入に加え、外部リソースの活用によって人材不足による負担の軽減を図ることが効果的です。
例えば、専門知識やスキルを持つフリーランスやコンサルタントの活用、業務の一部を外部に委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)などが挙げられます。
実際にIT分野などの専門家を外部から招き、短期間でプロジェクトを遂行したり、専門的な課題を解決したりする中小企業も増えています。
また経理や人事業務を外部に委託することで、社内の人材をより重要な業務に集中させ、生産性の向上を実現することも可能です。
DXの進行
2025年問題への対応として、DXを推進し、生産性の向上や競争力の維持、経済的損失の回避を図る企業が増えています。
例えば人手不足と少子高齢化の影響が特に深刻な建設業界では、生産性の向上と労働環境の改善を目的に、国土交通省が提唱する「i-Construction」に基づき、ICT技術の導入が進められています。
ただし、単にDXを導入するだけでは、既存システムに慣れた現場に過度な負担をかける可能性があるため、DXの推進とあわせて、組織全体での意識改革や業務プロセスの見直しもあわせて行うことが重要です。
事業承継
中小企業庁の「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」によれば、後継者問題を解決できなければ、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われると推測されており、計画的な事業承継が不可欠です。
同発表では、中小企業・小規模事業者の経営者の平均引退年齢は70歳とされていますが、事業承継には後継者の育成も含めて一般的に5年から10年を要するため、60歳を迎える時点で準備を始めることが望ましいとされています。
事業承継を支援する制度も整備されており、日本政策金融公庫による事業承継マッチング支援や、中小企業庁および中小企業基盤整備機構が設置する「事業承継・引継ぎ支援センター」などを活用すると良いでしょう。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
2025年問題は過去前例のない超高齢化社会に突入することによって発生する問題の総称です。
あくまでも2025年問題は過渡期に過ぎず、今のうちに十分な対策を講じなければ、将来的に深刻な影響を受ける可能性があります。
企業としては、DXの推進、働きやすい環境の整備、多様な雇用形態の導入、外部リソースの活用など、計画的な対応が求められます。
「何から始めれば良いのか分からない」という方は、フランチャイズへの加盟やコンサルタントの活用を検討するのも1つの手です。
フランチャイズに加盟すれば、業界の知見を持つ本部から経営ノウハウや市場動向、集客・営業などの支援を受けられるため、安定した経営がしやすくなります。
またコンサルタントを活用すれば、2025年問題を踏まえた戦略的なアドバイスを受けられるため、より実践的に課題へ対処できます。









