合同会社は国内において株式会社の次に多い法人形態です。
得られるメリットを期待して合同会社でビジネスを始める方も多く存在しますが、合同会社と株式会社のどちらが良いのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は合同会社の基礎知識やメリット・デメリット、株式会社との比較、設立手続きの流れなどを解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
合同会社とは?基本的な特徴と仕組み

合同会社は、2006年の会社法施行により導入された法人形態で、出資者(社員)が直接経営に関与できる点が大きな特徴です。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしており、株式会社と異なり、所有と経営が一致します。
詳しくは後述しますが、合同会社は株式会社よりも設立費用が安いため、スモールビジネスを展開したい方に向いています。
ここでは合同会社の概要を説明していきます。
合同会社の特徴は?
合同会社の大きな特徴は、出資者(社員)が有限責任を負うことです。有限責任とは、会社の債務に対し、出資者は出資額を上限として責任を負う仕組みを指します。
合同会社の社員は会社の所有者でありながら、会社の債務や負債について個人的に責任を負う必要はありません。
その一方で個人事業主や合名会社などは無限責任を負うため、事業の負債が出資額を超えた場合、個人の資産を使ってでも返済する義務があります。
合同会社の法的位置づけ
会社法第576条では、合同会社は「社員全員が有限責任を負い、出資者が業務を執行する会社」と定義されています。
株主など外部の所有者が存在しないため、経営の自由度が高く、迅速な意思決定が可能です。
会社法改正によって法人の最低資本金制度が撤廃・1円から設立が可能になりましたが、合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税6万円で設立できるため、株式会社と比べ大幅に費用を抑えられます。
株式会社よりも設立コストが低く、機動的な経営ができるため、小規模事業やスタートアップに適した法人形態といえます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
合同会社の役職と組織体制について

合同会社には、株式会社のような取締役や監査役の設置義務はなく、出資者(社員)が経営を直接担うシンプルな組織体制が特徴です。社員の中から業務執行社員を選任し、会社の運営をおこないます。
| 役職 | 役割 | 権限・責任 |
| 社員(出資者) | 会社の所有者 | 出資額を上限とした有限責任を負う |
| 業務執行社員 | 会社の経営を担当 | 会社の意思決定と日常業務を執行 |
| 代表社員 | 会社を代表し対外的な業務をおこなう | 契約締結などの対応をおこなう |
合同会社では、社員全員が経営権を持つため、迅速な意思決定が下せます。また、出資比率に関わらず、定款で役割や利益配分を自由に決められる点も大きな特徴です。
代表社員の権限と責任
合同会社の代表社員は、会社を代表して契約の締結や法的手続きをおこなう権限を持ちます。また会社の経営方針の決定や業務執行社員を統括する役割も担います。
責任として、健全な業務運営が求められ、法令違反や不正行為があった場合は損害賠償責任を負う場合があります。また、契約に関する意思決定の適正性も求められています。
合同会社のメリット5つとは?
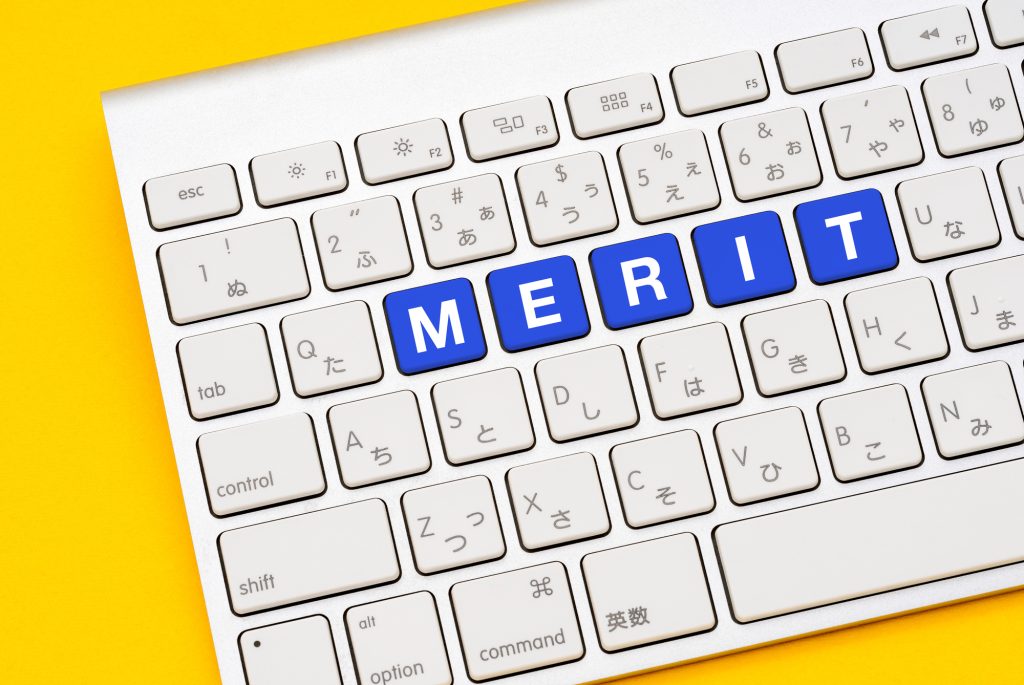
以下のメリットを期待して合同会社を選ぶ方も珍しくありません。
- 最小限の費用で法人設立が可能
- 経営判断のスピードが速い
- 法人税の節税効果が高い
- 出資者の責任が限定される
- 事業拡大に合わせた組織調整が容易
それぞれ詳しく解説していきます。
最小限の費用で法人設立が可能
合同会社は、株式会社に比べて低コストで設立できる法人形態です。
設立費用は登録免許税6万円のみで、定款の認証(約4万円)が不要となり、株式会社の設立費用(22万から25万円)よりも負担が少なく済みます。
個人事業主、スタートアップ、スモールビジネスなど、最小限のコストで法人化したい場合に適した選択肢といえます。
経営判断のスピードが速い
合同会社は、出資者(社員)が直接経営に関与するため、意思決定が速いのが特徴です。
株式会社のように取締役会や株主総会の承認を経る必要がなく、社員同士の合意のみで経営方針を決定できます。そのため、市場の変化に素早く対応し、事業戦略を迅速に実行できます。
特にベンチャー企業やスモールビジネスでは、スピーディーな判断が競争優位につながるため、合同会社の仕組みは大きなメリットとなります。
法人税の節税効果が高い
合同会社は役員報酬を全額経費計上できるため、法人税を軽減できます。株式会社のような役員報酬の事前確定届出義務がないため、柔軟な節税対策が可能です。
また、法人住民税の均等割は発生するものの、配当金の分配が不要なため、利益を内部留保しやすく、長期的な節税効果が期待できます。
特にスモールビジネスや個人事業主からの法人成りを考える場合、合同会社は節税面で有利な選択肢となります。
出資者の責任が限定される
合同会社の出資者(社員)は有限責任であり、会社の負債に対して出資額を超える責任を負いません。つまり、事業が失敗しても個人資産が差し押さえられるリスクがなく、安心して経営に取り組めます。
無限責任の個人事業主や合名会社とは異なり、合同会社は会社の債務と個人の財産が明確に分離されるため、資金調達の面でも有利だといえます。この仕組みは、起業時のリスクを抑えたい経営者にとって大きなメリットとなります。
事業拡大に合わせた組織調整が容易
合同会社は、経営権や利益配分を定款で自由に決定できるため、事業拡大に応じた組織調整が柔軟に可能です。
例えば、新たな出資者を迎える際も、出資比率に関係なく業務執行権を調整できるため、経営体制をスムーズに変更できます。また、取締役会や株主総会の承認も必要ありません。
成長フェーズに合わせて柔軟に経営体制を最適化したい企業にとって、大きなメリットとなります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
合同会社のデメリット3つとは?

合同会社には多くのメリットがある一方、決して無視することができないデメリットも存在するため、デメリットを許容できるかどうかを十分に考えることが大切です。
ここでは合同会社の主なデメリットを紹介していきます。
株式会社と比べて信用度が低い
合同会社は取締役会や株主総会の設置義務がなく、設立手続きが簡易で低コストな反面、経営の安定性や資金力に対する信用度が低いと見られることがあります。
また、株式会社は決算公告の義務がある一方で、合同会社には義務がないため、財務状況の透明性が低く、金融機関や取引先からの信頼を得にくいケースもあります。
そうした経緯から大口取引や融資を受ける際に不利になる可能性があり、事業規模の拡大を目指している場合は、株式会社が適しているといえるでしょう。
銀行融資が受けにくい
合同会社は決算公告の義務がなく、財務の透明性が低いため、信用力が不足しがちであり、銀行の融資審査が厳しくなる傾向があります。
また合同会社は仕組み上、経営者が出資者と一致していますが、組織の継続性が不透明と判断されることもあります。
融資を受ける際は事業計画書や財務諸表を詳細に準備し、財務の健全性を示すことが重要です。
事業承継時の課題と対策方法
合同会社の事業承継では、出資者(社員)の交代、持分の承継、経営権の引継ぎが大きな課題となります。特に出資者が死亡した場合、持分の相続や他の社員との合意形成が必要です。
対策として定款で事業承継のルールを明文化し、早期に後継者を決定するようにしておきましょう。
合同会社における事業継承の主な流れは、以下の通りです。
- 後継者の選定と育成
- 定款の確認・必要な変更の検討
- 持分の譲渡・相続手続き
- 取引先・従業員への引継ぎ
- 事業承継の実施
合同会社と株式会社、どちらを選ぶ?徹底比較

合同会社と株式会社は以下のようにそれぞれにメリット・デメリットがあるため、どちらを選ぶべきか悩んでいる方も多いでしょう。
最適な法人形態を選べるように、ここでは合同会社と株式会社をそれぞれ比較していきます。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
| 設立費用 | 6万円から10万円前後 | 22万円から25万円前後 |
| 所有者 | 社員(出資者) | 株主 |
| 経営権 | 社員が直接経営 | 取締役が経営 |
| 意思決定 | 迅速 | 取締役会・株主総会で承認が必要 |
| 社会的な信頼 | やや低い | 高い |
| 事業承継 | 持分譲渡が必要 | 株式譲渡が容易 |
事業規模で見る最適な選択方法
以下のように事業規模に応じて、合同会社もしくは株式会社を選ぶと良いでしょう。
【小規模の場合 → 合同会社】
低コストで設立可能で意思決定を迅速におこなえます。
【中規模以上・資金調達重視 → 株式会社】
社会的信用が高く、投資家からの資金調達も容易です。
事業の成長段階に応じて、合同会社から株式会社へ移行する選択肢も有効だといえます。
資金調達の可能性を比較
合同会社と株式会社では、以下のように資金調達の手段が異なります。
【合同会社】
銀行融資や補助金・助成金が主な資金調達手段です。株式発行ができないため、投資家からの出資は難しくなります。
【株式会社】
銀行融資、補助金・助成金などに加え、株式発行による資金調達がおこなえます。ベンチャーキャピタルや株式市場からの資金調達がしやすくなります。
合同会社は資金調達の手段が限られるため、大規模な資金調達を検討する場合は、株式会社を選ぶと良いでしょう。
社会的信用度の違いとは
以下のように合同会社は株式会社に比べ、社会的信用度が低い傾向にあります。
【合同会社】
決算公告の義務がなく、財務の透明性が低い傾向にあります。また比較的容易に設立できるため、取引先や金融機関からの信用を得にくくなります。
【株式会社】
決算公告の義務があり、株主が経営を監視する体制が整っているため、社会的信用が高い傾向にあります。
資金調達や取引などを考慮して信用を重視する場合は、株式会社の方が適しているといえます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
合同会社の設立手順と費用を解説

合同会社の設立手順は、主に以下の6ステップです。
- 会社情報の決定
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 登記書類の作成
- 法務局へ登記申請
- 設立完了
それぞれ詳しく解説していきます。
必要書類の準備リスト
合同会社を設立するためには、以下の書類が必要です。
- 定款(会社の基本ルールを定めた書類)
- 設立登記申請書(法務局に提出する申請書)
- 代表社員の印鑑証明書(個人の身元確認のため)
- 出資金の払込証明書(資本金の入金を証明)
- 登記すべき事項の記録(法務局での電子申請用)
- 印鑑届出書(会社実印の登録)
上記を全て法務局に提出・申請することで合同会社の設立がおこなえます。
設立手続きの具体的な流れ
合同会社の設立手続きは、以下の流れで進めます。
- 基本事項の決定(商号、事業内容、本店所在地、出資者・代表社員の決定)
- 定款の作成(収支印紙代4万円)
- 資本金の払込(代表社員の個人口座へ入金)
- 登記書類の準備(設立登記申請書、払込証明書、印鑑証明書など)
- 法務局へ登記申請(必要書類を提出)
- 設立完了(登記完了後、法人銀行口座の開設や税務署への届出)
また手続きの準備は3日前後で、申請してから受理されるまでに2週間前後かかるため、計画的に対応していくと良いでしょう。
設立費用の詳細と相場
合同会社の設立費用は6万円から10万円前後が相場です。以下が主な内訳です。
| 項目 | 費用(目安) |
| 登録免許税 | 6万円 |
| 定款認証 | 4万円(印紙代) |
| その他(印鑑作成、郵送費など) | 数千円 |
電子定款の場合、収支印紙代が発生しないものの、電子定款のための専用機器・専用ツールを用意する必要があります。
状況によっては導入コストの方が上回ってしまうため、あらかじめコストを十分に比較することが大切です。
合同会社の税金・会計の基礎知識
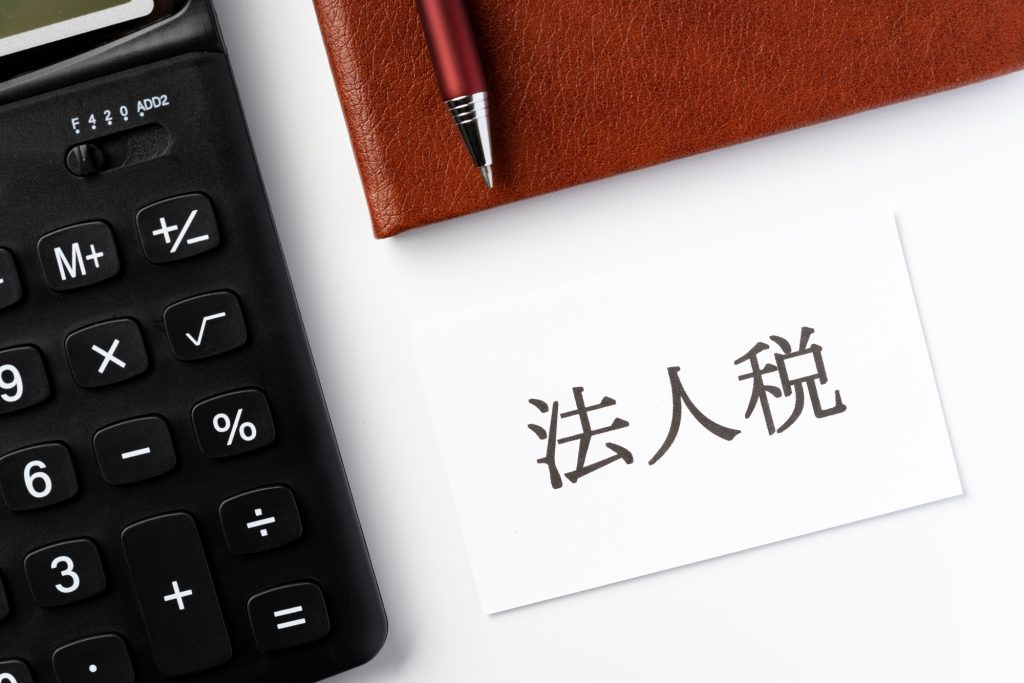
合同会社も株式会社と同様に法人税や消費税などの税金を納める必要があります。以下が主な税金の種類です。
| 分類 | 税金・保険の種類 | 概要 | 納付先 |
| 法人税関連 | 法人税 | 事業利益に応じて課税 | 国税(税務署) |
| 法人住民税 | 法人税額に応じて課税(均等割+法人税割) | 地方自治体 | |
| 法人事業税 | 事業所得に応じて課税 | ||
| 消費税 | 売上が1,000万円超で課税 | 国税(税務署) | |
| 社会保険関連 | 健康保険料 | 従業員と会社で折半 | 日本年金機構 |
| 厚生年金保険料 | 従業員と会社で折半 | ||
| 雇用保険料 | 失業時の給付のために負担 | ハローワーク | |
| 労災保険料 | 会社が全額負担 | 労働基準監督署 | |
| その他 | 固定資産税 | 事業用資産に課税 | 地方自治体 |
| 印紙税 | 契約書などの作成時に課税 | 国税(税務署) |
合同会社も株式会社と同様に各種税金・保険料の負担があるため、計画的な資金管理が重要です。ここでは合同会社における税金・会計の基礎知識を紹介していきます。
法人税の計算方法
合同会社の法人税は、課税所得(利益)に対して税率を適用して計算します。
計算式:法人税 = 課税所得 × 法人税率
例:課税所得500万円の場合
法人税率15%
500万円 × 15% = 75万円(法人税)
課税所得が800万円を超えると、超過分には23.2%の税率が適用されます。合同会社でも税負担を最適化するため、適切な経費計上や節税対策が重要です。
確定申告の具体的な手順
確定申告は、事業年度終了後に法人税を申告・納付する手続きです。合同会社は、以下の手順で進めます。
- 決算書の作成(損益計算書・貸借対照表を作成)
- 法人税申告書の作成(税務署指定の様式に記入)
- 消費税の計算・申告(課税事業者のみ)
- 地方税の申告(法人住民税・事業税を計算)
- 税務署・地方自治体へ申告書を提出(電子申告 e-Tax も可能)
- 税金の納付(法人税・住民税・事業税を期限内に支払う)
役員報酬の設定方法
合同会社の役員報酬は、法人税の経費として計上できるため、適切に設定することが重要です。
合同会社の役員報酬は、以下の流れで事業年度開始後3ヶ月以内に決定し、毎月一定額を支払う必要があります。
- 会社の財務状況を確認し、支払可能な範囲を決定
- 定款や社員総会で報酬額を決議
- 毎月同額を支給(変動報酬は原則認められない)
役員報酬が過度に高額な場合、税務署に経費としての計上を否認されるリスクがあるため、適切な金額を決めることが望ましいです。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
合同会社と株式会社にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、事業規模に応じた最適な法人形態を選ぶことが望ましいです。
スモールビジネスで比較的自由な経営をしたいという方は合同会社の方が得られる恩恵が大きくなるため、迷わずに合同会社を設立しましょう。
将来的な事業拡大を考えていて、資金調達や取引の観点から社会的な信頼を重視したいという方は株式会社が最適な選択となります。
起業しても必ずしも成功できるとは限りませんが、最初から安定した経営をしたいという方はフランチャイズへ加盟することも1つの手です。
フランチャイズは業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、集客や営業、仕入れ、商品開発などを手厚くサポートしているため、未経験からでも成功しやすい傾向にあります。









