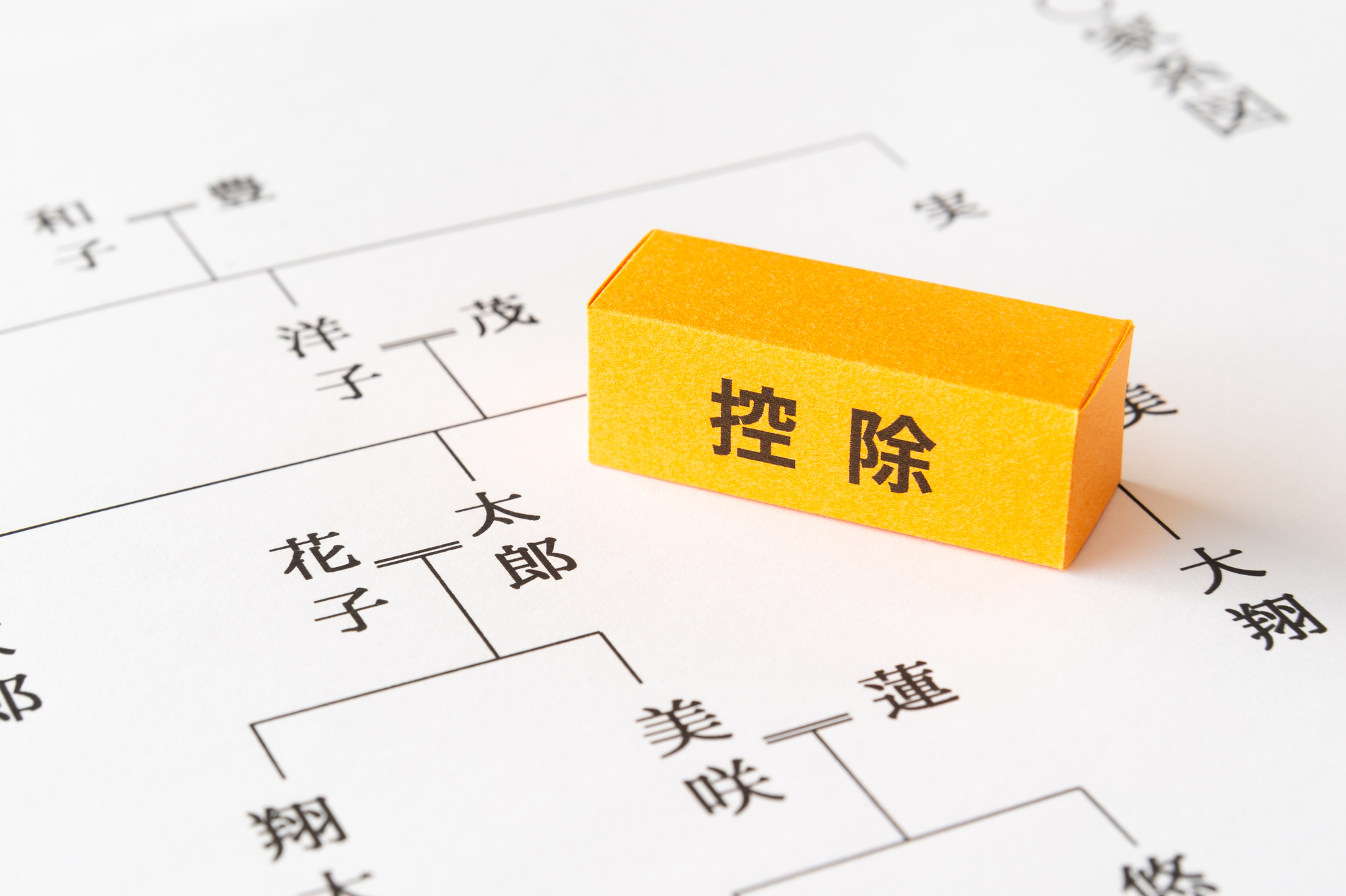家族を扶養家族に入れることで保険料や税金の軽減を図ることができますが、扶養家族にするためには一定の条件を満たす必要があるほか、場合によってはデメリットでかえって負担になる可能性があります。
今回は扶養家族の基礎知識とメリット・デメリット、入れるための条件、手続きなどを解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
扶養家族とは?

扶養家族とは、生計を共にし、経済的に独立していない家族を指します。社会保険と税制では目的が異なり、社会保険では健康保険料の負担軽減、税制では所得税や住民税の控除対象となることが特徴です。
扶養家族の主な目的と意義は、以下の通りです。
- 生活の負担を軽減し、家庭の経済的安定を図る
- 社会保険では被扶養者の医療費負担を抑える
- 税制上の扶養控除により納税者の負担を軽減する
この制度により、家族の生活を支えながら社会全体の安定にも寄与します。
誰が扶養家族になれるのか?
扶養家族として認められるには、条件を満たす必要があります。社会保険と税制の条件はそれぞれ以下の通りです。
【社会保険上の扶養(健康保険)】
- 配偶者(内縁関係含む)
- 直系親族(父母、祖父母など)
- 子・孫・兄弟姉妹
- 同居している三親等以内の親族(義父母、甥・姪など)
- 年間収入130万円未満(60歳以上または障がいを持つ方は180万円未満)
【税制上の扶養(扶養控除)】
- 16歳以上の配偶者・子・親・兄弟姉妹
- 別居の場合、仕送りなど経済的支援が必要
- 合計所得48万円以下(年間収入103万円以下)
扶養家族の条件を満たすかどうかは、収入や日頃の生活によって異なるため、事前に確認することが大切です。
社会保険の扶養条件は?

社会保険の扶養家族とは、健康保険や厚生年金において被保険者が経済的に支えている家族を扶養者として認定する制度です。
扶養に入ることで、被扶養者は保険料の負担なしで社会保険を利用できます。認定されるための条件は、以下の通りです。
【扶養認定の基本条件】
- 年間収入130万円未満(60歳以上・障がいを持つ方は180万円未満)
- 被保険者の年収の1/2未満であること
- パート・アルバイトの場合、月収10万8,333円未満
【同居要件】
- 配偶者・子・孫・兄弟姉妹:同居・別居どちらでも可
- 父母・祖父母:同居・別居どちらでも可
- 三親等以内の親族(義父母・甥姪など):同居が必須
健康保険の扶養認定基準と年収制限
健康保険の扶養に入るためには、以下の収入基準を満たす必要があります。
| 対象者 | 年間収入の上限 | 月収の目安 |
| 59歳以下 | 130万円未満 | 約10万8,333円未満 |
| 60歳以上 / 障がいを持つ方 | 180万円未満 | 約15万円未満 |
また給与所得者は「交通費込みの総支給額」、年金受給者は「年金額」も含めた年収を計算されますが、パート・アルバイトの場合は月収の安定性も考慮されます。
収入基準を超えると扶養から外れ、健康保険料の自己負担が発生するため、注意が必要です。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
税制上の扶養条件は?

税制上の扶養家族とは、納税者と生計を共にし、所得が一定額以下の親族を指します。扶養控除や配偶者控除の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【扶養控除の適用条件】
- 対象者:16歳以上の親族(配偶者は除く)
- 所得条件:年間合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)
- 生計要件:納税者と同居または仕送り等で生活を共にすること
【配偶者控除の適用条件】
- 対象者:納税者の配偶者
- 所得条件:配偶者の年間合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)
- 納税者の所得制限:合計所得1,000万円以下
扶養控除を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できるため、条件を正しく把握することが重要です。
所得税における扶養控除の計算方法
扶養控除とは、納税者が以下の条件を満たす扶養親族を持つ場合に所得から差し引ける控除です。
【扶養控除の適用条件】
- 対象者:16歳以上の親族(配偶者を除く)
- 所得制限:扶養親族の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
- 納税者の所得制限:合計所得2,500万円以下
【扶養控除額】
- 一般の扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19歳~22歳):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居なら58万円)
▼計算例
年間収入600万円の方が、19歳の子供(特定扶養親族)を扶養している場合、扶養控除額63万円が適用されます。
課税所得 = 600万円 - 給与所得控除(134万円) - 基礎控除(48万円) - 扶養控除(63万円)= 355万円
このように、扶養控除を適用すると課税所得が減り、所得税・住民税の負担を軽減できます。
扶養家族のメリット
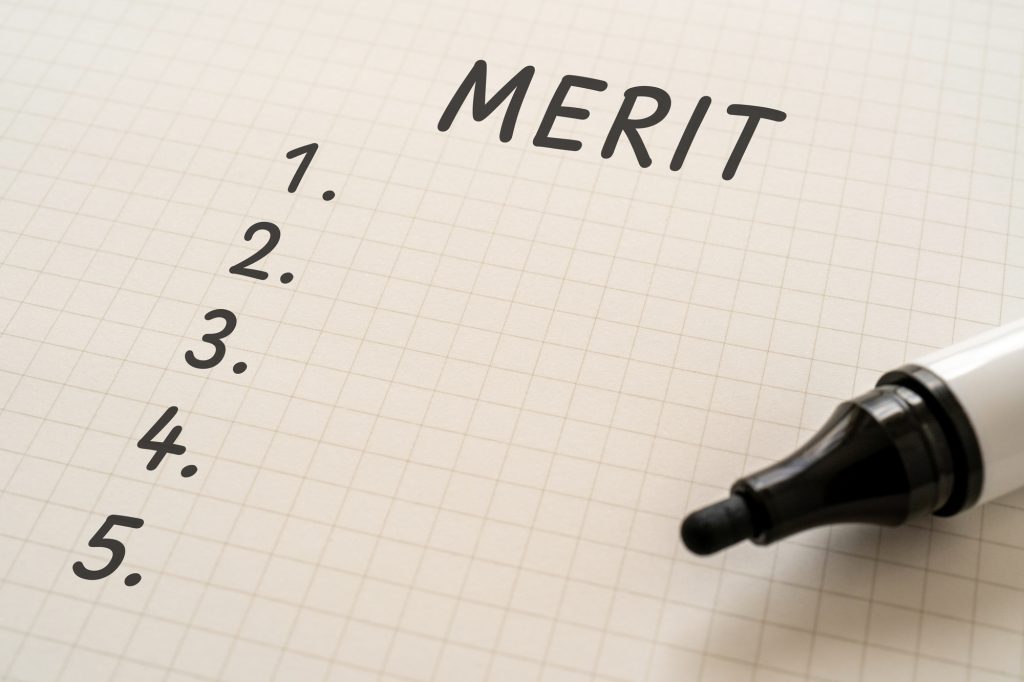
扶養家族を持つと、税金の優遇や社会保険料の負担軽減などのメリットがあります。
【税制上のメリット】
- 扶養控除:16歳以上の扶養親族がいると最大63万円の控除が適用され、所得税・住民税が軽減される。
- 配偶者控除:配偶者の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合、最大38万円の控除が受けられる。
【社会保険上のメリット】
- 健康保険の扶養:扶養家族の年収130万円未満(被保険者の収入の1/2以下)であれば、健康保険料がかからない。
- 年金負担の軽減:配偶者が第3号被保険者(年収130万円未満)になると、国民年金保険料を払う必要がなくなる。
所得税が軽減される仕組み
扶養家族がいると、以下のように扶養控除や配偶者控除によって所得税が軽減されます。
- 一般扶養控除:38万円
- 特定扶養控除(19~22歳):63万円
- 老人扶養控除(70歳以上):48万円(同居なら58万円)
配偶者の年収が103万円以下(所得48万円以下)なら38万円の控除が適用されます。
例えば年収500万円(所得400万円)の場合、一般扶養控除(38万円)と配偶者控除(38万円)を適用することで、課税所得は400万円から324万円に減少します。
所得税率10%の場合、税額は40万円から32.4万円となり、7.6万円の節税をおこなえます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
扶養家族のデメリット

扶養家族を持つことには税制上のメリットがありますが、一方で以下のようないくつかのデメリットも存在します。
【生活費の負担が増加する場合がある】
扶養家族の条件を満たすために新たに同居を始める場合、生活費など家計の負担が増える可能性があります。
【医療費の負担が増加する場合がある】
扶養者が扶養家族の医療費を支払う必要があります。高齢の親を扶養する場合、通院や介護費用がかさむことがあり、結果的に負担が増加する可能性があります。
扶養制度を活用する際は、控除額だけでなく、家計への影響を考慮し、慎重に判断することが大切です。
就労制限による収入の制約
扶養家族には以下の収入制限が設けられていますが、これを超えると扶養から外れ、税負担や社会保険料の支払いが発生することで手取り収入が減少してしまいます。
【税制上の扶養制限】
扶養対象者の 年間合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下) に制限されています。これを超えると、控除が適用されず扶養者の所得税負担が増加します。
【社会保険の扶養制限】
原則として 年収130万円未満(月収108,333円未満) が基準となります。ただし、特定適用事業所(従業員101人以上の企業)では 年収106万円以上 で社会保険への加入が義務付けられています。
扶養を維持するために労働時間を制限している方も多く、収入の伸び悩みにつながることがあります。
扶養制限は年収の壁と呼ばれていますが、国会で議論されており、2025年3月時点では最大160万円が控除される収入別の変動制へ変わることになりました。
扶養家族の手続き方法は?

扶養家族の登録には、社会保険と税制上の手続きの2種類があります。どちらも会社や自治体を通じて申請が必要です。
【社会保険の扶養手続き】
▼手続き先: 勤務先の健康保険組合または協会けんぽ
▼必要書類
- 扶養異動届(被扶養者異動届)
- 扶養対象者の収入証明(給与明細、源泉徴収票、課税証明書など)
- 扶養対象者の続柄を証明する書類(住民票、戸籍謄本など)
- その他、健康保険組合の指定書類
【税制上の扶養手続き】
▼手続き先: 勤務先または税務署
▼必要書類
- 扶養控除等申告書(会社へ提出)
- 配偶者控除や扶養控除を受ける場合、配偶者特別控除申告書(該当者のみ)
会社への申請手順と提出書類
社会保険と税制上の扶養手続きは、それぞれ以下の通りです。
▼社会保険の手続き
- 扶養対象者が条件を満たしているか確認
- 必要書類を準備する
- 会社の人事・総務部門へ必要書類を提出
- 会社が健康保険組合に申請
- 健康保険証が発行される
▼税制上の手続き
- 扶養対象者が条件を満たしているか確認
- 必要書類を準備する
- 会社の人事・総務部門へ必要書類を提出
- 会社が税務署に申請
- 翌年度から住民税・所得税が控除される
必要書類は会社によって異なる場合があるため、事前に確認し、漏れなく準備しておきましょう。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
扶養家族は世帯主が養っている家族のことであり、手続きで扶養家族に入れることで社会保険料や税金の負担を軽減できます。
ただし、扶養家族には収入制限が設けられているほか、場合によっては生活費や医療費が増大してしまうケースもあるため、生活コストを十分に算出した上で扶養家族に入れるかどうか考えると良いでしょう。