サラリーマンは毎月支給される給与から所得税や住民税が差し引かれていますが、節税対策に取り組むことで手取りを増やせる場合があります。
しかしこれから初めて節税対策をおこなおうと思っても、どのような節税対策があるのか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回はサラリーマンにとっての節税の基礎知識や個人でもできる代表的な節税対策を紹介していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
サラリーマンの節税とは?
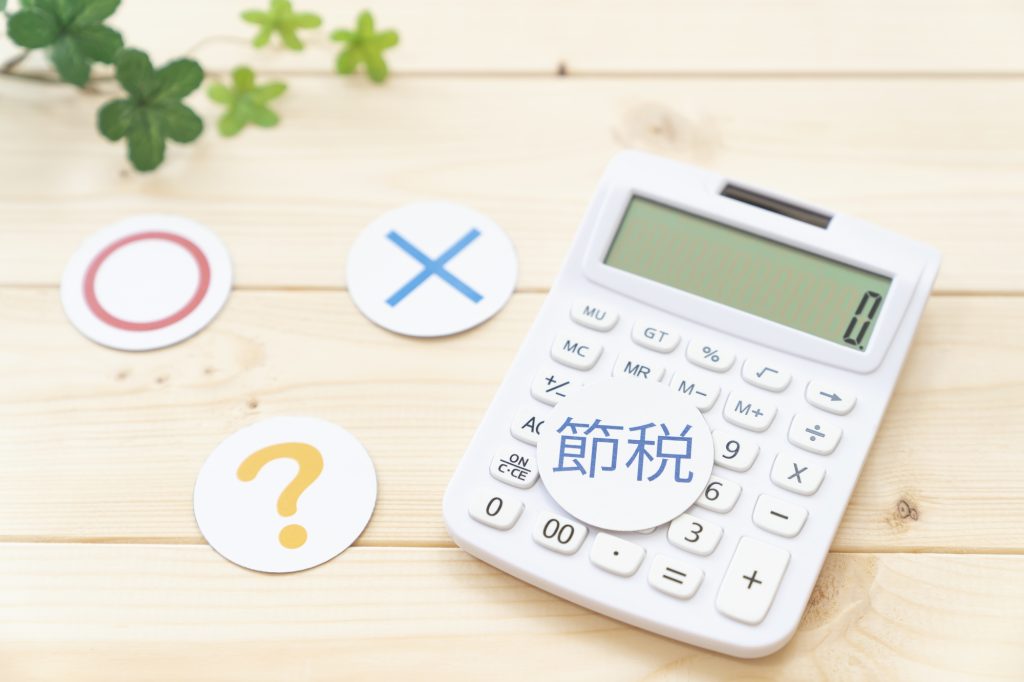
節税とは控除・特例・仕組みを活用して、合法的に負担する税金を減らす行動のことです。
法律の範囲内での節税は国が認めているものの、違法行為によって税金を減らす行動は脱税となり、ペナルティの対象となります。
サラリーマンの節税は法人に比べて手段が限られていますが、上手く活用することで可処分所得(手取り)を増やしたり、老後資金を増やせたりします。
所得税・住民税・社会保険料が主な対象
サラリーマンが節税を考える際に重要なのは主に以下の3つです。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
上記はいずれも、会社から支給される給与(=給与所得)を基に計算されており、課税対象となる「所得金額」を減らすことで、負担を軽減できます。
所得税と住民税は、給与から給与所得控除と各種所得控除を差し引いた後の「課税所得」に対して課税されます。
ふるさと納税やiDeCo、生命保険料控除、医療費控除などを活用することで、この課税所得を減らすことで結果として税額が下がります。
社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、給与の金額に応じて決まる標準報酬月額を基に計算されます。
控除による直接の軽減はできませんが、福利厚生制度を利用して現物支給に切り替えるなど、課税対象外の形にする工夫が有効です。
サラリーマンの節税は「手取り収入を増やす」ための賢い工夫であり、制度を正しく理解して使うことで、税や保険料の支出を最小限に抑えることができます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
サラリーマンに可能な節税対策12選

ここではサラリーマンでも取り組める主な節税対策を紹介していきます。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引くことで所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となる条件は、以下の通りです。
- 納税者と生計を一にする親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 対象者の年間所得が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)
- 16歳以上であること(16歳未満は対象外)
控除額の一例は、次の通りです。
- 一般の扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 70歳以上の親を扶養している場合:同居なら58万円、別居なら48万円
扶養控除を受けるには、年末調整または確定申告で「扶養控除申告書」を提出する必要があります。
また扶養に該当するかどうかはその年の収入見込みで判断されるため、パートやアルバイト収入のある家族の年収は早めに確認しておきましょう。
控除によって課税所得が下がり、所得税率の階層が変わることで、結果的に手取りが増える可能性もあります。
医療費控除
医療費控除とは、自分や家族のために支払った年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。
医療費控除の条件は、以下の通りです。
- 本人や生計を一にする配偶者・扶養親族の医療費であること
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円超(所得が200万円未満の場合は所得の5%超)であること
- 医師の診療・治療費、通院に必要な交通費(公共交通機関)、薬代などであること
※予防接種や美容整形費用は対象外
▼計算方法
控除額 = 実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(または所得の5%)
控除を受けるためには確定申告が必要で、年末調整では対応できません。
申告に備えて、医療機関の領収書や薬局のレシートは必ず保管しましょう。通院の交通費についても、利用日・目的地・金額を記録しておくとスムーズです。
なお申告期限を過ぎても過去5年間までさかのぼって申請できるため、高額な医療費を支払った年は忘れずに確認しておきましょう。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間で一定額以上購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。
ただし、前述の医療費控除とは併用できず、どちらか一方を選んで申告する必要があります。
セルフメディケーション税制の条件は、以下の通りです。
- 対象者が健康診断・がん検診・予防接種などを受けていること
- 対象となるスイッチOTC医薬品を1年間で12,000円を超えて購入していること
- 控除対象額の上限は88,000円
▼計算方法
控除額 = 対象医薬品の年間購入額 - 12,000円(上限88,000円)
※例:年間で25,000円購入 → 控除額は13,000円
購入時にはパッケージやレシートに「セルフメディケーション税控除対象」の記載があるか確認しましょう。
申告時には、対象医薬品の購入明細書やレシートに加え、健康診断等を受けた証明書類(健診結果、予防接種証明など)が必要です。
市販薬を日常的に利用している方は、通常の医療費控除よりも有利になる場合があるため、1年間の支出額を比較し、どちらの制度を選ぶか判断することが大切です。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
生命保険料控除
生命保険料控除は、年間に支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となる保険は、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分で、以下の条件を満たす必要があります。
- 申告者本人が契約者で保険料を支払っていること
- 原則として国内の保険会社等に支払っていること
- 対象保険のいずれかの区分に該当すること
- 年末調整または確定申告で生命保険料控除証明書を提出すること
各区分ごとに最大4万円(住民税は2.8万円)まで控除可能であり、すべての区分に該当する場合は最大12万円(住民税は7万円)が控除されます。
控除を有効に活用するには、加入している保険がどの区分に当たるかを確認し、必要に応じて内容の見直しを検討しましょう。
複数の保険に加入している場合は、合算して控除額を最適化することも可能です。
地震保険料控除
地震保険料控除は、地震保険に加入し、保険料を支払った場合に所得控除を受けられる制度です。
地震による被害への備えを促進する目的で設けられており、所得税や住民税の負担を軽減できます。
地震保険料控除の条件は以下の通りです。
- 申告者が保険の契約者本人であること
- 地震保険の対象が契約者本人、またはその家族の所有物であること
控除の対象は地震保険料のみです。火災保険料だけでは対象になりませんが、火災保険に地震保険が付帯している場合、その地震保険料分が控除の対象となります。
なお地震保険をかけている物が自身の所有物であることが条件であり、第三者であるオーナーに借りている賃貸物件などは地震保険料控除の対象外です。
▼計算方法
- 所得税:年間支払額の全額(上限5万円)
- 住民税:年間支払額の全額(上限2万5,000円)
※旧長期損害保険の経過措置に該当する場合は別途計算が必要
地震保険料は火災保険とセットで契約されていることが多いため、見落とさずに「控除証明書」で対象金額を確認し、正確に申告しましょう。
複数の契約や年の途中での支払いがある場合も、証明書をもとに合算して申告できます。
特定支出控除
特定支出控除は、サラリーマンなどの給与所得者が業務に関連して支払った特定の費用について、一定の条件を満たせば所得控除を受けられる制度です。
通常の給与所得控除に上乗せして認められる制度であり、自己負担の多い人にとっては節税効果が期待できます。
特定支出控除の条件は、以下の通りです。
- 給与所得者であること
- 支出が年間の給与所得控除額の1/2を超えていること
- 会社からの証明書(特定支出証明書)を支出ごとに取得していること
- 確定申告で領収書などの必要書類を提出すること
対象となる支出は次の通りで、会社が必要と認めたものに限ります。
- 通勤費(通勤定期代など)
- 転居費(転勤による引っ越し費用)
- 研修費(業務関連の研修)
- 資格取得費(業務に必要な資格)
- 帰宅旅費(単身赴任者の帰省費用)
- 図書費・衣服費・交際費(一定の職種に限る)
▼計算方法
控除額 = 特定支出の合計額 −(給与所得控除額 × 1/2)
例:給与収入600万円の場合、給与所得控除額174万円 → その半分87万円を超えた支出が控除対象
支出ごとに会社の証明書(特定支出証明書)を取得し、領収書などの証拠書類とともに確定申告で申請する必要があります。
申請手続きが煩雑なため、事前に対象となる支出かどうかを確認し、書類を整えておくことが重要です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に、年末時点のローン残高に応じて所得税が控除される制度です。
一定の条件を満たせば、最大13年間にわたり控除を受けられます。
住宅借入金等特別控除の条件は、以下の通りです。
- 自ら居住する住宅であること(賃貸や別荘は対象外)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 床面積が原則50㎡以上(条件により40㎡以上も可)
- 入居した年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 一定の省エネ基準や中古住宅の条件を満たすこと(物件により異なる)
▼計算方法
控除額=年末時点の住宅ローン残高 × 控除率(通常0.7%)
※上限は年ごとに異なり、新築・中古、認定住宅などで変動します。
初年度は確定申告が必須で、2年目以降はサラリーマンであれば年末調整で手続きできます。
住宅ローンの年末残高証明書や、登記簿謄本、売買契約書などの添付書類が必要になるため、あらかじめ準備を整えておきましょう。
制度内容は年度や物件の種別によって変更されることがあるため、購入前に最新情報を確認することが重要です。
正しく手続きすれば大きな節税効果が期待できるため、住宅取得時には必ず検討したい制度です。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をおこなうことで、2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度です。寄付先は出身地に限らず、全国の任意の自治体から選べます。
これは翌年度の住民税の一部を前払いする仕組みで、実質的な節税効果はありませんが、見返りとして地元の特産品などの返礼品がもらえるため、通常の納税よりお得だといえます。
返礼品には、お米・牛肉・お酒・宿泊券などさまざまな種類があり、日常生活の負担を軽減できます。
ふるさと納税の条件は、以下の通りです。
- 寄付者本人に課税所得があること
- 同一年に複数の自治体に寄付する場合、確定申告またはワンストップ特例制度の利用が必要
▼計算方法
控除額=寄付金額 − 2,000円(上限あり)
※控除対象上限額は、ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターなどで事前確認が可能
確定申告をしない場合、寄付先の自治体が5つ以内であれば「ワンストップ特例制度」を利用することで簡単に手続きが完了します。ただし、申請書の提出期限や書類の記載ミスに注意が必要です。
ふるさと納税は、税制上の優遇と地域貢献、返礼品という3つのメリットが揃った制度であり、計画的に活用することで家計にも地域にもプラスになります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)は、自分自身で積み立てと運用をおこない、将来の年金として受け取る制度です。
iDeCo(個人型)と企業型DCがあり、いずれも拠出金が所得控除の対象となるため、節税効果が期待できます。
iDeCo(個人型)と企業型DCそれぞれの条件は、以下の通りです。
- iDeCo(個人型):原則20歳以上60歳未満の公的年金加入者が対象(職業により拠出上限が異なる)
- 企業型DC:企業が導入していることが前提で、加入には会社の制度に従う必要がある
- 両制度共通:原則60歳まで引き出し不可
▼計算方法
iDeCoの場合、掛金の全額が所得控除対象
例:年間24万円を拠出した場合、課税所得から24万円が差し引かれる
拠出上限は職種・企業制度により異なりますが、月額1.2万円から6.8万円が目安となります。
iDeCoは長期運用を前提とするため、リスク分散を意識した資産配分が重要です。60歳まで原則引き出せないため、生活資金とは分けて積立てましょう。
企業型DCでは、会社が掛金を負担するケースも多く、制度をよく理解することで自分に合った運用ができます。
またiDeCoと企業型DCを併用できる場合もあるため、制度の違いや上限を確認しながら最適な活用を心がけましょう。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)は、一定の投資額までの運用益や配当金が非課税になる制度です。
2024年から制度が大幅に見直され、「新NISA」として恒久化され、非課税枠も拡充されました。
NISAの条件は、以下の通りです。
- 日本在住の18歳以上の個人であること
- 1人1口座のみ開設可能で、証券会社をまたいでの複数口座の併用は不可
- 口座開設にはマイナンバーと本人確認書類が必要
▼計算方法
- 年間投資上限:合計360万円
- 内訳:つみたて投資枠(120万円)+成長投資枠(240万円)
- 生涯非課税保有限度額:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
利益に対する約20%の税金が非課税になるため、長期的に大きな節税効果が期待されます
NISAは、長期・分散・積立投資に適した制度です。初心者には、手数料が低く分散投資ができるインデックス型投資信託を利用した「つみたて投資枠」がおすすめです。
また年間の非課税枠を無駄なく使うには、毎月の積立計画を立てて自動積立を活用することが効果的です。
投資先はNISAの対象商品に限られるため、金融機関ごとの取り扱い内容も確認しましょう。
ひとり親控除
ひとり親控除とは、子どもを養育しているひとり親に対して所得税や住民税の負担を軽減する制度です。2020年からは男女問わず適用され、寡婦(寡夫)控除と一本化されました。
ひとり親控除の条件は、以下の通りです。
- 納税者が婚姻歴のない単身者または離婚・死別後の単身者であること
- 所得48万円以下の子どもを扶養していること
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
▼計算方法
- 所得税:35万円の所得控除
- 住民税:30万円の所得控除
控除を受けるには、年末調整または確定申告で「扶養控除等申告書」の提出が必要です。所得制限や扶養の判定基準に注意し、年内に収入状況や家族構成を確認しておくことが大切です。
またひとり親控除は配偶者がいないことが前提となるため、内縁関係にある場合などは適用外となることがあります。誤申告を防ぐためにも、不明点がある場合は税務署や勤務先に事前に相談しましょう。
不動産投資
不動産投資とは、マンションやアパート、戸建てなどの不動産を購入し、賃貸収入や売却益を得ることを目的とした資産運用の方法です。
安定した家賃収入や節税効果が期待できる一方で、初期投資や管理の手間、空室リスクも考慮する必要があります。
投資には一定の自己資金が必要ですが、住宅ローンなどの融資審査を通過すれば誰でも始められます。
成功のポイントは、立地条件や入居需要の高い物件の選定に加え、賃貸経営、税務、法務の基本知識を身に付けることです。
▼計算方法
- 年間収入 = 家賃 × 12ヶ月
- 年間支出 = ローン返済 + 管理費 + 修繕費 + 固定資産税など
- 年間利益(不動産所得) = 年間収入 − 年間支出
この不動産所得は確定申告により所得税の対象となり、必要経費を差し引くことで節税効果も得られます。
物件選びでは、築年数や管理状況、周辺環境を慎重に確認しましょう。初心者は中古ワンルームマンションなど小規模投資から始めてリスクを最小限に抑えることがおすすめです。
購入後も賃貸管理や税務処理が必要なため、不動産管理会社や税理士の活用も検討すると良いでしょう。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
サラリーマンでもできる節税対策は多岐にわたり、制度を上手く制度を活用すれば手取り額を増やすことができます。
制度ごとに控除の条件は異なるため、あらかじめ自身の状況に当てはまる制度を調べておくと良いでしょう。
節税対策は負担する税金を合法的に減らすことで手取り額を増やす手段ですが、さらに自由に使えるお金が欲しい方は副業を始めるのも1つの手です。
副業にはWEBデザインや動画編集などの種類がありますが、未経験から安定収入を目指すならフランチャイズへの加盟がおすすめです。
フランチャイズは業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、集客や営業、仕入れ、商品開発をサポートしているため、早期に成功しやすい傾向にあります。









