事業を経営する方を事業主と呼びますが、法人と個人事業主のどちらでビジネスを展開すれば良いのか困っている方も中にはいるのではないでしょうか。
そこで今回は事業主の基礎知識や法人・個人事業の違い、それぞれのメリットなどを紹介していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
事業主とは?

事業主とは、事業を自らの責任で経営・運営する方のことです。
大きく分けて、個人で営む「個人事業主」と、会社を設立して経営する「法人事業主」の2種類があります。
事業主は、利益を得る立場である一方で、税金の申告や社会保険の手続き、従業員の雇用管理など、多くの義務を負います。経営判断や資金調達など、事業全体を統括する役割も担っています。
個人事業主と会社との違い
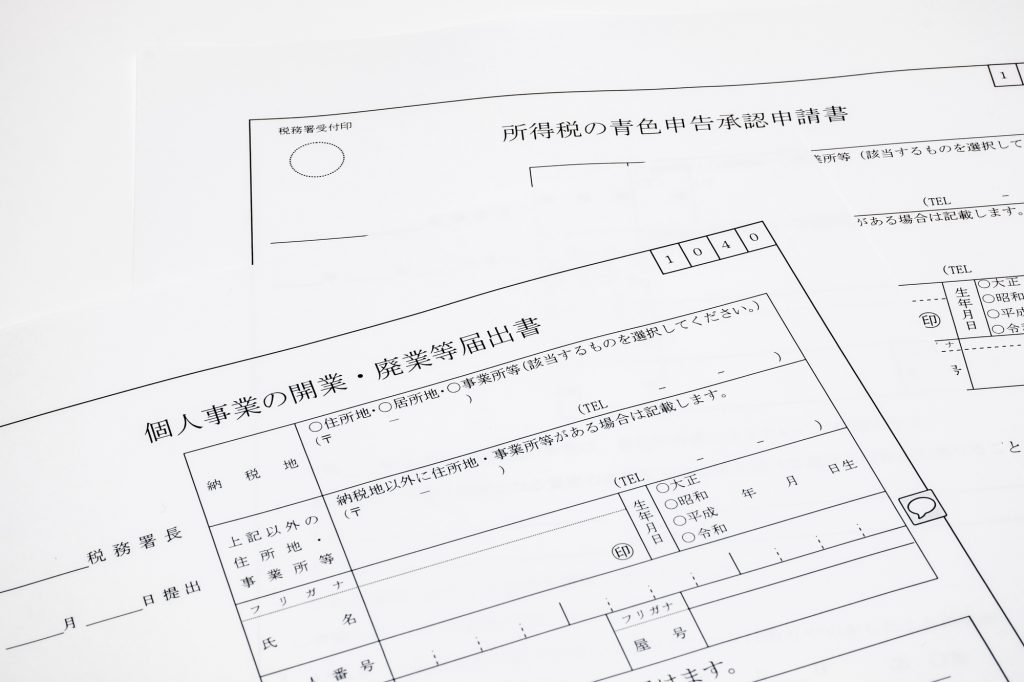
個人事業主と会社(法人)は、以下の点で異なります。
- 開業手続き
- 税金負担の違い
- 社会保険制度の適用条件
- 資金調達のしやすさ
- 社会的信用度の差
- 経費計上できる範囲
それぞれ詳しく解説していきます。
①開業手続きの比較
個人事業主の開業手続きは非常に簡単で、税務署に「開業届」を提出するだけで完了します。電子申請であれば費用はかからず、1日で手続きが完了します。
その一方で、法人を設立するには、定款の作成や公証人による認証、法務局での登記など複数の手続きが必要です。
設立には登録免許税や定款認証費用など、少なくとも22万円から25万円前後の費用がかかり、手続きの完了までに1ヶ月ほど要する場合もあります。
開業手続きの手軽さでは、個人事業主の方が大きなメリットがあります。
②税金負担の違い
税金面では、個人事業主は「所得税」、法人は「法人税」が課されます。所得税は累進課税制度が採用されており、所得が少ないうちは税負担が軽く、所得が増えるにつれて税率も上がる仕組みです。
国税庁の「No.2260 所得税の税率」で発表されている速算表を見れば分かるように、以下のように段階的に所得税が増えていきます。
| 課税所得(年間) | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
所得が増えると、累進課税制度により個人事業主の税負担は法人より重くなる傾向があります。
その一方で、法人に課されている法人税は原則23.2%(中小法人は一部15%の軽減税率)と一定になっており、利益が大きいほど税率の差による節税効果が期待できます。
たとえば年間利益が500万円の場合、個人事業主には約20%の所得税がかかるのに対し、法人なら15〜23%程度に抑えられます。
そのため、一定以上の利益を確保できるようになったタイミングで、節税を目的に法人化を選ぶ起業家も少なくありません。
③社会保険制度の適用条件
法人は、たとえ役員が1人だけでも原則として健康保険と厚生年金への加入が義務付けられています。
その一方で、個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を雇用する特定業種(飲食・製造・販売など)でない限り、社会保険への加入義務はありません。そのため、従業員が少ない場合は国民健康保険と国民年金で対応するケースが一般的です。
社会保険料は、事業主と従業員でほぼ折半するため、法人ではコストが増える反面、傷病手当金や将来の年金額など、保障が手厚いというメリットがあります。個人事業主は保険料負担は軽いものの、受けられる保障は限定されてしまう傾向にあります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
④資金調達のしやすさ
資金調達の面では、法人の方が有利です。法人は金融機関からの融資に加え、増資や株式発行といった多岐にわたる方法を活用できます。
また、定款が公開・経営の透明性が確保されているため、信用を得やすく、大口や長期の融資審査にも通りやすい傾向があります。
その一方で、個人事業主は事業と個人が一体であるため、事業計画や個人の信用情報が直接審査に影響します。
日本政策金融公庫では創業資金の融資を受けられることもありますが、十分な実績がなければ融資額は数百万円規模にとどまることが多く、資金調達の選択肢も限定されてしまう傾向にあります。
このように、資金調達の柔軟性では法人に軍配が上がります。
⑤社会的信用度の差
法人は法務局に登記され、定款や組織体制が明確であるため、社会的信用が高い傾向にあります。
取引先や金融機関からの信頼も得やすく、大手企業との契約や高額融資、助成金申請などで有利に働く場面が多くあります。
その一方で、個人事業主は事業と個人の区分が曖昧で経営状況も見えづらいため、信用力が低くなりやすい傾向にあります。
特にBtoB取引や公共事業では法人格が求められることが多く、契約機会が限られるケースもあります。
ただし、小規模な飲食店やフリーランスなど、業種によっては実績を積めば個人でも信用を築きやすい分野も存在します。
⑥経費計上できる範囲
経費計上の範囲は、法人の方が広く柔軟です。たとえば、法人では役員報酬や賞与、社宅費用、家族への給与も一定条件下で経費として認められます。
その一方で、個人事業主は自分自身への報酬や家族への給与(青色申告専従者給与を除く)を経費にできず、交際費や仕事場として使う自宅家賃の按分にも制限があります。
この差は課税所得に大きく影響し、法人の方が実質的に節税しやすい傾向があります。同じ売上でも、法人は経費を多く計上できるため、結果として税負担を抑えられる可能性が高くなります。
個人事業主のメリット

個人事業主のメリットは、以下の通りです。
- 開業が手軽で低コスト
- 経営の自由度の高さ
- 利益のすべて自分のものにできる
- 税務申告の簡素さ
それぞれ詳しく解説していきます。
①開業の手軽さと低コスト
個人事業主として開業するには、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけで手続きが完了します。
必要書類は本人確認書類のみで、提出は郵送・持参・e-Taxから選べます。e-Taxで申請する場合、費用は一切かからず、最短で即日の開業もできます。
その一方で、法人設立には定款作成・認証、法務局での登記など複数の工程があり、登録免許税や定款認証費用を含めて22万円から25万円前後の費用が必要です。
このように個人事業主は手続きがシンプルで開業コストも低いため、初めて事業を始める人にとって参入しやすい選択肢です。
②自由度の高い経営判断
個人事業主は経営判断をすべて自分1人でおこなえるため、意思決定のスピードが速く、事業方針やサービス内容の変更なども柔軟に対応できます。
たとえば、メニューの改定や営業時間の変更、新規事業の開始なども即日実行できます。
その一方で、法人では役員会議や株主総会での承認が必要となるケースが多く、意思決定に時間がかかる場合があります。特に組織が大きくなるほど調整が増え、スピーディーな対応が難しくなります。
このように、個人事業主は自由度の高い経営スタイルを維持しやすい点が大きなメリットです。
③利益をすべて自分のものにできる
個人事業主は、事業で得た利益をそのまま個人の収入として自由に使える点が大きな特徴です。法人のように役員報酬や配当といった形式を取る必要はありません。
その一方で法人の場合、利益は一旦会社のものとなり、役員報酬として定期的に支給するか、決算後に配当として分配する必要があります。
そのため、資金の引き出しには制限があり、資金繰りの柔軟性が欠ける場合もあります。個人事業主はこうした煩雑さがない分、資金管理の自由度が高い点がメリットです。
④税務申告の簡素さ
個人事業主の税務申告は、法人に比べて手続きが簡単です。確定申告は年1回で、白色申告なら簡易な記帳と収支内訳書の提出のみで済みます。
青色申告を選択すれば、複式簿記での記帳や貸借対照表・損益計算書の作成が必要ですが、最大65万円の特別控除などのメリットがあります。
その一方で、法人は法人税に加え、消費税や地方税の申告・納付も必要で、会計処理も複雑なため、税理士への依頼がほぼ不可欠です。
個人事業主は自身で対応可能な範囲が広く、事務負担が比較的少ないのが特徴です。
法人のメリット

法人のメリットは、以下の通りです。
- 有限責任で個人財産を守れる
- 節税効果が得られる
- 社会保険による福利厚生がある
- 事業継続・承継がしやすい
- 取引先から信頼されやすい
それぞれ詳しく解説していきます。
①有限責任で個人財産を守れる
法人の最大のメリットは、有限責任制度によって出資者の個人財産が保護される点です。たとえば株式会社では、事業で多額の負債を抱えても、原則として出資額(資本金)以上の責任を負う必要はありません。
会社が倒産しても、個人の貯金や自宅などが差し押さえられることはありません。
その一方で、個人事業主は「無限責任」であり、事業の借金や損失はすべて本人が背負うことになります。事業が失敗した場合、個人の財産まで差し押さえられるリスクがあります。
法人化することでリスクを抑えつつ、経営に取り組むことができます。
②節税効果が得られる場合
所得が一定額を超えると、法人化することで節税効果が期待できます。個人事業主は累進課税制度により、所得が増えるほど税率も上がり、課税所得が900万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%の所得税が課されます。
その一方で、法人税は中小企業であれば年間800万円以下の所得に対して約15%、800万円超の部分は約23.2%が適用され、税率は比較的安定しています。たとえば、年間利益が1,000万円の場合、法人化すれば税率を抑えることができます。
さらに法人では役員報酬として利益を分散できるため、家族を役員にすれば世帯全体の税負担を軽減することも可能です。
また、法人の方が経費として認められる範囲が広く、社宅や役員報酬、福利厚生費などを経費計上できる点も節税に有利です。
③社会保険による福利厚生
法人を設立すると、役員や従業員は厚生年金と健康保険に加入でき、より手厚い福利厚生を受けられます。
国民健康保険と比べて給付内容が充実しており、出産手当金や傷病手当金などの制度も利用可能です。
また厚生年金は国民年金よりも将来の年金受給額が多くなる傾向があり、老後の安心にもつながります。
さらに、一定の条件を満たせば扶養家族も保険の対象となり、追加の保険料負担なしでカバーできます。
このように法人化は、従業員の待遇向上や人材採用の面でも有利に働きます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
④事業継続・承継のしやすさ
法人は「会社」という独立した人格を持つため、経営者が変わっても事業を継続することができます。株式を譲渡するだけで経営権を移せるため、親族や第三者へのスムーズな事業承継が可能です。
その一方で、個人事業主は事業と経営者が一体であるため、承継時には名義変更や資産の引き継ぎ手続きが複雑になりやすく、事業の継続性にも不安が残ります。
また、法人化しておけば相続税対策としての効果も期待でき、事業資産を計画的に承継しやすくなります。こうした点から、法人は将来的な事業の安定と永続性に優れた選択肢といえます。
⑤取引先からの信頼獲得
法人は登記によって法的に認められた存在であり、社会的信用が高いため、取引先や金融機関からの信頼を得やすいのが特徴です。
特に大企業との取引や公共事業の入札では、法人格を持っていることが前提条件となることが多く、ビジネスチャンスが広がります。
また、財務状況や事業計画が明確な法人は融資審査でも評価されやすく、資金調達においても有利です。
このように法人化は信頼性を高め、事業拡大に向けた重要な1歩だといえます。
事業形態の選び方

事業形態を選ぶ際は、以下のような要素を総合的に判断することが重要です。
- 年間収益
- 事業規模
- 成長計画
- 業種
- 将来展開
それぞれ詳しく解説していきます。
①年間収益による判断
事業の年間収益が一定額を超えると、個人事業主より法人の方が税制上有利になる場合があります。一般的に、年間所得が800万円を超えるあたりから法人化を検討するケースが増えます。
たとえば、個人事業主が900万円の所得を得た場合、累進課税により所得税と住民税を合わせて約33%前後の税負担が生じます。
その一方で、法人であれば800万円以下は約15%、超過分は23.2%程度と、全体の税率を抑えやすくなります。
また法人化により経費計上の幅が広がるほか、家族に役員報酬を支給することで所得を分散し、世帯全体の税負担を軽減することも可能です。
収益が一定以上見込める場合は、節税と資金管理の面から法人化は最適な選択肢になるでしょう。
②事業規模と成長計画
事業規模や成長計画に応じて、最適な事業形態は変わります。たとえば、従業員を増やして複数店舗を展開するなど、事業拡大を目指す場合は法人化が効果的です。
法人化することで社会的信用が高まり、資金調達や人材採用、取引先との契約面でも有利に働きます。
その一方で、1人で完結するフリーランスや小規模店舗などの事業であれば手続きが簡単で負担の少ない個人事業主の形態が適しています。将来の方向性に合わせて、柔軟に事業形態を選ぶことが重要です。
③業種別の最適形態
業種によって最適な事業形態は異なります。たとえば、BtoBが中心のIT業やコンサル業では、社会的信用の高い法人の方が契約や資金調達で有利です。
また、製造業や建設業など、事故や損害リスクが高い事業も有限責任である法人の方が適しています。
その一方で、美容師・ライター・講師などの専門職や小規模な小売・サービス業では、手続きが簡単でコストも低い個人事業主が向いているケースが多く見られます。
業種の特性を踏まえて、信頼性・リスク・コストのバランスを考慮した選択が重要です。
④将来展開を見据えた選択
将来の事業展開を見据えることも事業形態選びの重要なポイントです。たとえば、従業員数の拡大や外部からの資金調達、将来的な第三者への事業承継を考えている場合は、法人化が適しています。
法人であれば組織としての体制が整っており、信用力も高いため、人材採用や資金調達、株式による事業承継などがスムーズにおこなえます。
その一方で、ライフステージに合わせて事業を無理なく続けたい場合や家族経営で完結する範囲であれば、個人事業主のままでも十分です。今後の展望に応じて、柔軟に形態を見直していくと良いでしょう。
よくある質問

ここでは事業主に関するよくある質問を紹介していきます。
会社の事業主は誰ですか
法人の場合、事業主は会社そのものであり、「株式会社〇〇」や「合同会社〇〇」などの法人名が事業主となります。
代表取締役や社長は、あくまで法人を運営・代表する立場であって、個人としての事業主ではありません。
たとえば、申請書類や契約書で「事業主名」の記載が求められた場合は、「株式会社〇〇」と法人名を記載し、必要に応じて代表者名を添えるのが一般的です。実務上でも、法人と代表者の区別を明確にすることが重要です。
事業主と社長の違いは何ですか
「事業主」は事業の所有者を指し、個人事業主であれば本人そのもの、法人であれば法人自体が事業主となります。
その一方で「社長」は、法人における経営の最高責任者であり、一般的には代表取締役を指します。つまり、事業の所有者と経営の実務責任者は必ずしも同一ではありません。
個人事業主が「社長」と名乗ることもありますが、正式な肩書きではなく、あくまで通称や対外的な呼称にすぎません。
実務上では、名刺や案内状などに「代表」「店主」「経営責任者」などと表記するケースも多く見られます。呼称は役割に応じて適切に使い分けることが大切です。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
法人・個人事業主にはそれぞれメリットがありますが、展開する事業の規模に応じて形態を選ぶことが大切です。
個人事業主は、所得が少ないうちは納税額も少なくて済む一方、累進課税制度により所得が増えると税負担が重くなります。そのため、最初は個人事業主として開業し、一定の利益が安定して確保できるようになった段階で法人化するケースも多く見られます。
すでにコネクションが十分にあり、起業したばかりでもある程度の利益が見込める場合は、最初から法人として起業するのも良いでしょう。
実績もコネクションも十分にないという場合は、リスクを抑えられる個人事業主が適しています。
初めての起業や異業種参入でも安定した経営をしたい場合は、フランチャイズ加盟店として起業するのも1つの手です。
フランチャイズは本部が経営ノウハウを提供しているほか、営業、集客、商品開発、仕入れなどをサポートしているため、未経験の方でも早期な黒字化を目指しやすい傾向にあります。









