株式会社は国内で最も多い法人形態であり、多くの起業家が選択していますが、株式会社にどういったメリットがあるのか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は株式会社の基礎知識やメリット・デメリット、合同会社との違いなどを網羅的に解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
株式会社とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

株式会社は、株式を発行して資金を調達し経営をおこなう、国内で最も一般的な法人形態です。
株式は出資者に発行される証券で、保有者を「株主」と呼びますが、株主には以下のようなメリットがあります。
- 配当金や株主優待を受け取れる
- 株式の売買によって利益を得られる可能性がある
- 会社解散時に残った財産の一部を受け取れる場合がある
- 株主総会に参加し、会社経営に関与できる
日本で新たに設立できる法人形態には、主に以下の種類がありますが、一般的には株式会社と合同会社が多く選ばれています。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人
株式会社と合同会社の主な違いは、次の通りです。
| 法人形態 | 株式会社 | 合同会社 |
| 所有者 | 株主 | 社員 |
| 経営者 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 役員の任期 | 2年から10年 | 任期なし |
| 監査役の人数 | 1人以上必要 | 不要 |
| 利益配分 | 出資割合に応じて分配 | 定款で自由に規定可能 |
| 決算公告 | 必須 | 不要 |
| 定款 | 必須 | 作成は必須、認証は不要 |
| 設立費用 | 22万円から25万円前後 | 10万円前後 |
| 資金調達の種類 | 株式発行など幅が広い | 株式発行ができず幅が狭い |
| 社会的な信頼性 | 金融機関・取引先から最も信頼される | 設立しやすいことから株式会社よりも信頼性が劣る |
会社の資金調達の仕組み
株式会社は、株式を発行して資金を調達できるという他の法人形態にはない独自の強みを持ちます。株主となる出資者は出資額以上の損失を負うことがないためリスクが小さく、多くの投資家を集めやすい点が特徴的です。
株式による資金調達をおこなった株式会社は、その資金を元に事業を拡大し、利益向上を目指します。投資家は、会社が利益を上げれば配当金を受け取れるほか、株価が上昇すれば売却によって利益を得ることも可能です。
また、株式会社は以下のような多様な方法で資金調達が可能です。手続きの複雑さや所在地・資本金の公表といった特徴がありますが、投資家の信頼を得やすく、資金調達が成功しやすい傾向があります。
- 金融機関や行政の融資
- 投資家やVCからの出資
- ファクタリングやリースバックの利用
- 補助金・助成金の活用
- クラウドファンディングの活用 など

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
所有と経営の分離の仕組み
所有と経営の分離とは、株式会社の所有者である株主と経営者を分離する仕組みのことであり、多くの大手企業や上場企業で導入されています。
会社の所有には一定以上の資金力、経営には利益を生み出す経営スキルが必須になります。しかし、経営者がその両方を兼ね備えていることは少ないため、所有と経営の分離によって資金を確保しつつ、効率的な経営をおこなうことができます。
また所有と経営の分離によって所有者が経営を客観的に評価・監視できるため、不祥事の発生を抑え、コーポレートガバナンスの強化もおこなえます。
その一方で中小企業庁の「2018年版 中小企業白書」で説明されている通り、中小企業においては72%が経営者が会社を所有するオーナー経営企業となっています。
所有と経営の一致によって経営者が所有者を兼ねている場合、意思決定のスピードが速くなるというメリットがある一方、経営者に権力が一極集中・監視の目がないことで独断的な経営や不祥事のリスクが高まる可能性があります。
株式会社のメリット

前述したように株式会社は得られるメリットを期待されて、国内では法人形態のなかで最も選ばれています。
ここでは株式会社の代表的なメリットを解説していきます。
信用力が高まり融資が受けやすい
株式会社設立時に法務局に提出する登記簿謄本には、商号や所在地、資本金、事業の目的などを記載します。
これらの情報は世間一般に公開される仕組みであるため、社会的な信頼を得やすく、金融機関や取引先からの評価も高くなる傾向にあります。
また融資などの資金調達時には、登記簿謄本が企業の信用力を示す判断材料の1つになるため、比較的に資金調達がしやすくなります。
事業拡大時の資金調達がスムーズ
株式会社は、株式発行によって資金調達がおこなえるため、事業拡大時もスムーズに資金を確保できます。
株式で集めた資金は返済義務がなく、使用用途の自由度が高いのが大きなメリットです。また、株主は出資額以上の責任を負わない間接有限責任のため、資金を集めやすいという特徴があります。
株式会社が株式を発行する方法には複数ありますが、最も一般的な第三者割当増資は、以下の手順でおこなわれます。
- 募集事項の決議の実施
- 募集事項を投資家・株主に通知する
- 出資希望者の申込内容の確認
- 株主総会・取締役会で出資希望者への株式の割り当て
- 出資希望者からの払い込みの確認
- 登記で資本金の変更をおこなう
経営者の個人財産が保護される
会社が倒産した場合、経営者は負債を支払う責任を負います。責任の範囲は法人形態によって有限責任か無限責任のいずれかに分かれます。
株式会社は有限責任であり、出資者が負う責任は出資額の範囲内に限られます。そのため、事業が失敗してもリスクを最小限に抑えられます。
設立した株式会社が倒産した場合、出資額は回収できなくなるものの、それ以上の責任を問われることはなく、経営者の個人財産は保護されます。
一方、合名会社・合資会社・個人事業主の場合は無限責任となるため、会社が負債を支払えない場合、経営者は個人の財産から負債の全額を支払う義務を負います。
事業を撤退した後も、金融機関からの借入や滞納税金、取引先・仕入先への未払い金は、代表者が個人の負債として支払わなければなりません。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
株式会社のデメリット
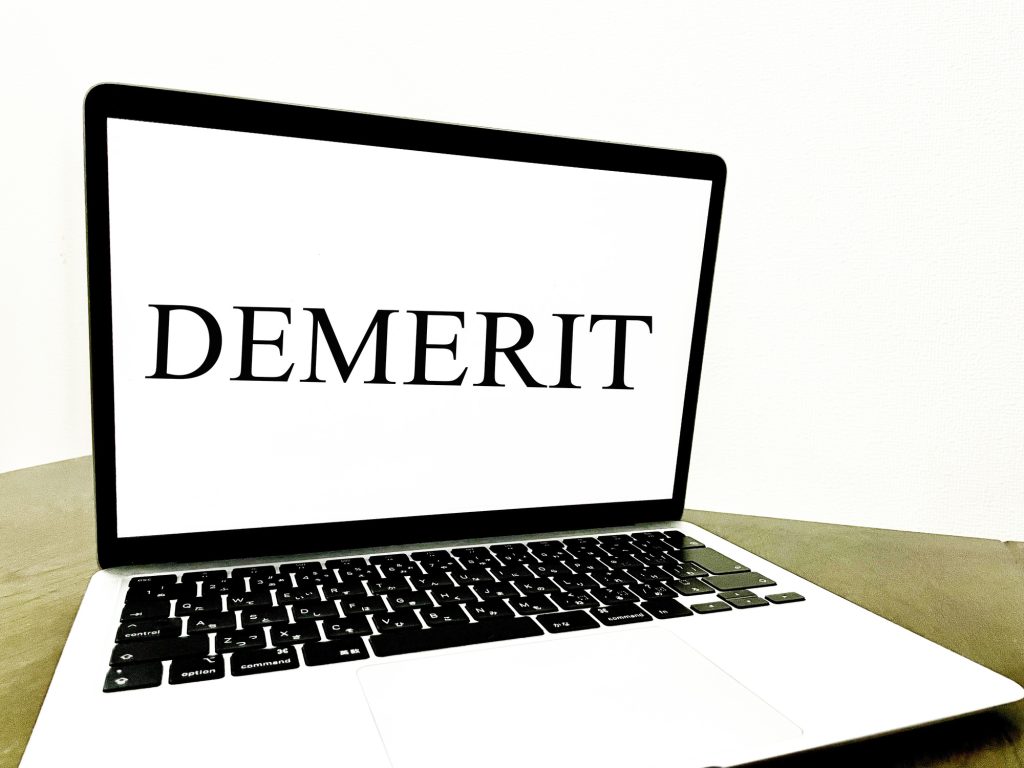
株式会社には多岐にわたるメリットがある一方で決して無視できないデメリットもいくつか存在します。
ここでは株式会社特有のデメリットをご紹介していきます。
設立時の手続きが複雑
株式会社は最も社会的な信頼を得やすい法人形態であるものの、設立時の手続きが複雑です。
詳しくは後述しますが、主な設立の手続きは以下の通りです。
- 社名や所在地、役員の構成など会社概要の決定
- 法人用の実印の作成
- 定款の作成と認証手続き
- 資本金(出資金)の準備と払い込み
- 登記申請書類の作成と申請
申請には以下の書類が必須で、受理までに1ヶ月ほどかかることもあるため、計画的に進める必要があります。
| 提出書類 | 提出先 |
| ・発起人会議事録(発起人決定書) ・登記申請書 ・登録免許税納付用台紙 ・代表取締役の就任承諾書 ・取締役の就任承諾書 ・設立時取締役の印鑑証明書 ・資本金の払い込みを証明する書類 ・印鑑届出書 ・「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R | 法務局 |
| 定款 | 公証役場 |
設立費用の負担が大きい
株式会社は設立手続きが複雑なだけでなく、設立時に22万円から25万円前後の費用が発生するのもデメリットだといえます。
設立費用の内訳は以下の通りです。
| 収入印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
| 謄本の発行手数料 | 約2,000円 |
| 定款の認証手数料 | 資本金100万円未満:30,000円資本金 100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 |
| 登録免除税 | 150,000円もしくは資本金×0.7%のどちらか高い方 |
| 合計 | 22万円から25万円前後 |
電子定款を利用すれば収入印紙代が発生しないものの、電子定款のための専用機器・専用ツールを用意する必要があります。
状況によっては導入コストの方が上回ってしまうため、あらかじめコストを十分に比較することが大切です。
情報開示義務の負担
株式会社は会社法440条によって毎年の決算期ごとに財務状況を公表する決算公告が義務付けられています。
決算公告は次のいずれかの方法でおこなう必要があります。
- 官報
- 日刊新聞
- 自社や信用調査機関のWEBサイト
決算公告には手間がかかるうえ、多くの企業が利用している官報への掲載は7万円前後が発生してしまいます。
一部の株式会社は競合企業や取引先に経営状況を見られたくないという理由から決算公告をおこなっていません。
しかし、あくまでも法的義務であり、違反すると罰則によって100万円以下の過料を処されることになります。
株式会社の種類と特徴

株式会社と一口にいっても、実は以下の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
- 公開会社
- 非公開会社
- 持株会社
ここではそれぞれの特徴を解説していきます。
公開会社と非公開会社の特徴
公開会社とは、発行する株式の一部またはすべてに譲渡制限を設けていない株式会社のことで、株主は自由に株式の譲渡・売買ができます。
証券市場への上場には公開会社であることが一般的な要件となっており、多くの上場企業が公開会社です。ただし、公開会社=上場企業ではなく、上場企業でも非公開会社である場合があります。
非公開会社とは、発行する株式のすべてに譲渡制限を設けている株式会社であり、株主が株式を譲渡・売買する際には、取締役会などで必ず承認が必要です。
公開会社と非公開会社のメリット・デメリットは以下の通りです。
| 種類 | 公開会社 | 非公開会社 |
| メリット | ・外部から幅広く資金調達可能 ・間接的にコーポレートガバナンスを強化できる | ・株式を全てコントロールできることで意図しない買占めリスクを防げる ・取締役の任期を最長10年まで延長可能 ・株式の分散を防げる |
| デメリット | ・意図しない株式の買占めリスクがある ・取締役会や監査役のコストがかかる | ・資金調達の幅が狭まってしまう |
公開会社は株式の譲渡・売買に制限がないため、意図しない第三者に株式を買い占められ、経営権を奪われたり、役員報酬を大幅に引き下げられたりするリスクがあります。
一方、非公開会社は、株式を経営層が完全に管理できるため、買い占めのリスクを防げます。しかし、株式発行による資金調達が比較的難しいという欠点があります。
持株会社(ホールディングス)のメリットとデメリット
持株会社とは、傘下の会社を管理・支配する目的で株式を保有する会社のことです。法律上、株式を保有する会社を親会社、保有される会社を子会社と呼びます。
親会社は事業運営を子会社に任せることで、経営戦略の立案や意思決定に専念できます。一方、子会社は経営方針に従い、効率的に事業を展開できます。
持株会社には以下の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
【純粋持株会社】
子会社の経営管理をおこなうものの、自ら事業活動はおこなわない持株会社です。収益源は子会社の株式配当のみであることから複数の子会社を傘下に持つケースが多く、一般的に「〇〇ホールディングス」と称されます。
【事業持株会社】
子会社の株式を保有しながら、自らも事業を展開する持株会社です。収益は株式配当だけでなく、自社の事業からも得られます。
【金融持株会社】
銀行、証券、保険などの金融関連企業を統括する目的で設立された持株会社です。自身は事業活動をおこなわず、傘下の子会社の管理・運営に特化します。
持株会社のメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・役割分担により経営の効率が上がる ・社長や役員のポストが増え、リーダーの育成につながる ・子会社は外部株主の影響を受けにくく、意思決定のスピードが速くなる ・株式を集約しやすく、事業継承がスムーズになる ・税制上のメリットが得られる場合がある | ・子会社同士には支配関係がなく、連携が難しくなることがある ・株式保有などの維持コストが発生する ・子会社の成果が出るまでに時間がかかる |

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
株式会社と合同会社、どちらが適している?

法人を設立する場合、株式会社と合同会社のいずれかを選ぶ方が多い傾向にありますが、どちらを選べば良いのでしょうか。
ここでは事業の規模別に適している法人形態をご紹介します。
事業規模別の選び方
株式会社と合同会社のどちらが適しているのかは、起業を考えている方の目的によって大きく変わります。
以下の比較表を参考にどちらの法人形態が考えているビジネスにマッチするのかを十分に検討しましょう。
| 種類 | 株式会社 | 合同会社 |
| 向いている | ・将来的に会社の規模を拡大したい ・上場を目指している ・資金調達の選択肢を広げたい ・金融機関や取引先、顧客から信頼を得たい ・人材採用を有利に進めたい | ・設立費用やランニングコストを抑えたい ・会社の規模を大きくする予定がない ・自由度の高い経営をしたい ・意思決定を素早くおこないたい ・人材採用が有利にならなくても良い |
| 向いてない | ・設立費用やランニングコストを抑えたい ・スモールビジネスを維持したい | ・将来的に会社の規模を拡大したい ・上場を目指している ・社会的な信頼を得たい ・資金調達の選択肢を広げたい |
個人事業主と株式会社の違い

個人事業主とは、法人を設立せずにビジネスを展開する事業者のことです。開業手続きは税務署に開業届を提出するだけで済み、特に費用はかかりません。
一方、株式会社を設立する場合、10種類の書類を提出しなければならないほか、受理までに1ケ月前後かかることも珍しくありません。また、申請時に22万から25万円程度の費用が発生します。
個人事業主は手軽に開業できる一方、株式会社は設立に手間・コストがかかるものの、社会的信頼が高く、金融機関や取引先、顧客からの評価も得やすいという違いがあります。
個人事業主と株式会社の主な違いは以下の通りです。
| 法人形態 | 個人事業主 | 株式会社 |
| 手続き方法 | 開業届を税務署に提出する | 法務局と公証役場に申請書類を提出する |
| 申請時に発生する費用 | 0円 | 22万円から25万円前後 |
| 責任の範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
| 資金調達の手段 | ・金融機関などの融資 ・補助金や助成金 ・リースバック ・クラウドファンディング ・ファクタリング | ・株式の発行 ・社債の発行 ・金融機関などの融資 ・補助金や助成金 ・リースバック ・クラウドファンディング ・ファクタリング ・投資家やVCによる資金調達 |
| 社会的な信頼性 | 株式会社よりも低く、どんなに実績が高くても取引を断られる場合もある | 最も信頼されている法人形態で金融機関や取引先からの評価も高い |
| 税金 | ・所得税(累進課税) ・個人事業税 ・住民税 ・固定資産税 ・消費税 | ・法人税 ・法人住民税 ・法人事業税や特別法人事業税 ・地方法人税 ・消費税 ・事業所税 ・固定資産税 ・印紙税 ・自動車重量税(法人で自動車を所有する場合) |
| 社計保険料の負担 | 従業員5人以下の場合はなし | 従業員の社会保険料を負担する必要あり |
| 経費 | 事業のためにかかった費用 | ・事業のためにかかった費用 ・社宅の家賃 ・出張時の日当 ・生命保険料 ・役員報酬 |
| 会計・経理 | 確定申告 | 法人決算書・申告 |
ここでは個人事業主と株式会社の事業リスクの責任範囲や税金・会計処理の違いを詳しく解説していきます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
事業リスクの責任範囲
事業リスクの責任範囲は個人事業主が無限責任で、株式会社は有限責任となります。事業が失敗した場合、株式会社の方が背負う責任が小さくなります。
無限責任では、事業が負債を返済できない場合、事業主(代表者)が個人の財産で負債の全額を支払う義務を負います。
株式会社の場合は有限責任となり、出資者の責任の範囲は出資額以内に留まるため、それ以上の責任が問われることはなく、経営者の個人財産は保護されます。
税金・会計処理の違い
個人事業主の所得税は、所得に応じて税率が変わる累進課税が適用されますが、収入が少ない間は税負担が軽くなり、経営が安定しない時期でも負担を抑えられます。
法人の税率は、所得400万円以下の場合、法人税率が15%、事業税や住民税を含めた実効税率は約21%(21.366%)となります。
個人事業主の累進課税では所得が増えるほど税負担が大きくなり、一般的に年間所得が330万円を超えると法人より税率が高くなるため、このタイミングで法人化を検討する事業者が多くなります。
また個人事業主は赤字の場合、所得税や住民税が免除されるため、経営が厳しい時期の負担が軽減されます。その一方で、株式会社は赤字でも法人住民税を支払う必要があり、状況によっては負担が大きくなるリスクがあります。
確定申告の難易度にも違いがあります。個人事業主の確定申告は比較的簡単で、多くの事業主が自らおこなっています。しかし、株式会社の確定申告は専門性が高く、未経験者には難しいため、多くの企業が税理士など専門家に依頼しています。
株式会社の設立手続きの流れ

ここまで株式会社と合同会社・個人事業主の違いを説明しましたが、実際に株式会社を設立する場合、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。
株式会社の設立手続きを大まかに分けると、以下の通りです。
- 会社概要を決める
- 法人用の実印を作成
- 定款の作成
- 定款の認証を受ける
- 出資金(資本金)の払い込み
- 登記申請書類を作成後、法務局で申請
ここでは株式会社を設立する流れを説明していきます。
今回は簡易的な説明となりますので、詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
会社設立前の準備事項
株式会社を設立する第一歩として、まずは以下の会社概要を決めていきます。後述する定款にも掲載する内容であるため、慎重に考えることが大切です。
- 会社名
- 事業の目的
- 本社の所在地
- 資本金
- 会社の設立日
- 会計年度
- 役員・株主の構成
事業の目的は金融機関や取引先が法人の信頼性を確認する際の判断材料の1つになるため、説得力のある内容に仕上げることが大切です。
定款で定めた目的以外の事業は認められておらず、新たに始める場合は定款の変更手続き(3万円)が必須となります。
「変更手続きが面倒、最初から柔軟に事業展開できるようにしたい」と事業の範囲を広げすぎると何の会社か伝わりづらくなることで金融機関や取引先の信頼を損なうリスクがあります。迷った場合は専門家に相談することが賢明だといえます。
資本金(出資金)に関しては2006年の会社法改正によって資本金1円でも起業できるようになりました。社会的信頼の獲得や資金調達の面を考えると、事業規模に応じた適正な資本金を準備することが望ましいです。
法律上は資本金1円でも問題ないものの、資本金が極端に低いと金融機関や取引先から「企業体力がない」「経営難に陥っている」「貸し倒れリスクが高い」と警戒され、ビジネスチャンスを逃す可能性が高まります。そのため、資本金1円など事業規模に見合わない極端に安い資本金は避ける方が無難でしょう。
登記申請に必要な書類
株式会社を設立する場合、以下10種類の書類を法務局と公証役場に提出する必要があります。
準備には手間がかかり、申請から受理まで約1か月かかることもあるため、計画的に進めることが重要です。
| 提出書類 | 提出先 |
| ・発起人会議事録(発起人決定書) ・登記申請書 ・登録免許税納付用台紙 ・代表取締役の就任承諾書 ・取締役の就任承諾書 ・設立時取締役の印鑑証明書 ・資本金の払い込みを証明する書類 ・印鑑届出書 ・「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R | 法務局 |
| 定款 | 公証役場 |
記載漏れやミスがあると受理されず、設立が遅れる可能性があるため、申請前に内容を十分確認しましょう。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
設立後の初期手続き
株式会社設立後は、法人税の納付などを含む各種初期手続きをおこなう必要があります。手続き先は以下の通りです。
- 法務局
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 市町村役場
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 金融機関
任意の提出書類もありますが、必須書類が多いため、事業の開始準備と並行して期限内に提出することが重要です。
| 提出書類 | 要否 | 期限 | 提出先 |
| ・印鑑カード ・印鑑証明書 ・登記事項証明書 | 必須 | 法人設立後、直ちに提出 | 法務局 |
| 法人設立届出書 | 必須 | 会社の設立から2ヶ月以内 | 税務署 |
| 青色申告の承認申請書 | 必要な場合 | 法人設立から3ヶ月以内、もしくは最初の事業年度内のどちらか早い日の前日 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 役員報酬や給与を支払う場合、必須 | 給与支払事務所の開設から1ヶ月以内 | |
| ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ・適格請求書発行事業者の登録申請書 | 必要な場合 | 任意 | |
| 法人設立届出書 | 必須 | 市町村によって期限が異なる | 市町村役場 |
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 必須 | 会社設立から5日以内 | 年金事務所 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 必要な場合 | 被保険者の資格を取得後、5日以内 | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 必要な場合 | 被保険者に扶養がいる場合、直ちに提出 | |
| 労働保険保険関係成立届 | 必要な場合 | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 | 労働基準監督署 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇用してから50日以内 | ||
| 就業規則(変更)届 | 常時雇用の従業員が10人以上いる場合、直ちに提出 | ||
| 適用事業報告書 | 従業員を雇用した場合、直ちに提出 | ||
| 雇用保険適用事業所設置届 | 必要な場合 | 適用事業所になった日の翌日から10日以内 | ハローワーク |
| 雇用保険被保険者資格届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 | ||
| 法人口座新規開設届 | 任意 | 法人口座開設時 | 金融機関 |
株式会社設立の費用と期間
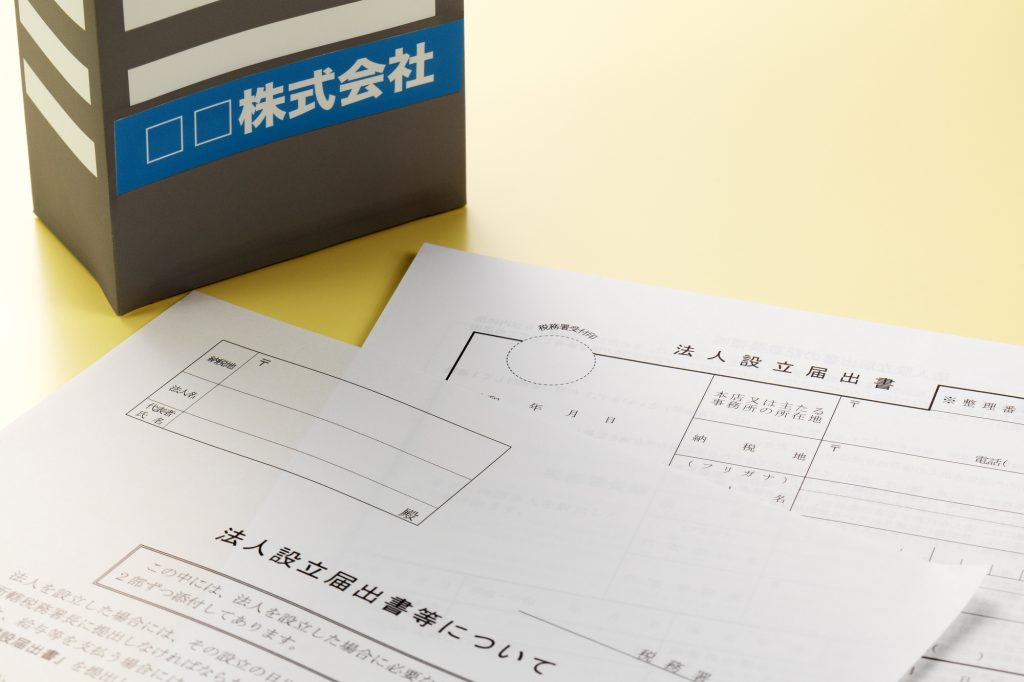
初めて株式会社を設立する場合、設立までにどれぐらいの費用と期間がかかるのか気になるのではないでしょうか。
ここでは株式会社を設立するまでに発生する費用と期間の目安を紹介していきます。
設立時にかかる費用の内訳
前述したように株式会社は、設立の手続きによって22万円から25万円前後の費用が発生します。
設立費用の内訳は以下の通りです。
| 収入印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
| 謄本の発行手数料 | 約2,000円 |
| 定款の認証手数料 | 資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 |
| 登録免除税 | 150,000円もしくは資本金×0.7%のどちらか高い方 |
| 合計 | 22万円から25万円前後 |
設立完了までの所要期間
株式会社の設立には約2ヶ月から3ヶ月かかるため、計画的に進めることが重要です。主なスケジュールは以下の通りです。
- 事前準備:1ヶ月前後
- 定款の作成・認証:1週間前後
- 資本金の確保・払い込み:1週間前後
- 書類提出による申請から完了:2週間から1ヶ月前後
申請から完了までは最短2週間ですが、1ヶ月かかることも珍しくないため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
また上記は設立までのスケジュールであり、設立後には前述した初期手続きが必要です。期限に間に合わない事態を防ぐために事前にスケジュールをしっかり立てておきましょう。
費用を抑えるためのポイント
株式会社の設立には22万円から25万円の手続き費用がかかるほか、事業規模に応じた資本金も必要です。そのため、できるだけ費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。
株式会社で費用を抑えるためには、主に以下のような工夫をすると良いでしょう。
- 条件を満たす補助金・助成金に申請する
- 中古品やリース品を利用する
- レンタルオフィス・コワーキングスペースを使う
- アウトソーシング(外注委託)を活用する
- リモートワークを導入するなど
補助金・助成金は要件を満たす必要があるものの、原則返済義務がないため、創業初期の資金負担を大きく軽減できます。
またレンタルオフィス・コワーキングスペースの利用やリモートワークの導入をすることで、毎月の大きな負担になりがちなテナント賃料や電気代などのランニングコストを削減できます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
株式会社は国内で最も一般的な法人形態であり、多くの起業家がそのメリットを期待して設立しています。
その一方で設立費用が22万円から25万円程度かかるなど、決して無視できないデメリットも存在します。
株式会社には向き不向きがあるため、展開するビジネスと株式会社のメリット・デメリットを照らし合わせて、最適な法人形態を選ぶことが重要です。
また、異業種からの参入や初めての起業で安定した経営を目指す場合は、フランチャイズへの加盟も選択肢の1つです。
フランチャイズでは、業界に精通した本部が経営ノウハウを提供し、集客などをサポートするため、専門知識がなくても成功しやすい傾向にあります。
GLUGでは福祉・飲食の領域に特化して開業から運営までトータルでサポートしています。









