事業で使用する建物や車両など、多くの固定資産は時間の経過や使用によって価値が減少していきますが、耐用年数に応じて取得コストを分割する減価償却を活用することで利益や納めるべき税金を正確に把握できます。
会計では必須の概念の1つですが、どのように考えれば良いのか分からない方も中にはいるのではないでしょうか。
そこで今回は減価償却の基礎知識や対象・対象外の資産、減価償却の計算方法などを解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
減価償却とは?
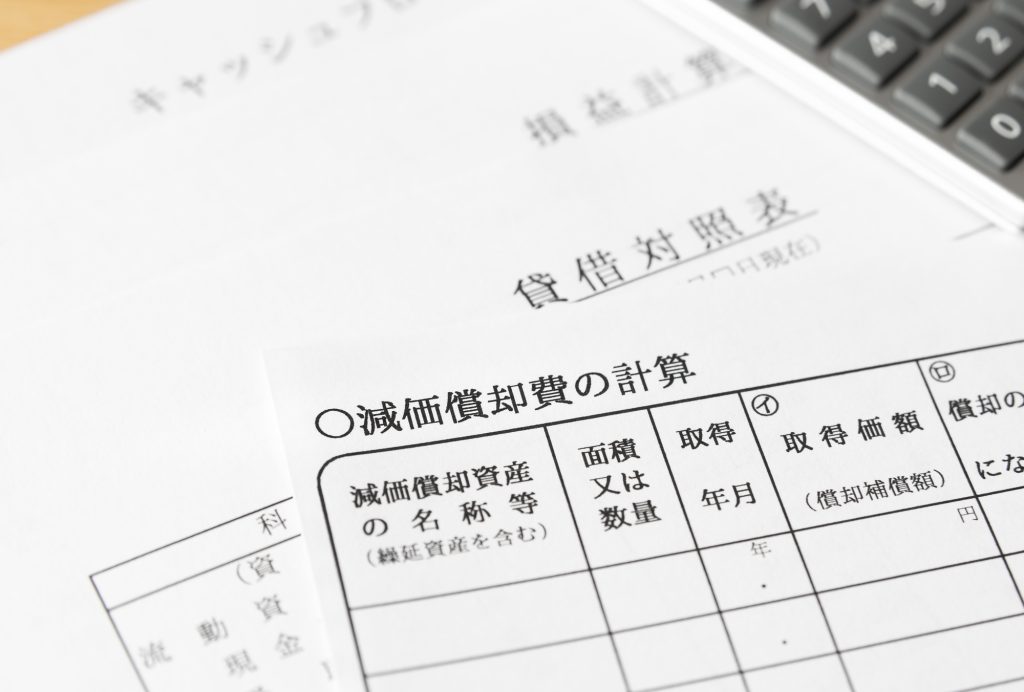
減価償却とは、建物や機械などの固定資産の取得費用をその使用期間に応じて、各会計期間に分割して計上する会計処理です。
減価償却をおこなうことで資産の価値の減少を適切に反映し、企業の利益を正確に把握できます。
ここでは国税庁の「No.2100 減価償却のあらまし」に基づいて、減価償却の概要を説明していきます。
なぜ減価償却をするのか
減価償却をおこなう主な目的は、固定資産の取得費用を使用期間に応じて適切に費用配分し、企業の損益計算を正確におこなうことです。
その他にも主に以下4つのメリットがあり、多くの企業が活用しています。
【①資金繰りの安定】
減価償却費は現金支出を伴わないため、資金の流出を抑えながら内部留保を蓄積し、設備投資の原資確保にも役立ちます。
【②節税効果】
減価償却費の計上により課税所得が減少し、法人税などの税負担を軽減できます。
【③財務状況の健全化】
資産の価値減少を帳簿に反映させることで、財務諸表の信頼性が向上し、投資家や金融機関からの評価が高まります。
【④自己金融の促進】
減価償却費に相当する資金が社内に残るため、外部の資金調達に頼らずに再投資がおこなえます。
減価償却をしないとどうなる?
減価償却をおこなわない場合、個人事業主・法人のいずれの場合も税務上および財務上のデメリットが生じる可能性があります。
ここでは個人事業主・法人それぞれの減価償却をしないデメリットを紹介していきます。
個人事業主の場合
個人事業主におけるデメリットは以下の通りです。
【経費計上の機会損失】
減価償却をおこなわない場合、その資産の取得費用を必要経費として計上できず、課税所得が増加し、税負担が重くなってしまいます。
一度計上を逃すと、後からの修正が難しいため、注意しなければなりません。
【経営判断のミスを招く】
減価償却をおこなわないと資産の使用による費用が反映されず、実際よりも利益が多く見えることがあります。これによって経営判断を誤るリスクがあります。
法人の場合
法人におけるデメリットは、以下の通りです。
【税負担の増加】
減価償却費を計上しない場合、課税所得が増加し、法人税の負担が重くなります。特に高額な資産を未処理のまま放置すると、税務上の不利益を受けるおそれがあります。
【財務諸表の信頼性低下】
資産の減価が適切に反映されないことで、財務諸表が実態とかけ離れた内容になり、金融機関や投資家の信頼を損なうおそれがあります。
【融資審査への影響】
減価償却を適切におこなっていない場合、利益操作の疑いを持たれ、金融機関から融資を拒否されるおそれがあります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
減価償却ができる資産とできない資産

どのような資産でも減価償却ができるとは限らず、減価償却ができる資産には条件があります。
ここでは減価償却ができる資産とできない資産の条件や例を解説していきます。
減価償却ができる資産
減価償却の対象となる資産は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業活動に使用される資産であること。
- 取得価額が10万円以上であること
- 使用可能期間が1年以上であること
- 時間の経過や使用によって価値が減少する資産であること
減価償却の対象となる主な資産は、以下の通りです。
| 資産の種類 | 主な例 |
| 建物 | 事務所、店舗、工場、倉庫、住宅など |
| 建物附属設備 | 給排水設備、電気設備、冷暖房設備、エレベーターなど |
| 構築物 | 用水路、貯水槽、サイロ、果樹棚、農業用井戸など |
| 機械および装置 | 食品製造設備、印刷機、旋盤、ボール盤、梱包機など |
| 車両および運搬具 | 普通自動車、トラック、フォークリフト、自転車、リヤカーなど |
| 工具、器具および備品 | 測定工具、事務机、椅子、パソコン、コピー機、冷蔵庫など |
| 無形固定資産 | ソフトウェア、特許権、商標権など |
減価償却ができない資産
すべての資産が減価償却の対象となるわけではありません。減価償却の対象とならない資産の条件は以下の通りです。
- 個人所有など事業活動で使用されていない資産
- 時間の経過や使用によって価値が減少しない資産
- 建設中や未稼働などによってまだ使用を開始していない資産
- 電話加入権など無形固定資産のうち償却の対象外とされるもの
| 資産の種類 | 主な例 |
| 土地 | 事業用地、駐車場用地など |
| 無形固定資産 | 電話加入権、借地権など |
| 美術品・骨董品 | 書画、彫刻、アンティーク家具など |
| 建設中の資産 | 建設中の建物、設備など |
| 未稼働の資産 | 稼働休止中の機械、使用していない設備など |
| 事業外の資産 | 個人使用の車両、趣味で所有する資産など |
資産の取得時には、その資産が減価償却の対象となるかどうかを確認し、適切な会計処理をおこなうようにしましょう。
減価償却の行い方

減価償却をどのようにおこなえば良いのか分からずに困っている方も中にはいるのではないでしょうか。
ここでは減価償却の主なおこない方を紹介していきます。
減価償却をするタイミング
減価償却は、固定資産を購入した日ではなく、事業で実際に使用を開始した日(事業供用開始日)からおこないます。
例えば機械設備を購入しても、実際に設置や試運転を経て稼働を始めた日が減価償却の開始日となります。
年度の途中で使用を開始した場合、その年度の減価償却費は月割りで計算します。
耐用年数を確認する
耐用年数は、固定資産の取得費用を減価償却する期間を定めるもので、資産の種類や使用目的によって異なります。
正確な耐用年数を確認するには、国税庁が公開している「主な減価償却資産の耐用年数表」を参照すると良いでしょう。
この表では建物や機械、車両、器具備品などの資産ごとに、構造や用途に応じた耐用年数が定められています。
取得価額を決める
取得価額は、減価償却をおこなう際の基礎となる金額であり、資産の購入価格だけでなく、資産を使用可能な状態にするまでに発生したすべての費用を含みます。
具体的には、主に以下のような費用を取得価額に含めて計算します。
- 購入代金
- 運搬費
- 試運転費
- 購入に伴う税金
- 仲介手数料など
ただし、消費税は原則として取得価額に含めず、仕入税額控除の対象とされます。
また資産取得時に割引や値引きがあった場合は、それを差し引いた実際の支出額を取得価額とします。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
減価償却の計算方法

減価償却の計算方法には様々な種類がありますが、企業では一般的に以下3つの計算方法が用いられています。
- 定額法
- 定率法
- 生産高比例法
それぞれ詳しく解説していきます。
定額法
定額法では、毎年同じ金額を減価償却費として計上します。計算式は以下の通りです。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
償却率は耐用年数に応じて定められており、例えば耐用年数が5年の場合、償却率は0.200(20%)となります。
▼計算例(取得価額100万円・耐用年数5年・償却率0.200の場合)
- 1年目:1,000,000円 × 0.200 = 200,000円
- 2年目:1,000,000円 × 0.200 = 200,000円
- 3年目:1,000,000円 × 0.200 = 200,000円
- 4年目:1,000,000円 × 0.200 = 200,000円
- 5年目:1,000,000円 × 0.200 = 199,999円
上記のように最終年は資産が存在することを示すために1円を残し、減価償却費を199,999円とします。
定額法は毎年の減価償却費が一定であるため、計算が簡単で資金計画が立てやすいというメリットがあります。
その一方で初年度の減価償却費が少ないため、初期の節税効果は限定的となります。
定率法
減価償却の定率法は、資産の未償却残高に一定の償却率を掛けて毎期の減価償却費を計算する方法です。
初年度の償却費が最も大きく、以降は年々減少していきます。ただし、償却額が一定の水準(償却保証額)を下回ると、計算方法が変更されます。
計算式は以下の通りです。
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
未償却残高とは、取得価額からこれまでの減価償却累計額を差し引いた金額のことです。
▼計算例(取得価額100万円・耐用年数5年・償却率が0.4の場合)
- 1年目: 1,000,000円 × 0.4 = 400,000円
- 2年目: (1,000,000円 – 400,000円) × 0.4 = 240,000円
- 3年目: (1,000,000円 – 400,000円 – 240,000円) × 0.4 = 144,000円
- 4年目: (1,000,000円 – 400,000円 – 240,000円 – 144,000円) × 0.4 = 86,400円
- 5年目: (1,000,000円 – 400,000円 – 240,000円 – 144,000円 – 86,400円) × 0.4 = 51,839円
定率法の特徴は、初期の償却費が大きいため、早期に費用を計上できる点にあります。なお、最終年度は定額法と同様に資産の存在を示すため、1円を残します。
生産高比例法
生産高比例法は、資産の使用の度合いに応じて減価償却費を計上する方法で、特に鉱業用設備など、総使用量を正確に見積もれる資産に適しています。
この計算式は資産の価値の減少をより正確に反映させることができます。計算式は以下の通りです。
減価償却費 = 取得価額 ÷ 見積総使用量 × 当期使用量
取得価額を見積総使用量で割って1単位あたりの減価償却費を算出し、それに当期の使用量を掛けて減価償却費を求めます。
▼計算例(取得価額500万円の掘削設備・見積総掘削量10万トン・当期の掘削量4,000トンの場合)
- 1単位あたりの減価償却費: 500万円 ÷ 10万トン = 50円/トン
- 当期の減価償却費: 50円/トン × 4,000トン = 20万円
減価償却の仕訳方法

減価償却の仕訳方法には、直接法と間接法の2種類があります。
ここでは直接法と間接法の仕訳方法や処分時・売却時の計算を紹介していきます。
直接法
直接法は資産の帳簿価額を直接減額する方法で、資産の現在価値を明確に把握できるというメリットがあります。
仕訳の例は以下の通りです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 減価償却費 | 10万円 | 工具器具備品 | 10万円 |
直接法によって工具器具備品の帳簿価額が直接10万円減少し、同額が減価償却費として費用計上されます。
ただし、直接法では帳簿上に取得原価や減価償却累計額が表示されないため、資産の取得時期や償却状況の把握が難しくなるというデメリットがあります。
このデメリットを回避するために、直接法を使う場合は事前に注記しておくと良いでしょう。
間接法
減価償却の間接法では、減価償却費を「減価償却累計額」として記録し、固定資産の帳簿価額を間接的に減少させます。これにより、取得原価と減価償却累計額を明確に把握できます。
仕訳の例は以下の通りです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 減価償却費 | 100,000円 | 減価償却累計額 | 100,000円 |
処分時の仕訳
固定資産の処分時の仕訳は、減価償却の方法によって異なります。直接法と間接法それぞれの仕訳例は以下の通りです。
▼直接法による処分時の仕訳例
(取得原価100万円の機械装置を減価償却費20万円で処理し、帳簿価額80万円となった時点で除却する場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 固定資産除却損 | 80万円 | 機械装置 | 80万円 |
▼間接法による処分時の仕訳例
(取得原価100万円、減価償却累計額20万円の機械装置を除却する場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 減価償却累計額 | 20万円 | 機械装置 | 100万円 |
| 固定資産除却損 | 80万円 | ||
売却時の仕訳
固定資産を売却する際、企業では一般的に間接法が用いられています。仕訳例は以下の通りです。
▼間接法による売却時の仕訳例
(取得原価100万円、減価償却累計額40万円の車両を70万円で売却し、10万円の売却益が発生した場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 70万円 | 車両 | 100万円 |
| 減価償却累計額 | 40万円 | 車両売却益 | 10万円 |
固定資産の売却においては、取得原価の追跡が難しくなるため、企業では一般的に直接法ではなく間接法が用いられます。
その一方で個人事業主や小規模事業者の場合、仕訳を簡易的におこなうために、稀に直接法で売却時の仕訳をおこなう場合があります。仕訳例は以下の通りです。
▼間接法による売却時の仕訳例
(取得原価100万円の車両を減価償却累計額40万円(帳簿価額60万円)で管理し、70万円で売却した場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 70万円 | 車両 | 60万円 |
| 車両売却益 | 10万円 | ||
直接法では仕組み上、詳細の確認が難しくなるため、別途で固定資産台帳などに記録するようにしましょう。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
決算書への記載方法

ここでは以下の決算書で、直接法や間接法でどのように記載すれば良いのか紹介していきます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
貸借対照表
間接法では、固定資産の取得原価を貸借対照表の資産の部に記載し、減価償却累計額を控除項目として表示します。
これによって取得原価と減価償却累計額が明確に区分され、資産の帳簿価額(未償却残高)を把握しやすくなります。
仕訳では、借方に「減価償却費」、貸方に「減価償却累計額」を記録します。間接法は、有形固定資産に適しており、企業において広く利用されています。
直接法では、減価償却費を固定資産勘定から直接控除し、帳簿価額を減少させます。
貸借対照表には、減価償却後の帳簿価額のみが表示され、取得原価や減価償却累計額は明示されません。仕訳は、借方に「減価償却費」、貸方に「固定資産」を記録します。
直接法は無形固定資産に適しており、現在の資産価値を即座に把握できるというメリットがあるものの、取得原価などの詳細の把握が困難になることから注記しておく必要があります。
損益計算書
損益計算書では、減価償却費は「販売費及び一般管理費」の一部として記載します。これは、固定資産の使用による価値の減少を費用として計上し、収益と費用の関係を明確にするためです。
減価償却費の計算は、取得価額、耐用年数、残存価額、用いる償却方法(定額法、定率法など)に基づきます。
仕訳では、借方に「減価償却費」、貸方に「減価償却累計額」(間接法)または「固定資産」(直接法)を記録します。
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書では、減価償却費は「営業活動のキャッシュフロー」の項目に記載します。
減価償却費は現金の支出を伴わない費用であるため、損益計算書で減少した利益を加算し、実際の現金収支を調整します。
一般的に使用される間接法では、税引前当期純利益に減価償却費を加算して営業キャッシュフローを算出します。
一方、直接法では項目ごとに現金収支を明示しますが、作成の手間が大きいため、実務ではあまり用いられていません。ただし、間接法・直接法いずれを用いても、キャッシュフローの合計金額は変わりません。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
減価償却は決算書と密接に関係しており、適切な経営判断をするうえでも重要度の高い会計処理の1つです。
減価償却は正確におこなう必要がありますが、所有する固定資産の数に比例して会計処理が複雑になるため、会計ソフトの導入や税理士などの専門家への依頼によって負担を少しでも軽減すると良いでしょう。
これから起業を目指している方や異業種参入を考えている方は、フランチャイズへの加盟も1つの手です。
フランチャイズでは、業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、集客や営業、仕入れなどをサポートしているため、未経験の場合でも最初から安定した経営をおこないやすい傾向にあります。









