少子高齢化による人材不足やグローバル化によって、多様性を意味するダイバーシティが多くの企業で注目を浴びていますが、どのように取り組めば良いのか分からない方もなかにはいるのではないでしょうか。
ここではダイバーシティの基礎知識や歴史、インクルージョンとの違い、注目されている理由、主な取り組み事例、実践方法などを網羅的に解説していきます。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
ダイバーシティとは?

ダイバーシティは、人種・性別・年齢・国籍・宗教・価値観などの多様性を認め、尊重する考え方であり、近年では多くの企業で取り入れられています。
ここではダイバーシティの概要を説明していきます。
ダイバーシティの語源・歴史
ダイバーシティ(Diversity)の語源は、ラテン語の「diversus(異なる、さまざまな)」に由来し、多様性や違いの尊重を意味します。
この概念は、人種や性別にとどまらず、年齢、宗教、文化、価値観、働き方など、さまざまな違いを受け入れ、活かす考え方として発展してきました。
歴史的には、1950年代から1960年代のアメリカで起きたアフリカ系アメリカ人の公民権運動が大きな転機となりました。
この社会運動を通じて、雇用や教育の機会均等、差別の撤廃の重要性が徐々に認識され、企業や教育機関でも多様な人々を受け入れる姿勢が求められるようになりました。
その後、1980年代以降には企業経営でも「ダイバーシティ・マネジメント」という概念が生まれ、組織の創造性や競争力を高める戦略として注目されるようになりました。
現在では、ダイバーシティはCSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも重視され、持続可能な成長を目指す上で不可欠な要素となっています。
ダイバーシティとインクルージョンの違いは?
ダイバーシティは、人種、性別、年齢、宗教、価値観などの違いを尊重し、多様な人材を受け入れる考え方です。
一方、インクルージョンは、受け入れた多様な人々が組織内で公平に扱われ、活躍できる環境を整えることを指します。
近年では、これらを1つの概念として「D&I(Diversity & Inclusion)」と表現し、単なる多様性の受容にとどまらず、実際に活用する体制づくりが重視されています。
D&Iに取り組む企業は、性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、幅広い人材を惹きつけることができるほか、多角的な視点やアイデアが生まれやすくなり、革新的な商品・サービスの開発にもつながります。
またD&Iを重視している企業では、従業員が「自分らしく働ける」と感じやすく、定着率やエンゲージメントの向上も期待できます。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
ダイバーシティには2種類ある
ダイバーシティには2種類があり、効果を最大限に生かすために両方のダイバーシティに取り組む必要があります。
ここでは2種類のダイバーシティを解説していきます。
表層的ダイバーシティ
表層的ダイバーシティとは、外見や公的な属性など、目に見える違いに基づく多様性を指します。
組織における多様性の入り口として重視されますが、これだけでは真の包摂的な環境は築けないため、価値観や経験といった深層的ダイバーシティと併せて考えることが重要です。
主な例は以下の通りです。
- 人種・民族
- 性別
- 年齢
- 国籍
- 障がいの有無
- 宗教的服装や髪型などの外見的特徴
深層的ダイバーシティ
深層的ダイバーシティとは、外見では判断できない、個人の内面に関わる多様性を指します。
表層的ダイバーシティと異なり、価値観や思考、経験の違いに着目するもので、組織の創造性や問題解決力の向上に貢献します。
主な例は以下の通りです。
- 思考や価値観の違い
- 教育や職歴などの経験
- 仕事への向き合い方
- 性格やコミュニケーションスタイル
- 宗教・信条・人生観など
深層的ダイバーシティを尊重することで、見た目にとらわれない多様性を活かし、より包括的な組織文化を築くことができます。
ダイバーシティが注目されている理由・背景
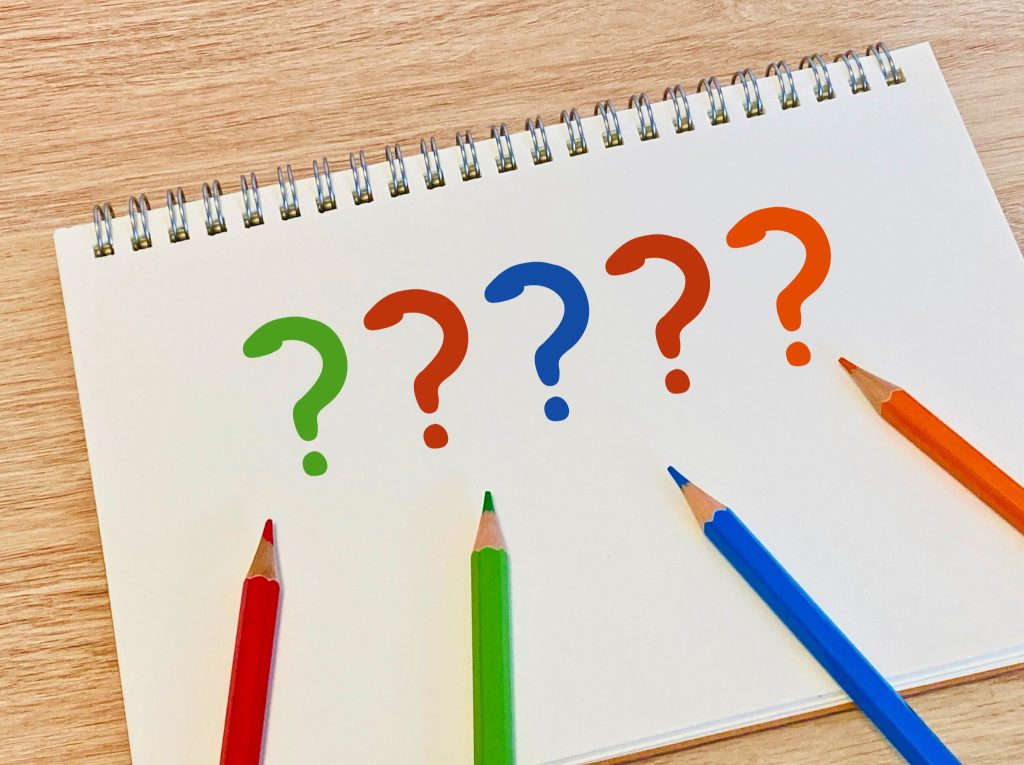
近年は多くの企業でダイバーシティが重要視されるようになっていますが、なぜ注目されているのでしょうか。
ここではダイバーシティが注目されている主な理由・背景を紹介していきます。
【1. グローバル化の進展】
国境を越えた人材交流が活発になり、異なる文化や価値観を持つ人々と働く機会が増えています。多様性への理解と受容は、国際競争力を高める上で不可欠です。
【2. 労働力不足への対応】
少子高齢化や人手不足が深刻化するなか、主婦、高齢者、外国人、障がい者など、多様な人材の活用が求められています。こうした人材を受け入れることで、柔軟で強い組織づくりに寄与します。
【3. イノベーション創出】
多様な背景を持つ人々の視点や発想が交わることで、新しいアイデアや価値が生まれやすくなります。ダイバーシティは創造性の源であり、企業が成長する原動力として注目されています。
これらの背景から、ダイバーシティは持続可能な社会と経営の実現に不可欠な要素とされています。
経済産業省の取り組み:ダイバーシティ2.0
経済産業省は、企業が少子高齢化が進むなかで人材を確保し、多様化する市場ニーズやリスクへの対応力を高めるためにはダイバーシティが不可欠であり、日本経済の持続的成長にとって重要だとしています。
経済産業省は「企業に求められる具体的アクション(ダイバーシティ2.0行動ガイドライン)新旧対照表」で企業がダイバーシティに取り組むためのヒントを提示しています。
同ガイドラインでは、多様性を受け入れるだけでなく、それを「価値創造の源泉」として活用し、経営成果につなげることを求めています。
主な取り組み内容は以下の通りです。
【戦略的ダイバーシティ推進】
経営層が主体となってダイバーシティを推進し、KPIの設定や人事制度の見直しなどを通じて、組織全体で取り組む体制を構築します。
【制度・法改正の支援】
女性活躍推進法、障害者雇用促進法、育児・介護休業法などの法制度の整備を通じて、誰もが働きやすい環境づくりを後押しします。
【LGBTQや外国人労働者への配慮】
性的マイノリティや国籍などに関する配慮を明文化し、多様な価値観を尊重するガイドラインや事例を公開しています。
【新・ダイバーシティ経営企業100選などの表彰制度】
多様性を活かして成果を上げている企業を選定・発信し、他企業の参考モデルとすることで全国的な普及を促進します。
これらの取り組みを通じて、ダイバーシティは単なる社会的配慮ではなく、企業の価値創造に直結する経営資源として位置づけられています。経済産業省は今後も企業のD&I推進を積極的に支援していくとしています。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
厚生労働省の取り組み
厚生労働省は、「ダイバーシティ&インクルージョンの時代に 治療と仕事の両立で自分らしく働く」で発表しているように、すべての人が自分らしく働ける社会の実現を目指し、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進に取り組んでいます。
以下のように施策は、法制度の整備から企業支援、啓発活動まで多岐にわたります。
【女性活躍推進法の改正】
2022年7月の改正により、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して「男女の賃金差」の情報公表が義務化され、企業の透明性向上と格差是正が期待されています。
【障害者雇用促進法の改正】
2022年の改正では、障がい者の職業能力の開発・向上が事業主の責務として明文化されました。週10時間から20時間の勤務が可能な重度障がい者や難病患者も雇用率算定の対象となりました。
【性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する法律の施行】
2023年6月に施行されたこの法律は、性的マイノリティへの理解促進を目的とし、基本計画の策定などを通じて寛容な社会の実現を目指します。
【職場におけるダイバーシティ推進事業】
多様な人材が活躍できる職場環境の整備を支援するために企業の取組事例集を作成し、啓発活動を実施しています。
【治療と仕事の両立支援】
病気を持つ労働者が安心して働き続けられるように「トライアングル型支援」や両立支援コーディネーターの配置など、具体的な支援策を展開しています。
【ハラスメント防止指針の整備】
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止に関する指針を策定し、事業主に対して雇用管理上の措置義務を課しています。
【相談窓口の設置】
労働者が安心して相談できるように総合労働相談コーナーや電話相談窓口を設置し、職場でのトラブルや悩みに対応しています。
厚生労働省の上記のような取り組みは、単なる法令遵守にとどまらず、多様な人材が能力を発揮し、安心して働ける職場環境の実現を目指すものです。
ダイバーシティ経営とは

ダイバーシティ経営とは、多様な人材を受け入れつつ、活躍できる環境を整備し、持続的な成長と競争力の向上を目指す経営手法のことです。
ここではダイバーシティ経営の主なメリットと課題を紹介していきます。
メリット
ダイバーシティ経営は、多様な人材を活かすことで企業の競争力や柔軟性を高める経営手法です。
主なメリットは以下の通りです。
【イノベーションの創出】
異なる文化や価値観を持つ人材が交わることで、多角的な視点が生まれ、新商品や新サービスの開発につながります。
例えばグローバル市場向けの商品開発では、外国人社員の意見が重要なヒントになることがあります。
【優秀な人材の確保・定着】
性別や年齢、国籍などを問わない公平な環境は、幅広い人材からの応募を促し、離職率の低下にもつながります。
多様性を尊重する企業は「働きやすい」と評価され、求職者から選ばれやすくなります。
【組織のレジリエンス向上】
多様な背景を持つ人材が異なる視点や対処法を持ち寄ることで、変化への対応力が高まり、組織の柔軟性と持続性が向上します。
これらのメリットから、ダイバーシティ経営は単なる人材戦略ではなく、企業価値向上の鍵となります。
課題
ダイバーシティ経営は多くのメリットがある一方で、適切に運用しなければ逆効果になることもあります。
主な課題は以下の通りです。
【価値観の衝突】
異なる文化や考え方を持つ人材が集まることで、意思疎通や判断にズレが生じ、チーム内の摩擦が起こる可能性があります。
例えば指示の出し方や報連相に対する認識の違いがトラブルの原因になることがあります。
【インクルージョンの不足】
多様性を確保しても、それぞれの人材が活躍できるインクルージョン(環境)が整っていなければ、能力を十分に発揮できません。形式だけの多様化では、逆に従業員の疎外感を招くおそれがあります。
【管理職の意識とスキル不足】
多様な人材をマネジメントするためには、深い理解力と柔軟な対応力が必要です。特に中間管理職に対する研修や支援体制が不足すると、ダイバーシティが現場で機能しません。
これらの課題を克服するには、全社的な意識改革と制度設計、継続的な教育が不可欠です。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
ダイバーシティ経営の企業取り組み例

企業はどのようなダイバーシティ経営をおこなっているのでしょうか。
ここでは経済産業省の「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム 100選ベストプラクティス集」に基づいて、ダイバーシティ経営で大きな成功を収めた企業の事例を紹介していきます。
大橋運輸株式会社
大橋運輸株式会社は、1954年に愛知県瀬戸市で設立され、陶器輸送を主な事業として発展してきました。しかし1990年代に大手運送会社の下請に転換して以来、価格競争の激化や人手不足、長時間労働といった課題が慢性化していきました。
こうした状況を受け、同社は2010年から「社員一人ひとりが働きやすく、能力を発揮できる会社を目指す」という方針のもと、ダイバーシティ経営に取り組み始めました。
同社でおこなっている取り組みは主に以下の通りです。
- 高齢者の雇用延長
- 外国人やLGBTQ社員の採用
- 書類選考の撤廃と複数回の面接実施
- 面接段階での職場見学・体験
- 社内管理栄養士による健康管理
- 外国人社員向けの日本語教室や生活サポート
- 障がいのある社員への業務サポート
- ジョブローテーションによる繁忙期の部署の負担軽減
- 選択制による週休3日や短時間労働の導入など
上記のような取り組みの結果、女性社員比率は6%から20%に上昇し、女性管理職数も全体の半数を占めています。
また外国人社員が8名、障がいのある社員4人が正社員として勤務しており、複数の部署でLGBTQ社員が活躍しています。
このように多様な人材を確保していることで主に以下のような成果を出すことに成功しています。
- LGBTQ当事者からの生前整理・遺品整理の依頼が増え、5年間で売上が3倍に
- 家財を輸出する国の出身者である外国人社員が対応することで高利益を確保など
横関油脂工業株式会社
1948年に創業した油脂メーカーの横関油脂工業株式会社は、小回りのきく生産ラインを強みとして、大手では難しい業務を受注することで安定した経営をおこなってきました。
しかし、現状維持では将来の成長が見込めないとの危機感から、2011年に大きな方針転換を図りました。
従来は対応していなかった新規開発品の試作やオーダー品の受注、さらには海外での原料調達や市場開拓にも着手することにしましたが、実現するには多様な人材の確保が不可欠であり、同社はダイバーシティ経営に取り組むことにしました。
それまで同社では新卒採用や異動・配置転換をほとんどおこなっておらず、人材の流動性に乏しい状況でしたが、方針転換後は、地元での新卒採用や女性、障がい者の積極採用に取り組むようになりました。
また多様な人材を確保するだけでなく、以下のようにダイバーシティ経営の一環として社員が働きやすい環境を整備しています。
- 資格取得も評価基準に追加
- 定年後の継続雇用・継続雇用後の再々雇用制度の導入
- 障がいのある社員の通院に配慮した勤務形態の導入
- 主治医と連携した障がい者支援環境の構築
- 60歳以上のシニア社員と新入社員のペアによる技術継承の促進
- 長時間労働を防ぐためのシフト勤務やテレワーク勤務の制度化など
こうした取り組みの結果、多様な人材同士の異なる価値観や自由な発想が刺激となり、主に以下のような成果を出しています。
- 社員数が67%まで増加(64人から107人に増加)
- 女性社員の比率が47%まで高まり、育児休業後の復職率は100%を記録
- 若手社員の活躍でマネジメントの平均年齢が47.8歳から39.1歳まで低下
- 新規依頼が増えたことで年間生産量が45%増加
- 年商が8年で27億円から42億円に拡大
- 2016年に始めた新規事業の売上がわずか3年で1億5,000円を記録
- 海外の現地代理店3社の新規開拓に成功など
東和組立株式会社
1969年に設立された東和組立株式会社は、自動車用油圧緩衝部品の組立、塗装、梱包の一貫生産をおこなっています。
同社では1971年から障がいのある人材や外国人を積極的に採用しており、2009年のリーマンショックで外国人派遣社員を苦渋の決断で大量解雇したことを教訓に、2013年から性別・国籍・障がいの有無にかかわらずに正社員雇用を前提に長く働ける環境を整備しています。
また受注増と人手不足が深刻化するなかで、「社員全てが安心して働き続けられ、当社で働くことが幸せに思える企業を目指す」を基本方針として、本格的にダイバーシティに取り組むようになりました。
- 画像判断装置やバーコード識別装置の導入で熟練工ではない外国人やシニア、障がいを持つ社員でも検査工程を可能に
- 改造台車や昇降テーブルを活用し、体格・体力差による作業偏在の解消と業務範囲の拡大
- 知的障がいのある社員に光の点灯で指示を分かりやすく伝えるアクションボードの導入
- 聴覚障がいを持つ社員のために声を文字に変換するスピーチキャンパスを導入
- スマートグラスを通してマニュアルを見ながら作業訓練ができる仕組みの導入
- 正社員・パート社員を切り替えらえる制度の導入で結婚・出産による離職を防止
- 障がいのある社員が希望に応じて雇用形態を柔軟に変更可能に
- 70歳以降も就業できるように制度を変更など
IT化による業務効率化や多様な人材の確保、働きやすさの追求をした結果、以下のように大きな成功を収められました。
- 社員の生産能力が20%向上
- 納期の遵守率が大きく改善し、目標の90%を達成
- 取引先の評価指数が業務改善レベルの0.8%から優良企業レベルの3.6%に向上
- 障がいを持つ社員の定着率がわずか3年で約90%に向上
- 地元高校や外国人コミュニティーから高く評価され、求職者が増加
- 経営が評価され「2020年中部IT経営力大賞優秀賞」「第1回日本でいちばん大切にしたい会社特別賞」を受賞など
株式会社足立商事
2016年に設立された株式会社足立商事では、当初は卸売業・物流業が中心でしたが、自社でインターネットショップを開設し、生活雑貨をメインとした小売直販事業へ拡大しました。
その後、経営者の地元である兵庫県丹波市に本社移転・工場を備えた自社倉庫を整備しましたが、同地域では過疎化が進んでおり、事業撤退や廃業によって就労意欲があっても働く場がない主婦や高齢者が増えているという地域の課題を発見しました。
そこで同社は主に以下のような取り組みによって、多様な人材の確保と雇用機会の拡大を図りました。
- 1日1時間からの勤務で遅刻・早退・欠勤全てOKの完全フリーフレックス制度
- EC事業部や卸売事業部を担当する外国人エンジニアの正社員雇用
- 誰でも同じ質で作業できるように作業量の目安やノルマも明記したマニュアルの整備
- パート社員でも昇給可能な透明性の高い評価制度
- 採用時期を揃えることで同期を作ることでチームワークを促進
- 社員たちの中抜けの受容し、柔軟な働き方を実現
- 人の悪口を全面的に禁止し、誰もが制度を活用できる働きやすい環境を構築など
こうした前代未聞の先進的な取り組みによって、主に以下のような成果を出しています。
- 過疎化が進む地域にも関わらず、わずか7ヶ月で40人の人材を確保
- 創業から4年で売上が1.6億円から11億円に増加
- 人材不足で事業継続が難しくなった企業からの引継ぎ依頼の増加など
株式会社四国銀行
1878年に創業した株式会社四国銀行では、人口減少や高齢化に伴って、預貸ビジネスでは成長が見込めない状況にありました。
その一方で顧客企業の人手不足や企業の後継者不足により事業継承や資産形成への需要が増していることが分かり、「真っ先に相談され、地域の発展に貢献するベストリライアブル・バンク」の実現を目指すようになりました。
同社でおこなっているダイバーシティ経営の取り組みは、主に以下の通りです。
- 一人1人のチャレンジを促し強みを伸ばすためのスキル認定制度の導入
- 公募制研修や指名型研修、オンラインツールを活用した休日セミナーの実施
- 不動産販売業や保険会社など様々なバックグラウンドを持つ人材の採用
- 育児による短時間勤務制度を小学3年生修了までに拡大
- 不妊治療や介護などを含む傷病への支援制度の追加
- 子供が生まれた男性社員に育児休業等を促す「仕事と子育て両立パパ宣言」の実施
- 女性のキャリアアップのための「女性法人営業担当者育成研修」の導入など
業務の効率化や人材育成を強化した結果、主に以下のような成果を出しています。
- 1年間で事業承継・M&A支援件数が1,000件以上増加
- ビジネスマッチングの成約件数が729件と前年比で180件近く増加
- 女性社員のキャリアアップで女性役職者は50名増加、女性管理職は11名増加など
ケイアイスター不動産株式会社
1990年に創業されたケイアイスター不動産株式会社は、用地取得から開発、企画、施工、販売、販売後のリフォーム、買取りまでを網羅的に対応しています。
スピード感ある事業拡大と業績向上を目指す上では人材の確保・定着・育成が責務となっていますが、女性が働きづらい環境や少子高齢化による職人不足が深刻化していたため、多様な人材の活用と組織体制の強化を図るようになりました。
同社での主なダイバーシティ経営の取り組みは以下の通りです。
- ベトナムで優秀な若手人材を採用
- 女性社員のみで構成された社内チームの発足
- 男性社員の女性のライフイベントに対する意識改革の促進
- 時差勤務・時短勤務・在宅勤務等の制度の拡充
- 社員の意思で異動できるフリーエージェント制度
- OJT形式による職人育成プログラム「クラフトマン制度」の導入など
こうした取り組みを意欲的におこなった結果、主に以下のような成果を出すことに成功しました。
- 活躍した女性社員が取締役と執行役員に昇進
- 女性営業社員が46名から85名と増加率185%を記録
- 産休・育休取得後の復職率が100%を達成
- 男性の育休取得率が53%に到達
- 経済産業省の「なでしこ銘柄」に2年連続で認定
- 埼玉県の「多様な働き方実践企業」で最高ランクのプラチナプラスを取得
- 国土交通省の「優秀外国人建設就労者」を2年連続で受賞など
ダイバーシティ経営の実践方法

ダイバーシティ経営を効果的に実践できるように経済産業省は「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」で以下の7つのアクションを提示しています。
【①経営戦略への組み込み】
経営トップがダイバーシティを経営戦略の中核と位置づけ、明確な方針を策定します。KPIやロードマップを設定し、自らの責任で取り組みを主導することが求められます。
【②推進体制の構築】
ダイバーシティ推進を全社的かつ継続的に進めるため、経営陣が責任を持つ推進体制を構築します。各部門との連携を強化し、組織全体での取り組みを促進します。
【③ガバナンスの改革】
取締役会の多様性を確保し、監督機能を強化します。ジェンダーや国際性を含む多様な人材を確保することで、ダイバーシティ経営の取り組みを適切におこなえます。
【④全社的な環境・ルールの整備】
属性に関わらず活躍できるように人事制度や働き方を見直します。柔軟な勤務形態や評価基準の導入により、多様な人材が能力を発揮できる環境を整えます。
【⑤管理職の行動・意識改革】
管理職向けにマネジメント研修や評価制度を導入し、多様な人材を活かすスキルの習得を促します。無意識の偏見を排し、公平な人材育成を推進します。
【⑥従業員の行動・意識改革】
多様なキャリアパスを提示し、従業員が主体的にキャリアを築けるよう支援します。キャリアオーナーシップを育むことで、組織の活性化を図ります。
【⑦労働市場・資本市場への情報開示と対話】
一貫した人材戦略を策定・実行し、その成果を労働市場や投資家に対して積極的に発信し、企業価値の向上を目指します。
未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!
GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/
無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
企業におけるダイバーシティはイノベーションの創出や人手不足の解消、競争力の強化に欠かせない要素です。
しかし多様な人材を確保しても活躍できる環境を整備していなければ、企業と従業員の双方に負担がかかるおそれがあるため、ダイバーシティに取り組みつつ、インクルージョンを整えていくことが重要となります。
自社でどのようにダイバーシティを推進できるのかを十分に検討し、持続的な成長を目指しましょう。
そして、もし今後の起業や事業展開を検討している方は、多様な人材が活躍しやすい仕組みがあらかじめ設計されているフランチャイズへの加盟も1つの手です。
フランチャイズは業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しており、集客や営業、商品開発・教育体制まで幅広くサポートしているため、多様なバックグラウンドを持つ人材でも活躍しやすい環境が整っています。その意味でも、ダイバーシティ時代の新たな挑戦先として有効な選択肢のひとつです。









