障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)によって、一定以上の規模の企業には障害者雇用が義務付けられており、定期的に障害者雇用が義務付けられる企業の範囲も拡大していますが、障害者雇用における給料はどのように考えれば良いのでしょうか。
今回は障害者雇用における給料の基礎知識や一般雇用よりも平均賃金が低い理由、平均賃金を高める方法などを紹介していきます。
なお、GLUGでは障害者雇用率向上のためのトータルサポートサービスを展開しております。
法定雇用率の遵守・社会貢献につながるサービスについてはこちらのページもご覧ください。
難しい障がい者雇用もお任せください!
GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!
無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/
無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
障害者雇用による給料の平均とは
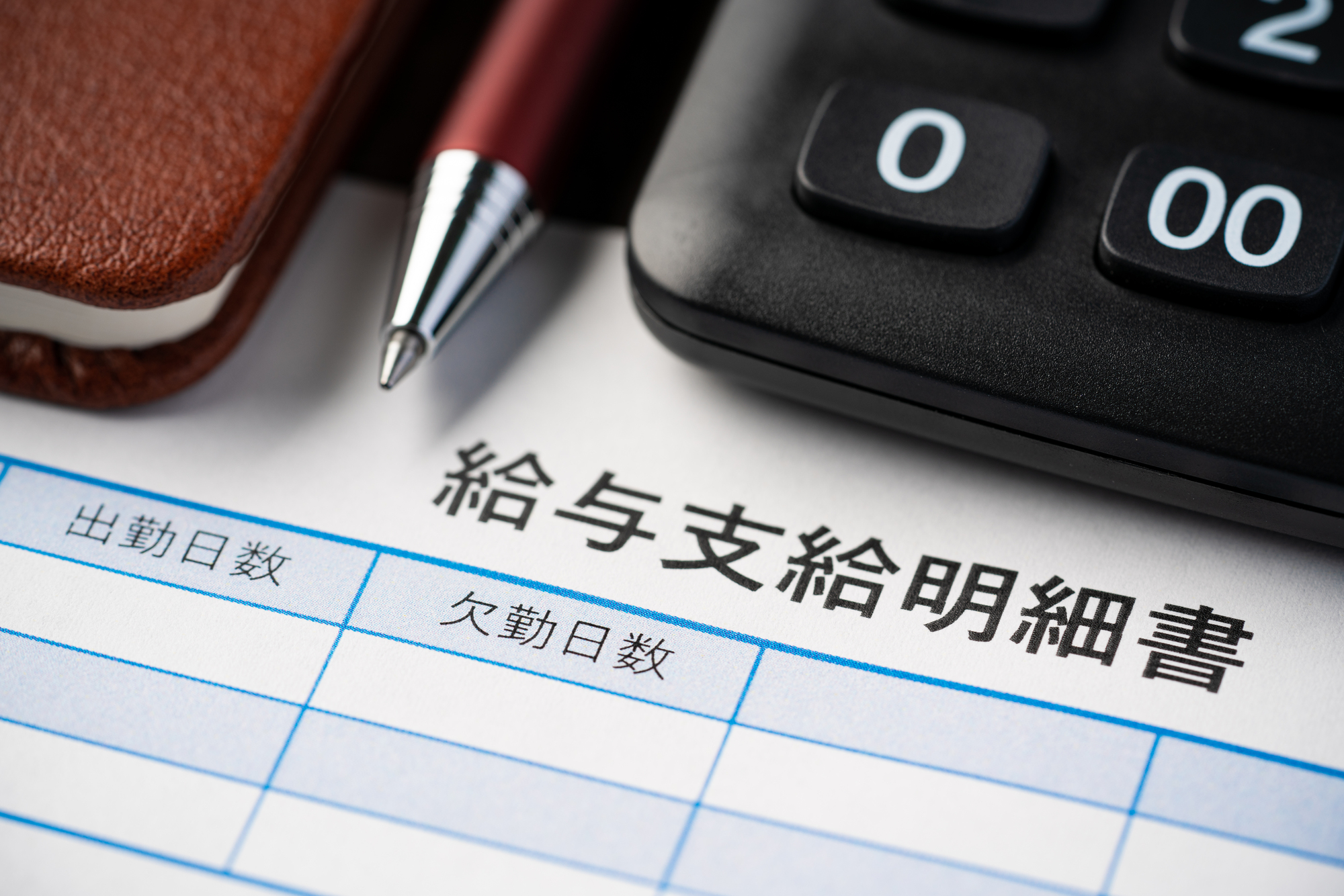
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によれば、一般企業で雇用されている身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者の1ヶ月あたりの平均賃金は、以下の通りです。
- 身体障害者:235,000円
- 知的障害者:137,000円
- 精神障害者:149,000円
- 発達障害者:130,000円
あくまでも雇用形態や週の所定労働時間を問わない平均賃金であり、例えば週30時間以上働く身体障害者の平均賃金は268,000円となりますが、手当を含めた平均賃金となります。
障害者雇用の概要を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
障害(障碍)者雇用とは?条件や助成金、支援制度、メリットを解説
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)によって、一定以上の規模の企業は障害を持つ方の雇用を義務付けられています。
2024年10月現在の障害者雇用促進法では、常時雇用する従業員が40人以上の場合、障がいを持つ方を1名以上雇用するように定められています。
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)のいずれかを所持している障害を持つ方が障害者雇用の対象となり、未所持の場合は障害者雇用の義務を果たせないため、一般枠での応募となります。
また障害者雇用促進法では、障害を持つ方への合理的な配慮が義務付けられている点も一般雇用と大きく異なり、障がい者の雇用において休憩や残業の調整、通院への理解などが必要になります。
さらに詳しく障害者雇用について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
GLUGが展開している障害者雇用のサポートサービスについてはこちらのページでもご紹介しています。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
障害者雇用の給料が低い理由

厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」に基づき、1ヶ月あたりの平均賃金で計算すると、障害を持つ方の全体的な平均年収は低い傾向にあります。
- 身体障害者:282万円
- 知的障害者:164万4,000円
- 精神障害者:178万8,000円
- 発達障害者:156万円
基本給だけでなく手当も含めた平均年収ですが、なぜ障害を持つ方の平均年収が一般雇用よりも低い傾向にあるのでしょうか。
ここでは障害者雇用の給料が低い傾向にある理由を説明していきます。
正社員の割合が少ない
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」で説明されている通り、以下のように障害者雇用の有期契約を含む正社員の割合が低いことにより、平均年収が下がっています。
- 身体障害者:59.3%
- 知的障害者:20.3%
- 精神障害者:32.7%
- 発達障害者:36.6%
派遣労働者やパート・アルバイトなどの非正規雇用の場合、基本給以外の手当などが設けられていないため正社員よりも平均年収が低い傾向にあります。
仕事の幅が狭まる場合がある
持っている障害の度合いによっては一般雇用の従業員よりも対応できる仕事の幅が狭まることも平均年収が低くなる要因として挙げられます。
一般企業は障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)に基づく合理的な配慮をおこなっており、障害の度合いに応じた仕事を一般企業から任せています。
一般雇用・障害者雇用問わずに仕事で一定以上の成果を出している場合は昇進・昇給によって年収を上げていくことができるものの、簡易的な仕事のみを対応している場合は上層部に評価されづらいことで、相対的に平均年収が上がりづらくなる傾向にあります。
時短勤務によって給料が低い
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」で説明されている通り、以下の割合で一般企業が短時間勤務等勤務時間の配慮をおこなっています。
- 身体障害者:37.9%
- 知的障害者:50.9%
- 精神障害者:54.3%
- 発達障害者:50.9%
障害を持つ従業員の心身への負担を少しでも減らすための一般企業の合理的配慮であるものの、時短勤務によって平均年収はフルタイム勤務よりも下がります。
労働時間分の給料を従業員に支払う仕組みとなっているため、一般雇用の場合でも時短勤務であれば受け取れる給料は下がります。
障害者雇用による給料を上げるためのポイントとは

障害者雇用の場合、非正規雇用の割合が高いことで年収が低い傾向にあるほか、正社員を目指している障害を持つ方もいるため、企業側は正社員登用制度を設けることで年収が上がりやすい仕組みをつくると良いでしょう。
障害の度合いによっては最初から正社員として週30時間以上働くことが難しい場合でも、正社員登用制度があればまずは非正規雇用としてスキルアップと実績を重ねながら正社員を目指せるため、正社員としてのハードルが下がります。
障害を持つ従業員がスキルアップを図るには、専門スクールでの実技習得や通信講座の活用が効果的です。
たとえば、事務職の場合は「日商簿記」や「MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)」、IT系では「ITパスポート」の取得が役立ちます。目標に合ったスキル習得を計画的に進めることが重要です。
また障害を持つ方のスキルアップやキャリアアップを後押しするために、資格手当を設けるのも1つの手です。
資格手当の相場は難易度や企業の規模によって金額は変わり、5,000円から30,000円前後ですが、任せている仕事と紐づく資格の手当を基本給にプラスする仕組みを作ると障害を持つ従業員のモチベーションも上がりやすくなるでしょう。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
業種別の給与相場と傾向
障害者雇用における給与水準は、職種や業界ごとの特性により大きく異なります。
たとえば、体力を要する現場系職種では経験よりも作業量が評価されやすく、比較的安定した給与が得られる傾向があります。
一方、事務職やIT関連などは専門スキルの度合いや資格の有無が賃金に大きな影響を与えており、高収入を得ている方もいます。
| 業種 | 主な仕事内容 | 月給相場 | 傾向・特徴 |
| 製造業 | 組立・検品など | 15万円から18万円前後 | 体力仕事が中心で安定した需要がある |
| サービス業 | 清掃・接客など | 14万円から17万円前後 | 求人数が多く、柔軟に働きやすい |
| 事務職 | データ入力・庶務等 | 16万円から20万円前後 | スキル重視で在宅勤務できる場合がある |
| IT関連 | プログラミング・保守等 | 18万円から25万円前後 | 専門スキル必須でスキル次第で高収入も目指せる |
活用できる手当や助成金制度
障害者を雇用する企業には、さまざまな助成金制度が活用できます。たとえば「特定求職者雇用開発助成金」では、ハローワーク経由で採用した場合に最大240万円が支給されます。
「障害者雇用調整金」は法定雇用率を上回る企業に対し、1人あたり月額27,000円が支給されます。
「在宅就業障害者特例調整金」は在宅勤務の障害を持つ方に仕事を35万円以上発注した場合、支払額に基づいて調整金が支給されます。
申請はいずれも所轄のハローワークまたは労働局にておこないます。事前届出、雇用契約書、勤務実績などの提出が必要となるため、計画的に準備しましょう。
給与アップの具体的な方法
給与アップを目指すには、スキルと雇用形態の両面からのアプローチが効果的です。ITパスポートや簿記検定などの資格を取得すれば、職務の幅が広がり、昇給や職種変更につながります。
また勤務先での信頼を積み重ね、正社員転換制度を活用すれば、非正規から正規雇用へ移行できるため、安定した収入を見込めます。実際に日頃の働きぶりが評価されたことで半年で正社員登用された例もあります。
企業側は「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を活用すれば、1人あたり57万円(中小企業)を国から受給できるため、社員のキャリアアップ・スキルアップを後押ししやすくなっています。
給与相談ができる公的機関
給与や雇用に関する相談は、主に以下3つの公的機関で無料で受けられるため、給与で悩んでいる場合は積極的に活用しましょう。
| 機関名 | 役割内容 | 連絡・相談方法 |
| ハローワーク | 助成金・就職相談 | 最寄りの窓口または電話で予約 |
| 労働基準監督署 | 賃金・労働条件の相談・指導 | 窓口対応、または労働局HPから確認 |
| 障害者就業・生活支援センター | 働き方や生活面の継続支援 | 各センターに電話・訪問で相談 |
給与交渉の進め方と注意点
給与交渉を成功させるには、事前準備とタイミングが鍵となります。まずは実績や貢献度を整理し、具体的な数値で示せるように準備しましょう。
交渉の時期は人事評価や契約更新前が適切です。面談では冷静かつ論理的に話し、感情的な表現は避けましょう。
交渉時の主なポイントは、以下の通りです。
- 成果やスキルを客観的に説明する
- これまでの実績と会社への貢献度を根拠に昇給を提案する
- 業界相場や会社の状況も踏まえて現実的な金額を提示する
最低賃金法について
最低賃金法とは、労働者の生活の安定と労働力の向上を図るための賃金の最低額を保証する法律であり、一般雇用と障害者雇用のどちらにも最低賃金法は適用されています。
同法律は最低賃金を下回る不当な対価で働かせる事態を防ぐことを目的としており、企業は最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
最低賃金法で定められている最低賃金には、以下の2種類があり地域や産業によって最低賃金は変わりますが、最低賃金を下回らないように把握しておくことが大切です。
【地域別最低賃金】
都道府県ごとに法律で決められている最低賃金です。
【特定最低賃金】
重要性や危険性などが理由で地域別最低賃金よりも高い水準で決められている最低賃金で、一部の産業は特定最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金を下回る給料はすべて違法であり、最低賃金法の第四十条で定められている通り、国への50万円以下の罰金と従業員への未払い賃金の支払いをしなければなりません。
第四十条
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
障害者雇用による給料に関する相談先

障害者雇用による給料を相談したい場合、障害者就業・生活支援センターやハローワーク(公共職業安定所)など障害福祉サービスを提供する機関に頼ると良いでしょう。
障害者就業・生活支援センターやハローワーク(公共職業安定所)は、障害者雇用をおこなう一般企業と障害を持つ労働者のどちらのサポートもおこなっており、障害者雇用における給料の相談対応も受け付けています。
今回は簡易的な説明となりましたが、さらに詳しく障害者雇用の支援サービスを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
障がい者の雇用支援はどのようなものがある?支援機関や支援サービスを紹介
難しい障がい者雇用もお任せください!
GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!
無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/
無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
一定以上の規模の企業の場合、障害者雇用が義務付けられていますが、非正規雇用や時短勤務などが要因となって一般雇用と比べて障害者雇用の方が平均賃金が低い傾向にあります。
障害を持つ方のキャリアアップや昇給などを後押しするために正社員登用制度や資格手当などを導入することで、一般雇用における平均賃金との差を縮められます。
障害者雇用の理解を深めつつ、障害を持つ従業員が定着できる制度を日頃から考えていくと良いでしょう。
なお、GLUGでは障害者雇用におけるトータルサポートを提供しています。









