就労継続支援B型を含む障がい福祉サービスは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)によって3年毎に改定される仕組みであり、2024年には大きな改定がありました。
今回は就労継続支援B型の基礎知識や2024年の改定内容、加算・減算の種類などを網羅的に解説していきます。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
就労継続支援B型の収益構造
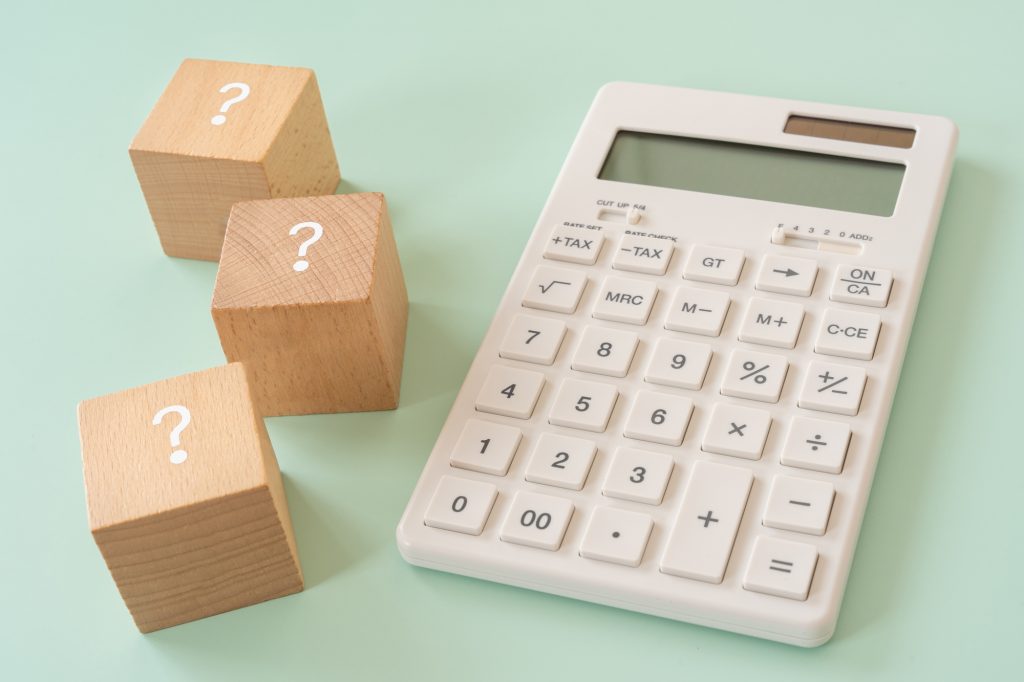
就労継続支援B型は、就労系障がい福祉サービスの1つであり、障がいや難病、高齢によって一般企業で雇用契約を結ぶ労働が難しい方を対象として、働く場所を提供しつつ、自立した生活に向けた支援・訓練をおこなっています。
就労継続支援B型の売上は以下の2種類です。
- サービス利用者の作業で発生する生産活動による売上
- 支援・訓練を提供する対価として支給される国からの報酬
それぞれ詳しく解説していきます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
就労継続支援B型の売上とは
就労継続支援B型事業所では、サービス利用者がおこなう施設の清掃やお弁当の製造などの生産活動によって売上を確保しています。
生産活動による売上は原則として余剰金を発生させてはいけないルールとなっており、売上から経費を除く金額を工賃としてサービス利用者に支払わなければいけません。
ただし例外として将来的にサービス利用者の工賃水準を下回る場合や生産活動に関する設備を導入する場合のみ、理事会等に承認を得た上で余剰金の積み立てが認められています。
原則として前述した理由以外で積立金を使用することは許可されていませんが、国や行政から支給される報酬の受け取りが2ヶ月以上遅れている場合に限り、積立金の一時繰替使用が認められています。
就労継続支援B型の訓練報酬の仕組み
就労継続支援B型では、サービス利用者に支援・訓練を提供する対価として国・行政から報酬を受け取れます。
報酬の金額は基本報酬と加算によって最終的に受け取れる金額が決まる仕組みで、基本報酬は以下いずれかの報酬体系を選びます。
【「平均工賃月額」に応じた報酬体系】
サービス利用者に支払う平均工賃の金額に比例して基本報酬などが高くなる報酬体系で、就労継続支援B型サービス費ⅠからⅢに基づいて算定されます。
【「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系】
同じような境遇や立場にいる人たちがサポートし合うピアサポートや地域共同に対して加算をおこなう報酬体系で、基本報酬は就労継続支援B型サービス費ⅣからⅥに基づいて算定されます。
またサービス利用者数と日数なども掛け合わせた上で基本報酬を決定するため、サービス利用者の人数やB型事業所を利用した月間利用日数も基本報酬に大きな影響を与えます。
詳しくは後述しますが、加算は一定の基準を満たした場合に上乗せされる報酬のことであり、一つひとつの単位自体は大きくないように見えるかもしれませんが、サービス利用者の人数・時間を掛け合わた基本報酬に全て加算されるため、最終的な報酬に大きな影響を与えます。
なお、GLUGでは就労継続支援事業所の開業・運営のサポートや加算を多く獲得するための支援をおこなっています。
福祉事業の概要やGLUGのサポートを詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
就労継続支援B型の2024年度報酬改定について

就労継続支援B型の報酬は、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)によって3年毎に改正される仕組みで、直近では2024年4月に改定されました。
ここでは厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」に基づき、2024年4月の報酬に関する改定内容を解説していきます。
報酬体系の見直し
就労継続支援B型事業所の工賃をさらに引き上げることを目的として、以下のように見直されました。
- 平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価引き上げ、低い区分の基本報酬の単価引き下げ
- 「利用者の就労や生産活動等への参加等」の報酬体系の見直しによって短時間利用者が多い場合は減算
- 手厚い人員配置を可能とするために人員配置6:1の報酬体系を新設
就労継続支援B型は雇用契約に基づく労働が難しい方を対象にしていることからサービス利用者と雇用契約を結ばないため、生産活動の対価として支払う工賃は最低賃金が保証されていません。
厚生労働省の「障害者の就労支援対策の状況」によれば、2022年における就労継続B型の全国平均工賃は以下の通りです。
月額:17,031円
時給(時間額):243円
国や行政がB型事業所の平均工賃を上げるための取り組みをおこなっており、詳しくは後述しますが、その一環で今回の改定で高工賃を支給している事業所の基本報酬の単価が引き上げられ、平均工賃月額15,000円未満の場合は単価が引き下げられています。
平均工賃月額の算定方法の見直し
就労継続支援B型事業所の中には障がい特性などによって利用日数が少ないサービス利用者も多く受け入れる場合があることも踏まえ、平均工賃月額の算定方法を以下のように見直しています。
- 前年度における工賃支払総額を算出
- 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
- 前年度における更新支払総額÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数÷1人当たり平均工賃月額を算出
加算方法の見直し
今回の改定によって基本報酬への加算がより分かりやすく、さらにサービス利用者の支援につながる内容になりました。
新設、または見直された加算は以下の通りです。
- 目標工賃達成指導員配置加算
- 目標工賃達成加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
- 集中的支援加算
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算
それぞれ詳しく解説していきます。
なお、GLUGでは就労継続支援事業所の開業・運営のサポートや法改正に伴う対応の共有などを網羅的におこなっています。
福祉事業の概要やGLUGのサポートを詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
目標工賃達成指導員配置加算
目標工賃達成指導員配置加算の見直しによって、常勤の目標工賃達成指導員を1人以上配置し、職業指導員・生活支援員(常勤で6:1以上の配置)、当該目標工賃達成指導員・職業指導員・生活支援員(常勤で5:1以上の配置)による人員体制で工賃向上に向けた取り組みをおこなう場合、以下の基準で加算されます。
| 利用定員 | 報酬単価 |
| 20人以下 | 45単位 |
| 21人以上40人以下 | 40単位 |
| 41人以上60人以下 | 38単位 |
| 61人以上80人以下 | 37単位 |
| 81人以上 | 36単位 |
目標工賃達成加算
目標工賃達成加算も新設された加算であり、目標工賃達成指導員配置加算の対象になる就労継続支援B型事業所などが行政の基準に基づき、工賃向上計画を作成した上で計画の工賃目標を達成した場合、10単位/日で加算されます。
福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員などの確保に向けて、処遇改善の措置を多くの事業所が活用できるように、今回の報酬改定で「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化した上で加算率を引き上げています。
複雑化していた加算を一本化することで事業所側が加算を狙いやすくすることを目的にしています。
新加算のいずれかを取得している場合でも新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金(工賃)の改善に充てることが要件とされています。
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
集中的支援加算
高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が事業所等が訪問等をし、適切なアセスメントや有効な支援方法の整理、環境整理などをおこなった場合、新設された集中的支援加算で評価されるようになりました。
集中的支援加算には以下2種類の区分があります。
【集中的支援加算(Ⅰ):1000単位/回】
広域的支援人材が訪問によって支援をおこなった場合、月4回の訪問を限度として加算されます。
【集中的支援加算(Ⅱ):500単位/日】
他の事業所・施設から集中的な支援が必要なサービス利用者を受け入れて集中的な支援をおこなった場合、1日につき加算されます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいを持つサービス利用者を多く受け入れている事業所がサービス利用者とのコミュニケーションに配慮しつつ、手厚い支援体制を整えている場合、見直し後の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算によってさらに評価されようになりました。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算には、以下の2種類の加算があります。
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ):51単位/日】
視覚・聴覚・言語機能のいずれかに重度の障がいがあるサービス利用者が全体の100分の50以上で、意思疎通に関する専門職員をサービス利用者数の40で割った数以上配置している場合に加算されます。
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ):41単位/日】
視覚・聴覚・言語機能のいずれかに重度の障がいがあるサービス利用者が全体の100分の30以上で、意思疎通に関する専門職員をサービス利用者数の50で割った数以上配置している場合に加算されます。
高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障害者支援体制加算は、今回の報酬改定で新設された加算であり、高次脳機能障害に関する研修を受けた職員を配置することで加算されます。
高次脳機能障害者支援体制加算は、以下の3種類があります。
【高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/日】
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置・公表し、実際に当該相談支援専門員が指定計画相談支援をおこなっている場合、加算されます。
【高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/日 】
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置・公表している場合、加算されます。
【高次脳機能障害支援体制加算 41単位/日 】
高次脳機能障害を持つサービス利用者が全体の100分の30以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置・公表している場合に加算されます。
減算方法の見直し
今回の報酬改定で以下の減算が新設されており、事業所側は減算を防ぐために日頃から注意しなければなりません。
- 短時間利用減算
- 虐待防止措置未実施減算
- 情報公表未報告減算
それぞれ解説していきます。
短時間利用減算
「利用者の就労や生産活動等への参加等」の報酬体系の見直しにより、利用時間4時間未満のサービス利用者が全体の5割以上の場合は、基本報酬が30%減算されることになります。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は全体の5割以上の場合でも基本報酬が減算されることはありません。
- 個別支援計画で定めた一般就労などに向けた利用時間延長のための支援をおこなっている
- サービス利用者に短時間利用せざるを得ない事情がある
虐待防止措置未実施減算
今回の改定で新設された虐待防止措置未実施減算によって、障害者虐待防止措置をおこなっていない事業所は基本報酬から1%減算されます。
以下いずれかを1つでもおこなっていない場合、基本報酬から1%減算されることになるため、見逃さないようにしておきましょう。
- 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る
- 従業者に虐待防止のための研修を定期的に実施する
- 上記措置を適切に実施するための担当者を配置する
また厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」で説明されているとおり、虐待防止委員会で外部の第三者・専門家を活用することや事業所の管理者・虐待防止責任者が都道府県の虐待防止研修を受講することが望ましいとされています。
業務継続計画未策定減算
厚生労働省は感染症や災害が発生した場合でも必要な支援を提供し続けられるように業務継続計画を求めています。
感染症や災害、もしくは両方の業務継続計画が未策定の場合、今回の改定で新設された業務継続計画未策定減算によって基本報酬から減算されます。
提供する障がい福祉サービスによって減算されるパーセンテージは異なりますが、業務継続計画を策定していない就労継続支援B型の場合は、所定単位数の1%が減算されることになります。
情報公表未報告減算
厚生労働省はサービス利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化を推進しており、今回の改定で新設された情報公表未報告減算によって行政に情報公表に関する報告をしていない事業所の基本報酬は減算されることになります。
情報公表未報告減算も提供する障がい福祉サービスによって減算される割合は変わりますが、未報告の就労継続支援B型の場合は所定単位数の5%が減算されることになります。
なお、GLUGでは就労継続支援事業所の開業・運営のサポートや加算・減算対策、行政対応などの支援をおこなっています。
福祉事業の概要やGLUGのサポートを詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
その他の改定事項
新設された加算と減算を中心に紹介してきましたが、今回の改定で新たに就労継続支援B型に求められているその他の対応もあります。
ここではその他の改定事項も紹介していきます。
本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
今回の改定によって本人の意思に反する異性介助を防止するために、サービス管理責任者等が本人の意思を把握した上でサービス提供体制を確保するように求められるようになりました。
本人の意向を踏まえたサービス提供は、以下の障がい福祉サービスを提供する事業所を除いた全ての事業所が対象です。
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
- 地域相談支援
- 自立生活援助
- 就労定着支援
身体拘束等の適正化の推進
サービス利用者の身体拘束等は原則禁止されていますが、本人や周囲の身体・命に危険が及ぶ可能性が高いなどやむを得ない場面では認められています。
ただし、そうした例外を除けば身体拘束等はサービス利用者の尊厳ある生活を阻むものであるため、安易に正当化することがないように指針の策定など身体拘束等の適正化が求められています。
義務付けられている以下の身体拘束に関する適正化を守っていない場合、就労継続支援B型の場合は所定単位数の1%が減算されることになります。
- 身体拘束等に関する記録をおこなう
- 身体拘束等の適正化を推進する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
- 従業者に対して、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する
参考:厚生労働省「身体的拘束等の適正化の推進」
個別支援計画の共有
今回の改定によってサービス利用者の個別支援計画を指定特定(障がい児)相談支援事業所への交付も求められるようになりました。
個別支援計画の共有は、以下の障がい福祉サービスを提供する事業所を除いた全ての事業所が対象です。
- 短期入所
- 就労選択支援
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
- 地域定着支援
- 福祉型・医療型障がい児入所施設
障がい者の意思決定を推進するための方策
今回の改定によって、障がいを持つサービス利用者の意思を尊重するためにサービス担当者会議・個別支援会議に原則として本人も参加するものとし、本人の意向等を十分に確認するように求められています。
障がい者の意思決定を推進するための方策は、以下の障がい福祉サービスを提供する事業所を除いた全ての事業所が対象です。
- 障がい児相談支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型・医療型障がい児入所施設
人員基準における両立支援への配慮
事業所での治療と仕事の両立を進めつつ、職員の定着促進を図ることを目的として、常勤要件と常勤換算要件が今回の改定で以下のように見直されました。
【常勤要件の見直し】
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤として扱われるようになりました。
【常勤換算要件の見直し】
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算でも1人分のカウント(常勤)として扱われるようになりました。
常勤とは就業規則などで定められた週の所定労働時間で働く方のことであり、所定労働時間40時間で40時間働くのであれば常勤、所定労働時間よりも短い勤務時間の方は非常勤に分類されます。
常勤換算とは非常勤職員の合計労働時間が常勤職員の何人分になるのかという計算であり、行政が常勤換算で人材を確保することを認めています。
常勤換算では常勤職員を1、非常勤職員を0.5(20時間労働の場合)と定義し、非常勤職員を2名配置することで人員配置の常勤職員1人以上という基準を満たすことができます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
管理者の働き方について
今回の改定によって、事業所の管理者は以下のようにより柔軟な対応ができるようになりました。
- 責務を果たせるなど一定の条件を満たしている場合のみ、同一事業者が設置する他の事業所等の管理者・従業者と兼務可能
- 必要に応じて出勤できる状態であるなど一定の条件を満たしていれば、テレワークで管理業務をおこなうことも可能
食事提供体制加算の経過措置の取扱い
2024年3月31日までとされていた食事提供体制加算は、サービス利用者への食事提供による栄養面での配慮から経過措置として2027年3月31日まで延長されました。
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・所得割16万円未満のサービス利用者に対して、次の条件をすべて満たした上で当該施設(事業所が原則)の調理室を使って食事の提供をおこなった場合、加算されます。
【食事提供体制加算(就労継続支援B型を含む通所系:30単位/日)】
- 管理栄養士・栄養士(外部委託含む)を献立作成に関わっていること、もしくは栄養ケア・栄養ステーション・保健所等の管理栄養士・栄養士が栄養面を確認した献立であること
- サービス利用者ごとの摂食量を記録していること
- サービス利用者ごとの体重・BMIをおおむね6ヶ月に1回記録していること
なお、GLUGでは就労継続支援事業とお弁当事業を組み合わせた福祉事業を展開しており、食事提供体制加算につなげているクライアント様が多くいらっしゃいます。
福祉事業の概要やGLUGのサポートを詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
感染症対策の強化にかかる取組み
就労継続支援B型は対象外となりますが、施設入居支援・共同生活援助(グループホーム)・福祉型障がい児入所施設の場合、協定締結医療機関と連携し、感染症発生時等の対応を取り決めることが努力義務とされています。
以下の必要要件を満たしている場合、「障害者支援施設等感染対策向上加算」として基本報酬に加算されます。
【障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10単位/月】
以下をすべて満たしている場合、1ヶ月につき所定単位数が加算されます。
- 第二種協定指定医療機関と新興感染症発生時等の対応を行う体制を確保している
- 協力医療機関等と感染症の対応を取り決め、連携しながら適切に対応できる状態である
- 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算・外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関の院内感染対策に関する研修・訓練に1年に1回以上参加している
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
【障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5単位/月】
医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1ヶ月につき所定単位数が加算されます。
また障害者支援施設等が新興感染症等の発生時にサービス利用者の施設内療養をおこなう場合、必要要件を満たしていれば新設された「新興感染症等施設療養加算」で加算評価されます。
【新興感染症等施設療養加算 240単位/日】
厚生労働大臣が定める感染症にかかった入居者に対して、相談対応・診療・入院調整等をおこなう医療機関を確保している指定障害者支援施設等が適切な感染対策・指定施設入所支援等をおこなった場合、1ヶ月に5日を限度に所定単位数が加算されます。
就労継続支援B型の基本報酬

前述しましたが、就労継続支援B型の基本報酬は、以下2つのいずれかの報酬体系から選びます。
【「平均工賃月額」に応じた報酬体系】
サービス利用者に支払う平均工賃の金額に比例して基本報酬などが高くなる報酬体系で、就労継続支援B型サービス費ⅠからⅢに基づいて算定されます。
【「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系】
同じような境遇や立場にいる人たちがサポートし合うピアサポートや地域共同に対して加算をおこなう報酬体系で、基本報酬は就労継続支援B型サービス費ⅣからⅥに基づいて算定されます。
ここではそれぞれ詳しく解説していきます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲ
就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲは、職員の配置・平均工賃・定員数の3つの項目で基本報酬が決まる仕組みであり、まとめて「平均工賃月額」に応じた報酬体系とも呼ばれています。
就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲのそれぞれの詳細は以下の通りです。
【就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)※利用定員が20人以下の場合】
| 配置 | 平均工賃 | 単位 |
| 6:1以上 | 45,000円以上 | 837単位 |
| 35,000円以上45,000円未満 | 805単位 | |
| 30,000円以上35,000円未満 | 758単位 | |
| 25,000円以上30,000円未満 | 738単位 | |
| 20,000円以上25,000円未満 | 726単位 | |
| 15,000円以上20,000円未満 | 703単位 | |
| 10,000円以上15,000円未満 | 673単位 | |
| 10,000円未満 | 590単位 |
【就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)※利用定員が20人以下の場合】
15,000円以上の平均工賃から基本報酬の単位が引き上げられた一方で、15,000円未満の平均工賃の場合は基本報酬の単位が引き下げられています。
| 配置 | 平均工賃 | 単位 |
| 7.5:1以上 | 45,000円以上 | 748単位 |
| 35,000円以上45,000円未満 | 716単位 | |
| 30,000円以上35,000円未満 | 669単位 | |
| 25,000円以上30,000円未満 | 649単位 | |
| 20,000円以上25,000円未満 | 637単位 | |
| 15,000円以上20,000円未満 | 614単位 | |
| 10,000円以上15,000円未満 | 584単位 | |
| 10,000円未満 | 537単位 |
【就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)※利用定員が20人以下の場合】
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)に関しても、15,000円以上の平均工賃から基本報酬の単位が引き上げられた一方で、15,000円未満の平均工賃の場合は基本報酬の単位が引き下げられています。
| 配置 | 平均工賃 | 単位 |
| 10:1以上 | 45,000円以上 | 682単位 |
| 35,000円以上45,000円未満 | 653単位 | |
| 30,000円以上35,000円未満 | 611単位 | |
| 25,000円以上30,000円未満 | 594単位 | |
| 20,000円以上25,000円未満 | 572単位 | |
| 15,000円以上20,000円未満 | 557単位 | |
| 10,000円以上15,000円未満 | 532単位 | |
| 10,000円未満 | 490単位 |
就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵ
就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵは、職員の配置・定員数の2つの項目で基本報酬が決まる仕組みです。
就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵだけにしかない加算もあることから「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系とも呼ばれています。
就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵのそれぞれの詳細は以下の通りです。
【就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)※利用定員が20人以下の場合】
| 配置 | 単位 |
| 6:1以上 | 584単位 |
【就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)※利用定員が20人以下の場合】
| 配置 | 単位 |
| 7.5:1以上 | 530単位 |
【就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)※利用定員が20人以下の場合】
| 配置 | 単位 |
| 10:1以上 | 484単位 |
職員の配置状況による区分
前年度の平均サービス利用者数と配置している職業指導員・生活支援員等の合計人数による区分です。
基準上は10:1以上であれば事業所の運営基準を満たすことができますが、支援をおこなう専門スタッフを多く配置すれば区分が高くなることで行政から支給される基本報酬が高くなるほか、より手厚い支援をおこないやすくなります。
定員数による区分
就労継続支援B型サービス費ⅠからⅥは、すべて事業所のサービス利用者の定員数によって以下5つのいずれかの区分に分類されます。
- 利用定員が20人以下
- 利用定員が21人以上40人以下
- 利用定員が41人以上60人以下
- 利用定員が61人以上80人以下
- 利用定員が81人以上
この区分は行政への届け出によって区分が決まり、事業所の規模拡大などによって定員数を変えたい場合は行政が定める基準を満たした上で変更届を提出する必要があります。
平均工賃月額による区分
前述したように就労継続支援B型事業所では雇用契約に基づく労働が難しい方を対象としているため、サービス利用者に仕事の対価として賃金代わりの工賃を支払っています。
就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲの基本報酬は前年度の平均工賃ごとに8段階に区分されており、サービス利用者に支払う平均工賃の金額に比例して支給される国・行政の基本報酬が高くなります。
就労継続支援B型事業所では雇用契約を結ばないことから最低賃金以上が保証される就労継続支援A型よりも受け取れる工賃が低い傾向にあり、国・行政が工賃を向上させるための取り組みを推進しています。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
就労継続支援B型の加算・減算

就労継続支援B型では必要要件を満たした場合、加算として基本報酬に報酬が上乗せされ、基準を満たせない場合は減産として基本報酬から報酬が差し引かれます。
安定した経営や手厚い支援を提供する上では加算を狙いつつ、減算が発生しないように細心の注意を払うことが大切です。
ここでは就労継続支援B型の主な加算と減算を解説していきます。
なお、GLUGでは就労継続支援事業所の開業・運営のサポートや加算・減算対策など総合的な支援をおこなっています。
福祉事業の概要やGLUGのサポートを詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
加算
ここでは就労継続支援B型の必要要件を満たした場合に報酬に上乗せされる加算の一例を紹介していきます。
B型事業所の支援内容によって算定できる加算は異なるほか、算定の要件を満たした場合はすみやかに申請が必要な加算もあります。
【初期加算】
新規のサービス利用者がいる場合、利用開始から30日間、利用日に応じて基本報酬に上乗せされる加算です。
【欠席時対応加算】
サービス利用者の急病などによる利用キャンセルが発生した際に連絡や相談などの支援をおこなった場合、1人あたり最大月4回まで受け取れる加算です。
【福祉専門職員配置等加算】
Ⅰ〜Ⅲの種類があり、社会福祉士や作業療法士などの資格を持つ常勤の生活支援員・職業指導員の割合に応じて分類・加算されます。
【訪問支援特別加算】
3ヶ月以上継続して通っていたサービス利用者が5日間以上休んだ際、職員がサービス利用者の自宅に訪問・相談対応などの支援をおこなった場合に得られる加算です。
訪問への同意を得ていることや、個別支援計画で定めていることなどが加算の条件となります。
【食事提供体制加算】
収入が一定以下で、個別支援計画などで対象となるサービス利用者に食事を提供した場合に得られる加算です。
【送迎加算】
サービス利用者の自宅や最寄り駅への送迎によって得られる加算です。
ⅠとⅡの2種類があり、1回の送迎で平均10人以上(定員20人未満は定員の50%以上)を送迎できている場合はⅠ、送迎回数が週3回以上の場合はⅡに分類されます。
両方を満たす場合、Ⅰに分類されます。
【就労移行連携加算】
サービス利用者が就労移行支援の利用を始める際に、就労移行支援事業所との連絡調整や、特定相談支援事業所への情報提供をおこなった場合に受け取れる加算です。
【就労移行支援体制加算】
サービス利用者が一般企業に就労し、就労先での雇用が6ヶ月を達した場合に得られる加算です。
基本報酬によって、Ⅰ・Ⅱに分類されます。
今回は就労継続支援B型の一例を紹介しましたが、詳しく知りたい方は厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。
減算
就労継続支援B型の基準を満たせなかった場合、基本報酬から減算として差し引かれてしまうため、事業所は減産が起きないように日頃から注意する必要があります。
ここでは就労継続支援B型の減算を紹介していきます。
【サービス管理責任者欠如減算】
支援の総合的な管理をおこなうサービス管理責任者の人員配置基準を満たしていない状況が一定期間続いた場合、基本報酬から減算されます。
【サービス提供職員欠如減算】
生活支援員・職業指導員の人員配置基準を満たしていない状況が一定期間続いた場合、基本報酬から減算されます。
【定員超過利用減算】
行政に申請しているサービス利用者の定員数から一定以上超過している場合、基本報酬から減算されます。
【個別支援計画未作成減算】
個別支援計画を作成していない・作成していない期間がある・内容に不備があるなどの場合に基本報酬から減算されます。
【身体拘束廃止未実施減算】
義務付けられている身体拘束の適正化を実施していない場合、基本報酬から減算されます。
【虐待防止措置未実施減算】
必要要件を満たす虐待防止措置が実施されていない場合、基本報酬から減算されます。
【業務継続計画未策定減算】
感染症や災害、または両方の業務継続計画を策定していない場合、基本報酬から減算されます。
【情報公表未報告減算】
障害福祉サービス等情報公表システムで行政に報告していない場合、基本報酬から減算されます。
【短時間利用減算】
利用時間4時間未満のサービス利用者が全体の5割以上の場合は、基本報酬から減算されます。
今回は就労継続支援B型の一例を紹介しましたが、詳しく要件を知りたい方は厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をご覧ください。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
就労継続支援B型を含む障がい福祉サービスは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)によって3年毎に改定される仕組みであり、より良い支援を目指すためには常に改定内容を正確に把握・支援に反映させる必要があります。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、生産活動の対価として支払われる工賃は最低賃金を下回る傾向にありますが、厚生労働省は工賃の向上を推進しており、今回の改定では高工賃を実現している事業所の基本報酬の単価が引き上げられ、平均工賃月額15,000円未満の場合は単価が引き下げられています。
またサービス利用者の工賃向上に取り組んでいる場合や実際に工賃を向上させた場合は、評価される加算も新設されており、工賃向上などサービス利用者の自立に向けたより良い支援を目指すことが事業所の安定した経営にもつながります。









