身体障害とは、一言でいえば「身体の機能に障害があること」です。
しかし、身体障害にも様々な種類や、障害の程度による等級の区別があり、それぞれ必要とする支援も異なってきます。
それにともない、身体障害を持つ方が利用できる制度やサービスも多様化しており、課題や悩みに対してどのようなサポートを受ければ良いか分からない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、身体障害の種類や等級のほか、生活や働くうえで役立つ仕組みやサービスをご紹介します。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
身体障害とは

身体障害者福祉法において、身体障害とは以下のように定義されています。
身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの 厚生労働省「障害者の範囲」より、身体障害者福祉法第四条
具体的には以下の5種類に分類された身体の各機能に障害がある場合に身体障害とされています。
- 視覚
- 聴覚または並行機能
- 手足や体幹
- 音声機能、言語機能または咀嚼機能
- 内臓や免疫など内部機能など
厚生労働省の調査によると、身体障がい者は436万人おり、人口の約3.4%が身体障害を持っています。
日本の高齢化にともなう身体障がい者の増加、重度化もあり、身体障がい者の人数も年々増加傾向にあります。
身体障害に限らず障がい者の人数は増え続けており、国は様々な障害特性や程度に応じたサポートができるよう、定期的に法律を見直しつつ、支援体制を拡大しています。
身体障害の主な種類

身体障害は大きく5種類に分類されるとご紹介しましたが、それぞれどのような症状があるのでしょうか。
ここでは種類ごとに、身体障害の症状をご紹介します。
視覚障害
視覚障害とは視力や視野などの機能に障害があることを指します。
見ることが不可能な場合(全盲)や見づらい場合(弱視)のほか、見える範囲が限定される視野狭窄も視覚障害に分類されます。
この症状により、形や色の識別、照明の明暗などへの対応、文字の判別などに困難が生じます。
聴覚・平衡機能障害
聴覚・平衡機能障害は、耳の神経または脳に障害があることを意味します。
聴覚障害では外耳・中耳・内耳・聴神経のいずれかに障害があることで、音が聞こえにくかったり、全く聞こえない状態となります。
程度は音量の単位であるデシベルを用いて表しますが、人によっては音が聞こえにくいだけでなく、歪んで聞こえたり、途切れて聞こえることもあり、補聴器や人工内耳を使用しても明瞭に聞こえないケースもあります。
平衡機能障害は内耳性のものと、脳性のものが存在します。
目を閉じた状態で立っていることができなかったり、目を開いていても10メートルを歩ききれない場合に平衡機能障害と判断され、その他の症状としてはめまいや耳鳴り、吐き気などが起こります。
肢体不自由
肢体不自由は、四肢や体幹の器官が病気やけがで損なわれることで日常生活が困難となる障害です。
事故などでの身体や脳・神経への損傷や、先天性のものもあり、個人差が大きい障害 といえます。
そのため症状も人によって異なり、歩行や筆記、食事などの生活ができなかったりするほか、体温調節ができないなどの症状を有する場合もあります。
音声・言語又は咀嚼機能障害
音声・言語又は咀嚼機能障害は、発音に関する機能や言語理解に関する障害、または咀嚼に関する機能に障害があることを指します。
音声・言語障害では、歯や顎、口腔などの発声器官の障害によるものや、脳の機能、聴覚の障害による「話す」「読む」「聞く」などの行動に困難が生じます。
話すことが一切できないという症状のほか、声が出ても言語にならないものもあり、知られているものでは吃音症も言語障害 にあたります。
咀嚼機能障害は、歯や顎、口腔や喉、食道などの障害により、食物の摂取が困難なものを指します。
噛むことだけでなく、飲み込むことが難しい場合もこれに該当し、重度な場合は経管のみでの栄養摂取しかできなくなる場合もあります。
内部障害
内部障害は身体の内部に障害を抱えることであり、身体障害者福祉法上では、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害の7種類が定められています。
症状によっては見た目やコミュニケーション上での判断が難しい場合もありますが、障害による症状のほか、運動能力や体力低下による疲れやすさなども発生します。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
身体障害の等級とは

身体障害の種類についてご紹介しましたが、種類とは別に、その障害・症状の程度により7つの等級が設けられています。
等級は指定医により判定され、1級に近づくほど障害の程度が重く、1級から6級までが身体障害者手帳の交付対象となります。
7級の等級では身体障害者手帳の対象となりませんが、7級にあたる障害を2つ持っている場合は交付対象になります。
なお、これらの等級については、厚生労働省より身体障害者障害程度等級表として公表されています。
肢体不自由
肢体不自由の場合、欠損や機能障害の度合いによって等級が決まっており、上肢・下肢は1級から7級、体幹は1級から3級と5級に分類されています。
等級の詳細は、以下の通りです。
| 識別 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | |
| 上肢機能 | 下肢機能 | ||||
| 1級 | 1.両上肢の機能を全廃したもの 2.両上肢を手関節以上で欠くもの | 1.両下肢の機能を全廃したもの 2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの | 体幹の機能障害により座っていることができないもの | 不随意運動・失調等により、上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
| 2級 | 1.両上肢の機能の著しい障害 2.両上肢のすべての指を欠くもの 3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4.一上肢の機能を全廃したもの | 1.両下肢の機能の著しい障害 2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | 1.体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの 2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの | 不随意運動・失調等により、上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
| 3級 | 1.両上肢の親指・人差し指を欠くもの 2.両上肢の親指・人差し指の機能を全廃したもの 3.一上肢の機能の著しい障害 4.一上肢のすべての指を欠くもの 5.一上肢のすべての指の機能を全 廃したもの | 1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠 くもの 3. 一下肢の機能を全廃したもの | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | 不随意運動・失調等により、上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
| 4級 | 1.両上肢の親指を欠くもの 2.両上肢の親指の機能を全廃したもの 3.一上肢の肩関節・肘関節・手関節のうち、 いずれか一関節の機能を全廃したもの 4.一上肢の親指・人差し指を欠くもの 5.一上肢の親指・人差し指の機能を全廃したもの 6.親指・人差し指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7.親指・人差し指を含めて一上肢の三指の機 能を全廃したもの 8.親指・人差し指を含めて一上肢の四指の機 能の著しい障害 | 1.両下肢のすべての指を欠くもの 2.両下肢のすべての指の機能を全 廃したもの 3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠 くもの 4.一下肢の機能の著しい障害 5.一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの 6.一下肢が健側に比して10センチ メートル以上または健側の長さの10分の1以上短いもの | 該当なし | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 5級 | 1.両上肢の親指の機能の著しい障害 2.一上肢の肩関節・肘関節・手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3.一上肢のおや指を欠くもの 4.一上肢の親指の機能を全廃した もの 5.一上肢の親指・人差し指の機能の著しい障害 6.親指・人差し指を含めて一上肢の三指の機 能の著しい障害 | 1.一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害 2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3.一下肢が健側に比して5cm以上または健側の長さの15分の1以上短いもの | 体幹の機能の著しい障害 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により、社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
| 6級 | 1.一上肢の親指の機能の著しい障害 2.人差し指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3.人差し指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | 1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2.一下肢の足関節の機能の著しい障害 | 該当なし | 不随意運動・失調等による上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
| 7級 | 1.一上肢の機能の軽度の障害 2.一上肢の肩関節・肘関節・手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3.一上肢の手指の機能の軽度の障 害 4.人差し指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5.一上肢の中指・薬指・小指を欠くもの 6.一上肢の中指・薬指・小指の機能を全廃したもの | 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2.一下肢の機能の軽度の障害 3.一下肢の股関節・膝関節・足関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害 4.一下肢のすべての指を欠くもの 5.一下肢のすべての指の機能を全 廃したもの 6.一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さの20分の1以上短いもの | 該当なし | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
参考:東京都福祉局「肢体不自由等級表と診断のポイント」
聴覚障害・平衡機能障害
聴覚障害は2級から4級と6級、平衡機能障害は3級と5級に区分されています。
等級の詳細は、以下の通りです。
| 識別 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 |
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 該当なし |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声を理解できないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 |
| 4級 | 1.両耳の聴力レベルがそれぞれ 80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話 声を理解できないもの) 2.両耳による話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの | 該当なし |
| 5級 | 該当なし | 平衡機能の著しい障害 |
| 6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話を理解できないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの | 該当なし |
参考:厚生労働省「身体障害認定基準等について」
視覚障害
視覚障害は障害の度合いに応じて、1級から6級に分類されています。
等級の詳細は、以下の通りです。
| 識別 | 視覚障害 |
| 1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者は、きょう正視力について測ったものをいう。)の和が0.01以下のもの |
| 2級 | 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ視能率による損失率が95%以上のもの |
| 3級 | 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ視能率による損失率が90%以上のもの |
| 4級 | 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
| 5級 | 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
| 6級 | 一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が 0.2を超えるもの |
参考:厚生労働省「身体障害認定基準等について」
内部障害
内部障害では7種類の障害ごとに1級から4級の区分が設けられています。
等級の詳細は、以下の通りです。
| 識別 | 心臓機能障害 | じん臓機能障害 | 呼吸器機能障害 | ぼうこう又は直腸の機能障害 | 小腸機能障害 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 肝臓機能障害 |
| 1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
| 2級 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
参考:厚生労働省「身体障害認定基準等について」
身体障害者手帳とは

身体障害福祉法上の障害に該当すると認められた場合、身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳が交付されると、医療費負担や税の減額や税の控除・免除、公共交通機関の運賃等の割引、障害者雇用枠の求人への応募ができるようになるなどのメリットがあります。
身体障害者手帳を交付されても、デメリットは存在しません。
不要であれば返却することもでき、履歴書などへの記載も義務ではありません。
サポートを受けることを考えるのであれば、手帳の取得をしておく方が良いでしょう。
また障害者手帳には今回紹介した身体障害者手帳以外にも療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の2種類があります。
簡易的な説明となりますが、それぞれの違いは以下の通りです。
| 種類 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
| 対象 | 6級以上の身体障害を持つ方 | IQがおおむね70以下の知的障害がある方 | 精神障害によって日常生活・社会生活に制約がある方 |
| 対象となる年齢 | 18歳以上 | 年齢制限なし | 年齢制限なし |
| 有効期限 | 原則なし | 原則2年、成人後の更新手続きの有無は自治体によって異なる。 | 原則2年、更新手続きが必要 |
| 申請場所 | 行政の障害福祉課 | 行政の障害福祉課 | 保健センター、もしくは行政の障害福祉課 |

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
身体障害のある方が受けられる制度・サービス
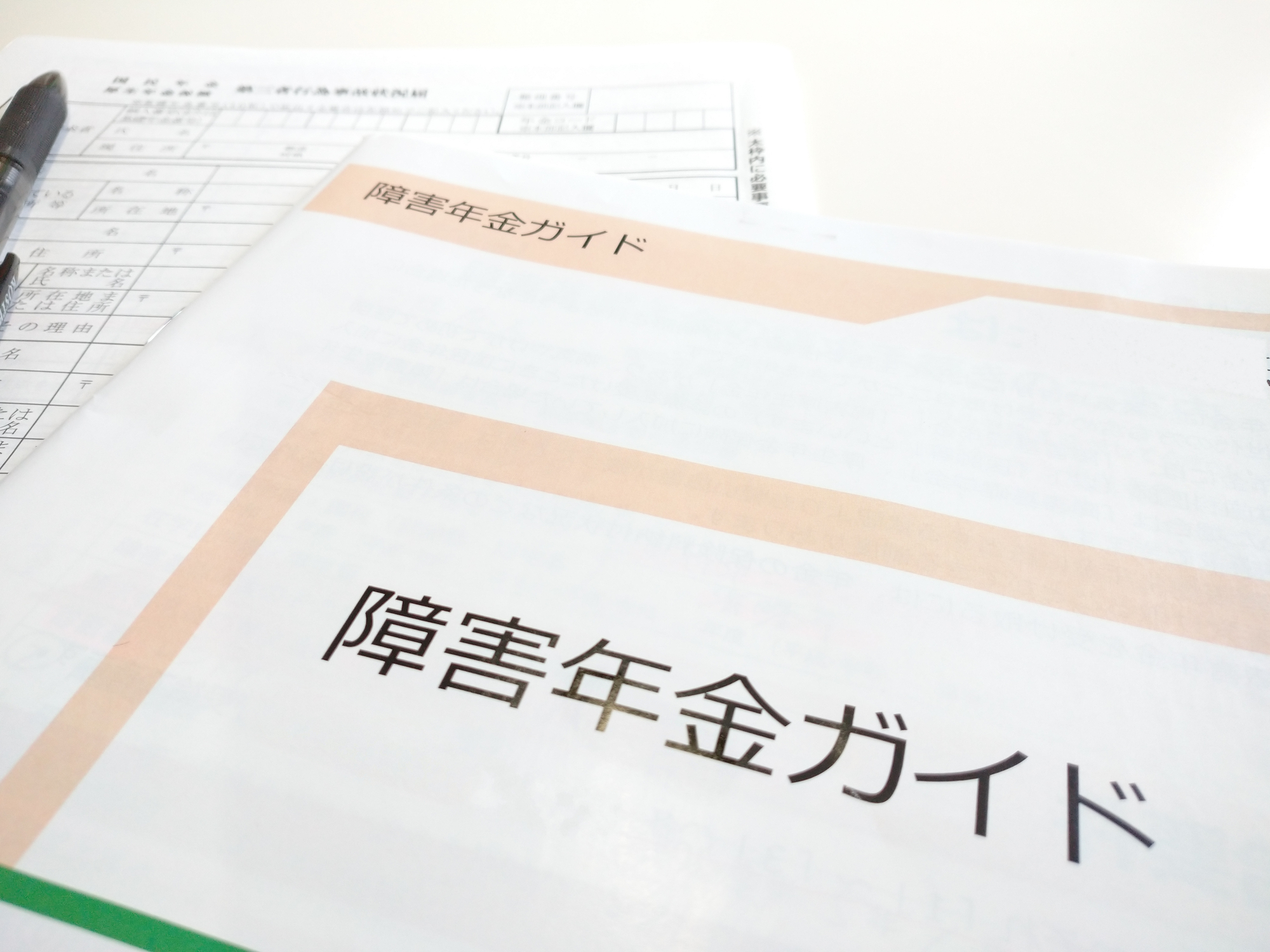
身体障害をお持ちの方は、その症状の程度によって、日常生活やコミュニケーションのなかで困難を感じることがあります。
そのような障がい者をサポートするため、様々な支援機関やサービスが存在します。
ここでは、その中でも主な5つをご紹介します。
経済支援制度
身体障害者手帳を持っていれば、医療費や補装具費用、リフォーム費用や税、公共料金などの助成や割引を受けることができます。
助成費用や割引額は自治体ごとに異なりますが、自治体ごとに用意される制度もあるため、どのような支援制度があるかは役所の福祉窓口で確認すると良い でしょう。
また、タクシーや飛行機などの交通機関、宿泊施設やテーマパークなどの民間の施設・サービスも割引を受けられる場合があります。
障害年金
障害年金制度は、病気やけがにより生活や仕事に制限を受けた場合に受給できる年金制度です。
「年金」とはいうものの現役世代も受給でき、原則20歳から65歳まで請求することができます。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられ、障害が重い方から1級・2級・3級と3種類があり、それぞれ年金額も異なります。
障害年金を受給するためには要件があり、以下の要件をそれぞれ満たしている必要があります。
- 初診日要件:初診日に年金制度に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること
- 障害状態該当要件:障害の程度が定められた基準に該当していること
就労系福祉サービス
就労を希望する場合、様々な就労系の福祉サービスを利用できます。
働く機会を通じて就労のためのスキルや経験を積む訓練を受けられる就労継続支援サービス や、障がい者の転職支援に特化した就労移行支援サービス 、一般就労後に職場に定着するためのサポートをおこなう就労定着支援サービス があります。
利用するにあたり、自身で調べるほか、就労支援センターや相談支援事業所、ハローワークに相談し紹介してもらう方法があります。
日常生活の支援サービス
障害を持つ方の生活をサポートするサービスも存在します。
一人暮らしで生活する障がい者の生活上の相談を受けて自分で解決できるよう援助する自立生活援助サービス や、障がい者グループホームでの共同生活を送るなかで生活力を養う共同生活援助サービス 、身体機能の維持・向上のためのリハビリや生活能力を上げるための支援をおこなう自立訓練サービス がこれにあたります。
また、先ほど紹介した相談支援サービスは地域の福祉サービスを熟知しているため、課題や希望に合わせて、これらのサービスも紹介してもらうことが可能 です。
介護サービス
介護と聞くと高齢者向けのサービスを想像しがちかと思いますが、障がい者向けの介護サービスも様々あります。
利用する期間や利用方法などによって異なり、夜間や休日に施設に入所して入浴・排泄・食事等の介護を受ける施設入所支援サービス や、介護者に来てもらうことでサポートを受ける訪問系の介護サービス 、短期のみ入所したり通うことでサポートを受けられる日中活動系の介護サービス などがあります。
常時介護が必要な場合、日中活動系の介護サービスと、施設入所支援サービスを組み合わせて利用することも可能です。
今回は簡易的な説明となりましたが、さらに詳しく障害福祉サービスを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
身体障害のある方の就労を支援する制度・サービス

身体障害をお持ちの方が働く場合、先ほど紹介した就労継続支援サービスを利用するほか、障害者雇用枠での就職、一般雇用での働き方があります。
一般雇用では障害を開示するオープン就労と、障害を開示しないクローズ就労がありますが、障害への理解や配慮を希望する場合、クローズ就労よりもオープン就労または障害者雇用枠での就労をする方が良い でしょう。
ここでは身体障がい者が働くための制度・サービスとして、就労継続支援サービスと障害者雇用についてご紹介します。
就労継続支援(A型/B型)
就労継続支援とは「障害者総合支援法」に基づき、障害や難病のために一般企業で働くことが困難な人々を対象とした障害福祉サービスです。
働くなかでの訓練や支援を通じ、障がい者の知識や能力の向上を目的としています。
サービスの利用者は障害の程度や体調に合わせて働くことができ、訓練や支援を受けながら給与・工賃といった報酬を受け取る ことができます。
就労継続支援には2種類あり、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」が存在します。
A型とB型で異なる点はいくつかありますが、大きな違いは「雇用契約の有無」 になります。
A型では事業者と利用者の間で雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給与が支払われますが、B型では雇用関係がないため「工賃」という事業所ごとに設定された報酬が支払われます。
これは障害や病気の程度によって対象が異なるためで、厚生労働省によると、A型は「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者」、B型は「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者」を対象としています。
事業所ごとに業務や支援の内容も異なりますが、上記のことから、B型の方が比較的簡単な仕事が多く、障害に対しての支援が多い傾向にあります。
また、一般就労に向けてのサポートをおこなっている事業所もあり、就労継続支援事業所でスキルを磨いた後、一般企業で働くという利用方法も可能 です。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
障害者雇用
障害者雇用とは、企業の障害者雇用枠の求人に応募して雇用されることです。
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、民間企業においては法定雇用率は2.3%、43.5人以上の従業員を雇用している場合には1人以上の障がい者を雇用しなければならないというルールが存在 します。
一般採用と同じく、書類選考と面接を経て採用という流れになりますが、面接の段階で障害について伝えていれば、その特性に配慮した休憩や残業時間の調整、通院への理解などが得られる こともあるでしょう。
また障害者雇用率が高い企業であれば、障害をお持ちの方がより働きやすくするための環境づくりを進めていることが考えられるため、障害者雇用の実績などを公開しているかも職場選びの基準になるでしょう。
就職・仕事について相談できるサービス・支援先

障害をお持ちの方の働き方についてご紹介しましたが、職場を探したり、働くうえでの悩みを相談できるサービスも存在します。
ここでは身体障害をお持ちの方が働くことを考えた際、相談できるサービス・支援機関をご紹介します。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターでは、障がい者の仕事の面と生活の面でそれぞれ支援を受けられます。
就労の前段階では、履歴書の作成や面接の準備、ハローワークや就労移行支援事業所と連携しての仕事探しなどのサポート が受けられます。
また、就労後も「働きづらい」などの悩みがあった場合、障害者就業・生活支援センターの職員による職場訪問や、休職した際の復職のための支援を受けられます。
就労移行支援
就労移行支援とは、障害や難病をお持ちの方の就職に向けての準備から、就職活動のサポート、就職後の定着支援など、就職に関しての様々なサポートをおこなうサービスです。
就労継続支援が働くためのサービスであるならば、就労移行支援は就職のための支援に特化している通所型のサービスで、就職するための相談から、目指す職業で必要となるスキルを得るための訓練、職場探し、就職後のサポートまで受けることが可能です。
受講できる訓練(プログラム)については就職を目指す職業や事業所によっても異なりますが、ビジネスマナーや応募書類の作成などの基本的なものから、WordやExcelなどの具体的な業務につながるパソコントレーニング、デザインやプログラミング言語の習得などの職種に特化したプログラムを組む事業所もあります。
ハローワーク
多くの企業からの求人を集めているハローワークでは、障害がある方への職業紹介もおこなっています。
障害に対して専門的な知識を持つ職員や相談員を配置しており、求人の紹介だけでなく、自己分析や自身の障害特性における仕事の適性の相談、採用面接への同行依頼もできます。
ハローワークでは企業側からの障害者雇用についての相談も受けているので、企業側の担当者の考えや職場の環境なども把握したうえでの職業紹介を受けられる 場合があります。
まとめ
身体障害は5つの種類と7つの等級で分類されていますが、それぞれ生活や仕事のうえでの制度・サポートが用意されています。
制度などはお住まいの市区町村ごとにルールや提出書類が異なる場合もあるので、利用する場合は役所の福祉課などにどのようなものがあるかを確認し、自分に必要なものを選択 しましょう。
もし選ぶことが難しければ、相談支援事業所や障害者就業・生活支援センターに相談してみるのも良いでしょう。
事業に福祉を取り入れるなら、GLUG
GLUGでは障がい者がより活躍できる社会を実現するため、障害福祉業界で事業を展開しようとする経営者をサポートすべく、就労継続支援A型事業や障害者グループホームの立ち上げから経営コンサルティングまで、トータルで支援しています。
障害福祉に参画する経営者・会社を増やさねばならないなか、国への事業申請や物件探索、人材の採用、利用者の集客、売上をつくれる生産活動の確保など、時間や手間がかかるポイントは様々あります。
GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営支援トップクラスの実績のもと、それらの全ての領域を支援しています。
就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。
また障害福祉業界の経営者・職員をサポートするべく、障害福祉サービスに特化した業務支援システムhaguパス などのツールもリリース。
業界をより活発にすべく、障害福祉に参画する経営者を支援してまいります。
年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!
GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!/
無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/
無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00









