障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)によって、対象となる企業は障害者雇用が義務付けられており、2024年12月現在は法定雇用率2.5%以上を維持しなければなりません。
法定雇用率を達成しやすくするために障害を持つ方のみなし雇用を導入して欲しいと考える一方、そもそも障害者雇用におけるみなし雇用がどういった制度なのか分からない方もいるでしょう。
そこで今回はみなし雇用の基礎知識やメリット・デメリット、導入事例などを解説していきます。
難しい障がい者雇用もお任せください!
GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!
無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/
無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
障害者のみなし雇用制度とは何か

障害を持つ方のみなし雇用とは、企業が就労継続支援事業所などに一定以上の発注をした際に、障害者雇用の法定雇用率に換算するという仕組みの制度です。
日本ではまだ導入されていない制度ですが、障害者雇用のハードルが下がるため、法定雇用率の達成を目指したい企業から制度化希望の声が数多く上がっており、後述するフランスの事例では実際に過去に障害福祉の制度の1つとして導入されていました。
なお、障害者雇用とは、身体・精神・知的障害のある方を対象に、一般雇用とは別に設けられた「障害者雇用枠」で雇用する制度のことです。
2025年6月現在、対象となる企業には障害者を法定雇用率2.5%以上の割合で雇用・維持することが義務付けられています。
障害者雇用を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
障害(障碍)者雇用とは?条件や助成金、支援制度、メリットを解説

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
障害者のみなし雇用制度の現状
2024年12月現在の障害者雇用の法定雇用率は2.5%ですが、雇用されている障害者数と失業中の障害者数に基づいて定期的に見直されており、2026年7月には2.7%以上(民間企業の場合)に引き上げられることが決まっています。
しかし厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」で説明されている通り、法定雇用率を達成している民間企業は50.1%であり、約半数が基準の法定雇用率に達していません。
法定雇用率に達していない主な原因は、以下の通りです。
- 障害者雇用のノウハウがない
- バリアフリー設備の導入が難しい
- 社内の理解が得られていない
- 対応できそうな業務がない
- 募集に人が集まらない・早期離職されてしまうなど
常用労働者100人超の企業の場合、障害者雇用が義務付けられていますが、上記のような原因によって障害者雇用が難しいと感じている企業も珍しくありません。
また障害者雇用を自発的に促すことを目的として、法定雇用率の未達企業から納付金を徴収することで達成企業に助成金を支給する障害者雇用納付金制度が整備されていますが、この制度によって未達企業の障害者雇用がさらに遅れてしまうケースもあると指摘されています。
こうした背景から法定雇用率の未達企業の負担を少しでも軽減しつつ、着実に障害者雇用に取り組むために国内でのみなし雇用の制度化を望む声が増えています。
障害者雇用を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
障害者雇用の義務とは?障害者雇用促進法において対象となる企業を解説
GLUGが展開している法定雇用率の遵守と社会貢献に役立つサービスはこちらのページもご覧ください。
障害者のみなし雇用制度を導入するメリット

将来的に国内で障害を持つ方のみなし雇用制度が導入された場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは障害を持つ方のみなし雇用制度を導入するメリットを紹介していきます。
直接雇用以外の方法で法定雇用率を達成できる
現在の障害者雇用は直接雇用や特例子会社・グループ会社で障害を持つ方を雇用した場合のみカウントされる仕組みですが、みなし雇用制度が導入されることで直接雇用以外でも障害者雇用に対応できるようになります。
みなし雇用制度によって就労継続支援事業所や在宅就業障害者などへの発注が法定雇用率でカウントできるようになれば、より多くの企業が法定雇用率を達成しやすくなります。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
障害を持つ方が働く機会が増える
現在の障害者雇用では、以下のように週の所定労働時間10時間以上20時間未満の重度を除く身体障害・知的障害を持つ方はカウントできない仕組みになっているため、法定雇用率の達成に影響しません。
出典:厚生労働省「障害者雇用率制度について」
障害者雇用の仕組み上、週の所定労働時間20時間未満の障害を持つ方の場合、一般企業で働く機会が限られている傾向にあります。
しかし、みなし雇用制度であれば企業の発注量が法定雇用率に換算できるようになるため、就労継続支援事業所などに通う週の所定労働時間20時間未満の障害を持つ方が活躍できる機会が広がります。
また法定雇用率を達成するために障害を持つ方に業務を発注したい企業が増えることで、就労継続支援事業所などの障害福祉事業所も現在よりも仕事(生産活動)を確保しやすくなります。
なお、GLUGでは就労継続支援事業所の開業・運営のサポートや、企業の法定雇用率を改善するための支援をおこなっています。
法定雇用率の遵守と社会貢献に役立つサービスの詳細についてはこちらのページもご覧ください。
助成金が支給される
将来的に障害者のみなし雇用制度が導入されれば、企業は実際の雇用に加え、一定の条件を満たす在宅就業障害者や委託就労者も法定雇用率の算定対象として扱うことができると考えられます。
また既存の助成金と連動して、支給額が上乗せされる可能性が高く、より企業の経済的な負担を軽減しつつ、障害者雇用が促進されることも期待できます。
みなし雇用との連携が見込まれる主な助成金制度は以下の通りです。
【在宅就業障害者特例調整金】
対象:在宅就業障害者へ仕事を発注し、対価を支払った場合に支給
支給額:1人当たり21,000円/月
特徴:業務委託を通じた継続的な障害者支援を促進
【在宅就業障害者特例報奨金】
対象:在宅就業障害者・在宅就業支援団体へ仕事を発注し、対価を支払った場合に支給
支給額:1人当たり17,000円/月
特徴:業務委託を通じて多様な形での障害者支援を後押し
【在宅就業支援助成金(環境整備支援コース)】
対象:在宅勤務に必要なICT機器・ソフトウェア等を導入する事業主
支給率:導入費用の1/2(上限あり)
特徴:在宅勤務環境の整備費用を補助し、就労継続を支援
【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】
対象:重度障害者や45歳以上の障害者など、就職困難者を常用雇用した中小企業
支給額:1人あたり最大240万円(フルタイム雇用時)
特徴:就職が困難な方の安定した雇用に向けた手厚い支援
経済的な理由で法定雇用率の達成が難しい企業にとって、みなし雇用は打開策になる可能性があるでしょう。
調整金の仕組みが変わる可能性がある
在宅就業障害者特例調整金は、在宅就業障害者・在宅就業支援団体に仕事を発注し対価を支払った場合に対価に基づく調整金が支給される制度です。
現在すでに整備されている制度であり、法定雇用率に達していない企業が仕事を発注・対価を支払った場合は在宅就業障害者特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されますが、みなし雇用制度が導入されることで現在の調整金の仕組みが変わる可能性があります。
みなし雇用制度が導入されることで調整金を受け取りつつ、法定雇用率にも換算できるようになる可能性があり、もし実現すれば企業の障害者雇用の負担の軽減につながると考えられます。
障害者のみなし雇用制度を導入するデメリット
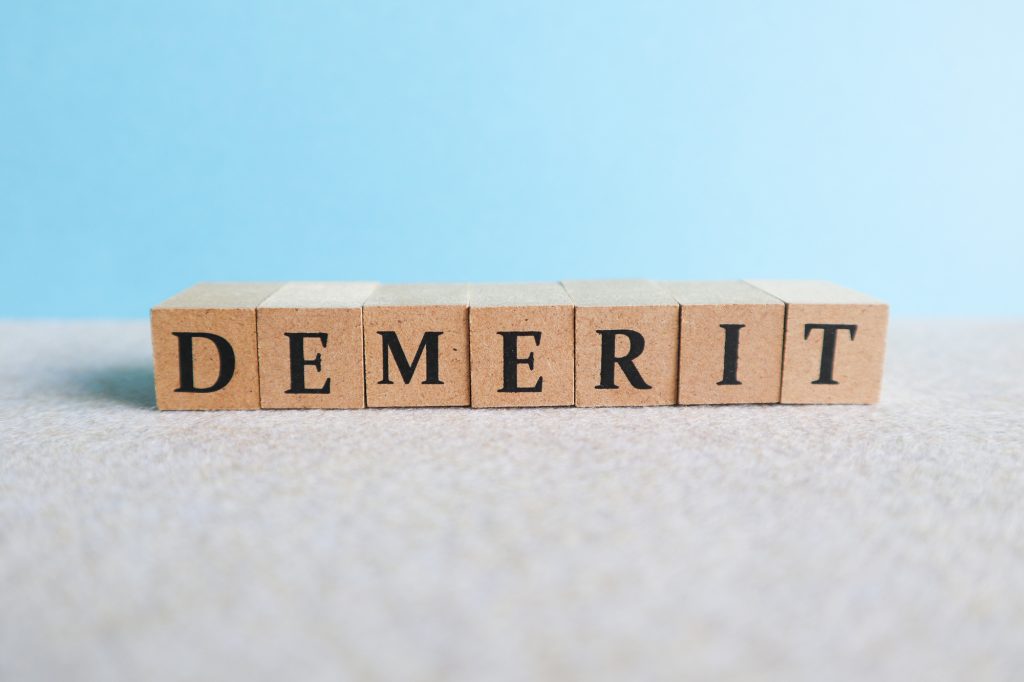
数多くのメリットがあるみなし雇用制度ですが、デメリットが議論され続けていることで現在に至るまで国内では導入されていません。
みなし雇用制度の導入によってみなし雇用で法定雇用率を達成しようとする企業が増えると、それに比例して障害を持つ方の企業の直接雇用が減ってしまうのではないかと懸念されています。
直接雇用は安定した雇用であり一定の収入を確保できるため、長期的に働くために直接雇用が適しているという意見があるほか、第197回国会参議院厚生労働委員会で厚生労働審議官の土屋喜久氏が「みなし雇用は、福祉的な就労から雇用への移行を促せなくなってしまう」とみなし雇用を慎重に考えるべきだと語っています。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!
障害者のみなし雇用制度の事例

フランスで義務付けられている法定雇用率は日本の2倍にあたる6%であり、障害者雇用を促進するためにさまざまな制度が整えられています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センターの「障害認定及び就労困難性の判定に係る諸外国の具体的実務状況等に関する調査研究~フランス・ドイツの取組」で説明されている通り、フランスでは2018年の法改正まではみなし雇用が認められていました。
雇用率50%を上限に障害を持つ労働者が働く保護労働・就労セクターへ発注することによるみなし雇用で法定雇用率を達成することができました。
その後、フランスでの実雇用率が3.5%にとどまっていたことで2018年にみなし雇用は廃止・見直され、法定雇用率未達の際に発注量に応じて納付金が減額される仕組みになっています。
難しい障がい者雇用もお任せください!
GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
\検討中でもOK!
無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/
無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら
03-6441-3820
[受付時間] 平日10:00-19:00
まとめ
障害を持つ方のみなし雇用とは、企業が就労継続支援事業所などに一定以上の発注をした際に、障害者雇用の法定雇用率に換算するという仕組みの制度です。
ノウハウがない場合でも障害者雇用に取り組みやすいなど数多くのメリットがある一方で、みなし雇用を導入することで障害を持つ方の直接雇用が減ってしまう可能性があり、導入には議論が続けられています。
障害者雇用におけるみなし雇用は国内ではまだ導入されていませんが、在宅就業障害者・在宅就業支援団体に仕事を発注・対価を支払った際に対価に応じた助成金を受け取れる在宅就業障害者特例調整金は用意されています。
将来的に国内でみなし雇用が制度化されるかどうかはまだ分かりませんが、法定雇用率は2026年7月には2.7%以上(民間企業の場合)に引き上げられることが決まっているため、新たに対象となる企業は今のうちに障害者雇用の整備を進めていくと良いでしょう。
また、GLUGでは企業の法定雇用率を改善するための支援をおこなっています。









